
最低賃金の月給計算ツール【最新版】|あなたの会社の給与は大丈夫?2025年(令和7年)10月からの最低賃金改正に対応
2024年08月01日
都道府県と労働時間を選ぶだけで、最低賃金の月額を簡単に計算できるツールです。年間休日数・月平均労総日数・月平均労働時間など、労働時間は様々な方法で計算可能です。2025年10月に改正された最低賃金に対応した最新版です。毎年10月に施行される最低賃金の改正について併せて解説しています。

2025年、2026年卒高校生採用スケジュール|高卒就活の独自ルールを解説
2024年12月12日
2025年卒、2026年卒(令和7年卒、令和8年卒)の高校新卒採用の独自ルールとスケジュールについて紹介します。ハローワークへの求人申込書受付開始から企業による選考開始まで、高校新卒採用で抑えておきたい日程について解説しています。

高卒採用の二次募集|スケジュールとポイント
2024年12月11日
実は高校新卒採用には「一次募集」と「二次募集」が存在します。 高校生は9月に学校を通して応募、選考に進み内定を得ます。 この時期が「一次募集」。 そして一次募集期間終了後に、予定採用人数に足らずさらに募集を継続するか、または追加で採用活動を行うのが「二次募集」です。 今回は二次募集について解説します。

ハローワーク求人票作成のコツ|記載項目別のポイントと例文を紹介
2024年07月02日
ハローワークの求人票には50項目以上の記載欄がありますが、その中でも特に求職者の心をつかむ重要な6項目を取り上げ、作成ポイントを紹介していきます。各例文を記載していますので、是非参考にしてみてください。 あなたの会社の求人情報をリッチ化し、応募につながる求人票に仕上げることが可能になります。

応募者との連絡にそのまま使えるメッセージテンプレート集・応募者に好かれるために必要な考え方
2025年03月02日
採用選考では、面接の日程調整、合否通知、書類提出の案内など、応募者とのメッセージのやり取りが多く発生します。 これらのやり取りは、応募者の企業に対する印象に関わるので、気を抜くのは禁物。 すぐに使えるテンプレートを用意しておくことで、適切なタイミングを逃さず、質の高いコミュニケーションを取ることができます。

高校新卒採用における求人の出し方|ハローワークへの求人票登録が必須
2024年08月17日
高校に求人を出すための手順・やり方を解説しています。高校に求人を出すには、ハローワークで高卒専用の求人票を作る必要があります。申請方法と気を付けるポイントを併せて説明。求人票の他にも高校に送付するべき採用PRコンテンツについても解説しています。

ハローワークの文字数、行数に対応!ハローワーク求人票用の文字数カウンター&表記調整ツール
2024年11月27日
ハローワーク求人票の作成時に困るのが、ハロワ独特の文字数と行数の制限。 項目ごとに縦の行数や横の文字数、全体の文字数が決まっています。 「ハローワークの求人票の作成」がより効率的にできればと想いを込めて、ハロワ求人票専用の文字数カウンター&表記調整ツールを作成しました。 是非ご活用ください!
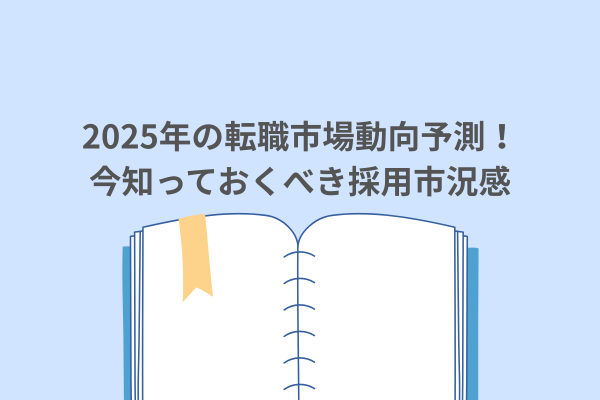
2025年の転職市場動向予測!今知っておくべき採用市況感
2025年07月15日
2025年の転職市場や中途採用の市況感について知りたい企業の人事担当者や経営者の方に向けて執筆しています。 最新の市場動向や注目トレンド、業界別・地域別の採用事情、今後の採用戦略や成功のポイントまで解説します。 2025年の採用・転職市場で成功するために、今知っておくべき情報を網羅した記事です。


