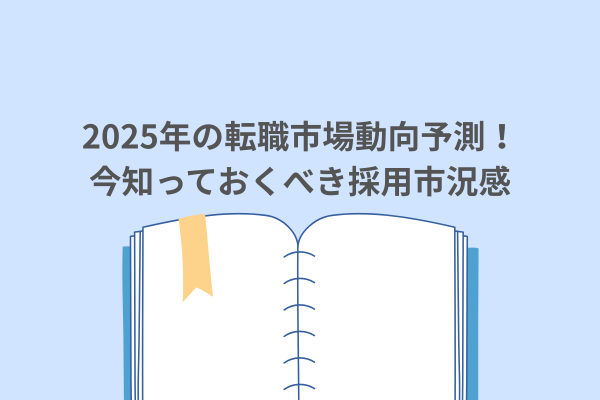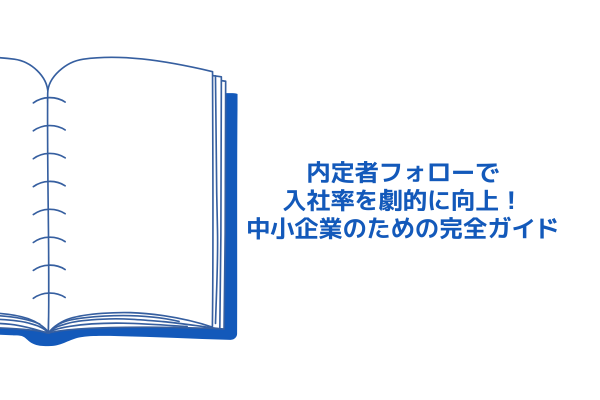近年、採用市場は大きな変化を遂げており、特に中小企業は人材獲得において厳しい状況に置かれています。
従来の「安定志向」から「自己成長」「ワークライフバランス」「社会貢献」など、求職者の価値観は多様化しています。
中小企業は、これらのニーズに応えるための柔軟な働き方やキャリアパスの提示が求められていると言えるでしょう。
さらに、情報過多による求職者の企業選択の複雑化も見逃せません。
インターネットやSNSの普及により、求職者は膨大な量の企業情報にアクセスできるようになりました。しかし、情報が多すぎるために、どの企業を選べば良いのか判断に迷う求職者も少なくありません。中小企業は、自社の魅力を効果的に発信する工夫が必要です。
中小企業は、大企業に比べて採用活動にかけられる予算や人員が限られている場合が多く、採用力は低い傾向にあります。
また、ブランド力が低い企業は、求職者からの認知度が低く、応募が集まりにくいという課題も抱えているのが現状です。
このような背景と少子高齢化による働き手の不足により、企業間の人材獲得競争は激化の一途を辿っています。
このような環境で中小企業が採用を成功させるには、「応募者を取りこぼさないこと」がポイントです。
他社と競合しながら採用活動を行い、ようやく内定を出しても、応募者が別の企業に行ってしまう...ということはよく発生します。この取りこぼしを0に近付けることが、中小企業の採用力アップの近道なのです。
この記事では、内定辞退を起こさない、内定者へのフォローに際しての思考法と方法を解説していきます。
内定者のホンネと企業の誤算:中小企業が陥りがちな落とし穴
内定者の心理:期待と不安、そして企業に求めるもの
内定を獲得した求職者は、期待と不安が入り混じった複雑な心理状態にあります。
期待としては、新しい環境で自分の能力を発揮し、自己成長できるワクワク感。社会人としての生活への期待などが挙げられます。
一方、不安としては、職場での人間関係、仕事内容への適性、企業文化へ馴染みめるかなどが考えられます。
特に中小企業の場合、大企業に比べて情報が少ないため、入社後の具体的なイメージを持ちにくいという不安を抱える求職者も少なくありません。
そのため、内定者は企業に対して、以下のような情報を求めています。
| 内定者が企業に求めている情報 |
|
・入社後の具体的な仕事内容やキャリアパス
・職場の雰囲気や人間関係
・研修制度やサポート体制
・企業のビジョンや将来性
|
これらの情報が不足していると、内定者は不安を募らせ、内定辞退につながる可能性が高まります。
中小企業の誤解:内定を出せば安心?コミュニケーション不足の代償
中小企業の中には、「内定を出せば応募者は必ず入社してくれる」と誤解しているケースが少なくありません。
しかし、実際には、内定を出してから入社までの期間に、内定者の気持ちは大きく変化する可能性があります。
就職みらい研究所やマイナビの調査によると、新卒学生の内定辞退率は約6割で、中途採用の場合の内定辞退率は約1割あります。
特に、中小企業の場合、大企業に比べて内定者フォローの体制が整っていないことが多く、以下のようなコミュニケーション不足に陥りがちです。
| 内定者とのコミュニケーション不足例 |
|
・内定者への連絡頻度が少ない
・内定者の質問や相談に十分に対応しない
・内定者同士の交流機会がない
・入社前の不安を解消する情報提供が不足している
|
このようなコミュニケーション不足は、内定者の不安を増幅させ、内定辞退につながる大きな要因となります。
以下に、こうしたコミュニケーション不足が内定辞退を招いた中小企業の失敗ケースを紹介します。
・事例1:情報提供不足による不安
内定後、企業からの連絡がほとんどなく、仕事内容や研修制度についての情報も不足していた。
内定者は、入社後の具体的なイメージを持つことができず、不安を募らせ、最終的に内定を辞退した。
・事例2:内定者フォロー不足による孤立感
内定者懇親会などの交流機会がなく、内定者は同期との繋がりを感じられなかった。
また、内定者自身が「会社は自分たちをあまり見てくれていない」と不安に思った。
入社前に相談できる相手もおらず、孤立感を深め、内定を辞退した。
・事例3:入社後のミスマッチ
面接時に聞いていた仕事内容と、実際に入社後に任された仕事内容が大きく異なっていた。
企業文化にも馴染めず、早期退職に至った。
これらの事例から分かるように、内定者フォローの不足は、内定辞退だけでなく、早期退職にもつながる可能性があります。
中小企業は、内定者の心理を理解し、丁寧なコミュニケーションと情報提供を行うことが重要です。
中小企業が優秀な人材を確保し、定着させるためには、内定者フォローの重要性を認識し、積極的に取り組む必要があります。
内定辞退を防ぎ、入社意欲を最大限に高める!中小企業のための戦略的アプローチ
企業の魅力を再発見:中小企業ならではの強みを効果的に伝える
中小企業は、大企業に比べて規模は小さいものの、独自の強みを持っています。
例えば、社員一人ひとりの裁量が大きく、若いうちから責任ある仕事を任せてもらえることや、社員同士の距離が近く、良い雰囲気で働けることなどが挙げられます。
会社の代表との距離感が近いことや、社内(社員)全体を見渡せる風通しの良さもあるでしょう。
内定者フォローでは、これらの強みを具体的に伝え、内定者に「この会社で働きたい」「自分の選択は誤っていなかった」と思ってもらうことが重要です。
企業の強みを再発見し、ターゲット層に響く言葉で伝えることで、内定者の入社意欲を高めることができます。
内定者のグリップでは、「エンゲージメント」を高める意識を持つと効果的。
詳しくは下の記事で紹介していますので、是非参考にしてください。
内定者フォローでは、企業と内定者の信頼関係を築くことが重要です。
一方的な情報発信ではなく、内定者の疑問や不安に寄り添い、共感を呼ぶ情報発信を心がけましょう。
具体的には、以下のような取り組みが考えられます。
| 内定者への情報発信の方法例 |
|
・内定者向けのコミュニケーショングループを作成し、気軽に質問や相談ができる場を提供する。
・定期的にアンケートを実施し、内定者の不安や疑問を把握する。
・個別の面談や電話で、内定者の悩みや相談に丁寧に対応する。
|
内定者一人ひとりと向き合い、丁寧なコミュニケーションを重ねることで、内定者は企業への信頼感を高め、入社意欲を高めることができます。
また、会社のnoteやXなどのSNSを使って、定期的に社内の様子や出来事を発信していくことも効果的です。
特にnoteでは、社員のキャリアパス、仕事のやりがい、身につくスキルや、会社の強み、サービスの特徴を詳しく伝えることができます。
noteの記事は投降したあとに消えてしまうということがありません。
積み重ねていくことで、重層的な情報提供が可能になります。
入社後のキャリアパスを提示:成長と貢献を具体的にイメージさせる
内定者は、選考中に「自身の将来・なりたい理想像」と「会社でできること・会社の将来」とのリンクを確認しています。
つまり、入社後のキャリアパスに強い関心を持っていることが多いです。
中小企業は、大企業に比べてキャリアパスが不明確な場合があるため、入社後の成長と貢献を具体的にイメージさせることが重要です。
具体的には、以下のような情報を面談やメール、note等のSNSで提供しましょう。
| 内定者への情報提供例 |
|
・入社後の具体的な仕事内容や研修制度
・若手社員のキャリアアップ事例
・将来的なキャリアパスの可能性
|
内定者が入社後の自分の成長と貢献を具体的にイメージできるような情報を提供することで、入社意欲を高めることができます。
内定者同士のコミュニティの形成:仲間意識を高め、不安を解消する
内定者は、同期入社の仲間との繋がりを求めています。
特にZ世代と言われる若い年齢層の求職者は、周囲とのつながりを大事にしています。
内定者同士のコミュニティを形成することで、仲間意識を高め、入社前の不安を解消することができます。
具体的には、以下のような取り組みが考えられます。
| 内定者同士のコミュニティ形成例 |
|
・内定者懇親会や交流会を開催する。
・内定者向けのSNSグループを作成し、情報交換や交流の場を提供する。
・内定者同士でグループワークや課題に取り組む機会を設ける。
|
内定者同士が交流を深め、仲間意識を高めることで、入社への不安を解消し、一体感を醸成することができるのです。
中小企業のための内定者フォロー実践マニュアル:今日からできる!具体的施策
内定通知:感動と期待感を醸成する、記憶に残る通知方法
内定通知は、内定者にとって人生の大きな節目となる瞬間です。
電話やメールだけでなく、手書きのメッセージや、内定者の個性や選考中のエピソードに合わせたオリジナルの通知方法を取り入れることで、感動と期待感を醸成し、企業への好感度を高めることができます。
この際には、内定者が「自分のことをよく見てくれている」と重要感を持てる内容を伝えることがポイント。
「あなただからこそ」と分かるメッセージが効果的です。
選考中の評価ポイント、入社後に期待していることを伝えましょう。
定期的な情報提供:企業の最新情報、社員紹介、Q&Aセッション
内定者は、入社までの期間に企業への理解を深めたいと考えています。
企業の最新情報、社員紹介、Q&Aセッションなどを定期的に提供することで、内定者の不安を解消し、企業への帰属意識を高めることができます。
企業の最新情報は、事業の進捗状況や新サービスの発表など、内定者が興味を持ちそうな情報を積極的に発信しましょう。
社員紹介では、若手社員のインタビュー記事や動画を掲載することで、内定者は入社後の自分をイメージしやすくなります。
この際には、内定者と似た経歴の社員や、内定者が希望している職種、キャリアの社員を紹介することで「親近感」を持ってもらいやすくなります。
Q&Aセッションでは、内定者からの質問に丁寧に回答することで、企業への信頼感を高めることができます。
双方向コミュニケーション:個別面談、座談会、懇親会、オンライン交流
内定者との信頼関係を構築するためには、双方向のコミュニケーションが欠かせません。
個別面談、座談会、懇親会、オンライン交流など、様々な方法で内定者とコミュニケーションを取りましょう。
個別面談では、内定者一人ひとりの悩みや不安に寄り添い、丁寧に対応することが重要です。
座談会や懇親会では、内定者同士や社員との交流を促進し、企業への親近感を高めることができます。オンライン交流では、遠方に住む内定者とも気軽にコミュニケーションを取ることができます。
あなたの会社の人員や時間に余裕があれば、お客さんに会ってもらうのも効果的です。
自分が働くことになる会社が満たしているニーズ、お客さんの声や笑顔を見ることで、その仕事をする意義を見出しやすくなります。
入社前研修:スムーズなスタートダッシュを支援する、実践的プログラム
入社前研修は、内定者がスムーズにスタートダッシュを切るための重要なプログラムです。
ビジネスマナー研修、PCスキル研修、グループワークなどを通して、内定者の不安を解消し、即戦力となるための準備をサポートしましょう。
特に中小企業の場合、入社後のOJTが中心となるケースが多いため、入社前研修で基本的なスキルを習得しておくことは、内定者にとって大きな安心材料となります。
メンター制度:先輩社員との個別サポートで、安心感と帰属意識を醸成
メンター制度は、先輩社員が内定者の相談役となり、個別サポートを行う制度です。
メンターは、内定者の不安や疑問に答えたり、キャリアに関するアドバイスをしたりすることで、内定者の安心感と帰属意識を高めます。
メンターは、内定者の年齢やキャリアプランに合った社員を選任することが重要です。また、定期的な面談や交流会を通して、メンターと内定者の関係性を深めることが大切です。
社内イベントへの招待:企業文化を体感し、社員との距離を縮める
社内イベントへの招待は、内定者が企業文化を体感し、社員との距離を縮める絶好の機会です。
忘年会、社員旅行、スポーツ大会など、様々なイベントに内定者を招待し、企業の一員としての意識を高めましょう。
イベントを通して、内定者は社員と交流を深め、企業への親近感を高めることができます。また、企業の雰囲気を肌で感じることで、入社後のイメージを具体的に描くことができます。
オンラインを活用したフォロー: 効率的かつ効果的なコミュニケーション
オンラインを活用したフォローは、時間や場所にとらわれずに、効率的かつ効果的に内定者とコミュニケーションを取るための手段です。
オンライン説明会、オンライン懇親会、オンライングループワークなどを通して、内定者との交流を深めましょう。
オンラインを活用することで、遠方に住む内定者とも気軽にコミュニケーションを取ることができます。また、動画や資料を共有することで、内定者の理解を深めることができます。
フォロー施策の効果測定と改善: PDCAサイクルで質を高める
内定者フォローの効果を測定し、改善することは、より質の高いフォローを実現するために不可欠です。
内定者アンケート、内定辞退率の分析、入社後に現場社員からのフィードバックなどを通して、フォロー施策の効果を測定し、改善点を見つけましょう。
PDCAサイクルを回すことで、内定者フォローの質を継続的に高め、内定者の満足度向上と内定辞退率の低下に繋げることができます。
内定者との効果的なコミュニケーション:連絡手段とタイミング
メール、電話、SNS、オンライン会議ツールの使い分け
内定者とのコミュニケーション手段は、メール、電話、SNS、オンライン会議ツールなど多岐にわたります。
それぞれの特徴を理解し、状況に応じて使い分けることが重要です。
①メール
重要な情報や正式な連絡に適しています。
内定通知、入社書類の送付、研修案内などに活用しましょう。
履歴が残るため、後から確認したい場合に便利です。
選考中に使える、応募者へのメッセージテンプレートは下の記事からご確認ください。
②電話
緊急の連絡や、個別の相談に適しています。
内定承諾の確認、面談日程の調整、個人的なフォローなどに活用しましょう。
声のトーンや話し方で、より親密なコミュニケーションが可能です。
③SNS
カジュアルな情報共有や、内定者同士の交流に適しています。
企業の日常や社員の紹介、イベント告知などに活用しましょう。
双方向のコミュニケーションが取りやすく、内定者の反応を把握しやすいです。
④オンライン会議ツール
複数人での情報共有や、遠隔地の内定者とのコミュニケーションに適しています。
オンライン説明会、グループワーク、個別面談などに活用しましょう。
画面共有やチャット機能など、多様なコミュニケーションが可能です。
内定者の状況に合わせた連絡頻度と内容
内定者の状況は一人ひとり異なるため、画一的な連絡ではなく、個別に合わせた連絡頻度と内容を心がけましょう。
頻繁な連絡を好む内定者には、こまめに情報提供や交流の機会を設けます。
じっくり考えたい内定者には、適度な距離感を保ちつつ、必要な情報を提供します。
不安を抱えている内定者には、個別面談や相談窓口を設け、丁寧に対応しましょう。
新卒学生の内定者の場合には、常に連絡のとれる窓口設け、質問を受け付けるのと同時に、月に1回ほどnoteの記事や社内報を共有すると良いでしょう。
社内イベントなどがあれば、その際の写真を送り、様子を伝えるのも定期的な連絡として効果的です。
大卒新卒の年間スケジュールは下の記事で解説しています。
大学生のスケジュールを把握した上で、時期に合った連絡と頻度を心がけましょう。
情報提供、質問対応、相談受付など、目的別のコミュニケーション設計
内定者へのコミュニケーションの目的によって、最適な手段や内容が異なります。
それぞれ見ていきましょう。
①情報提供
企業の最新情報、社員紹介、研修案内などを提供します。
メールやSNS、オンライン説明会などを活用しましょう。
内定者が興味を持ちそうな情報を、分かりやすく伝えることが重要です。
②質問対応
内定者の疑問や不安に、迅速かつ丁寧に回答します。
メールや電話、チャットなどで、個別の質問に対応しましょう。
FAQページを作成し、よくある質問をまとめておくことも有効です。
③相談受付
内定者の悩みや相談に、親身に寄り添い、適切なアドバイスを提供します。
個別面談や相談窓口を設け、プライバシーに配慮した環境で話を聞きましょう。
必要に応じて、専門家や関係部署と連携することも検討しましょう。
また、内定者のタイプによって、効果的な連絡方法は異なります。
内定者タイプ別のフォローのポイントは下の通り。
①積極的な内定者には?
情報提供や交流の機会を積極的に設け、主体性を尊重しましょう。
インターンシップやアルバイトなど、入社前に企業に貢献できる機会を提供することも有効です。
②慎重な内定者には?
丁寧な言葉遣いや、個別の相談機会を設け、安心感を与えましょう。
内定者同士の交流会など、徐々に企業に慣れてもらう機会を設けましょう。
③個性的な内定者には?
個性を尊重し、型にはまらないコミュニケーションを心がけましょう。
SNSやオンラインツールを活用し、多様なコミュニケーション手段を提供しましょう。
内定者一人ひとりの個性を意識し、最適なコミュニケーション方法を選択することで、内定者の満足度を高め、入社意欲を向上させることができます。
中小企業が内定者フォローで成果を上げるための重要ポイント
内定者フォローを「投資」と捉え、戦略的に取り組む
中小企業にとって、採用活動は時間もコストもかかる重要な業務です。
せっかく内定を出した優秀な人材に入社してもらうためには、内定者フォローを「投資」と捉え、戦略的に取り組む必要があります。
内定者フォローは、単に内定者の不安を解消するだけでなく、企業へのエンゲージメントを高め、入社後の活躍を促進するための重要なプロセスです。
長期的な視点を持ち、内定者の成長を支援する戦略的なフォローアップを行いましょう。
内定者の視点に立ち、真摯なコミュニケーションを心がける
内定者は、入社前に様々な不安や疑問を抱えています。内定者の視点に立ち、真摯なコミュニケーションを心がけることが、信頼関係を築く上で最も重要です。
一方的な情報提供ではなく、内定者の質問や相談に丁寧に耳を傾け、個別のニーズに合わせた対応を心がけましょう。内定者の不安を解消し、企業への安心感を高めることで、入社意欲の向上に繋がります。
組織全体で内定者フォローに取り組み、入社後の活躍を支援する
内定者フォローは、採用担当者だけの仕事ではありません。組織全体で内定者を迎え入れる体制を構築し、入社後の活躍を支援することが重要です。
現場社員との交流機会を設けたり、メンター制度を導入したりすることで、内定者は企業への帰属意識を高め、安心して入社することができます。
組織全体で内定者の成長を支援する姿勢を示すことで、内定者のエンゲージメントを高め、入社後の定着率向上に繋がります。
採用担当者の役割→内定者と組織をつなぐキーパーソン
採用担当者は、内定者と組織をつなぐ重要な役割を担っています。内定者の不安や疑問を解消し、組織への理解を深めるための情報提供やコミュニケーションを積極的に行いましょう。
また、内定者の情報を組織内に共有し、入社後のスムーズな受け入れ体制を構築することも重要です。採用担当者が内定者と組織の橋渡し役となることで、内定者は安心して入社し、組織の一員として活躍することができます。
中小企業が内定者フォローで成果を上げるためには、上記のポイントを意識し、内定者との信頼関係を築き、組織全体で内定者の成長を支援することが重要です。
まとめ
この記事では、中小企業が厳しい採用市場を勝ち抜き、優秀な人材を獲得・定着させるための「内定者フォロー」の重要性と具体的な戦略について解説しました。
労働人口の変化、求職者の価値観の多様化、情報過多による企業選択の複雑化など、中小企業を取り巻く採用環境は厳しさを増しています。
このような状況下で、内定辞退を防ぎ、入社意欲を高めるためには、内定者フォローを戦略的に行うことが不可欠です。
内定者の心理を理解し、企業の魅力を的確に伝え、信頼関係を築くためのコミュニケーションを丁寧に行うことが重要です。
また、組織全体で内定者を迎え入れ、入社後のキャリアパスを提示することで、内定者の不安を解消し、エンゲージメントを高めることができます。
内定者フォローは、単なる事務作業ではなく、未来の組織を担う人材への「投資」です。
内定者の視点に立ち、真摯なコミュニケーションを心がけ、組織全体で内定者の成長を支援することで、中小企業は優秀な人材を確保し、持続的な成長を実現することができるでしょう。