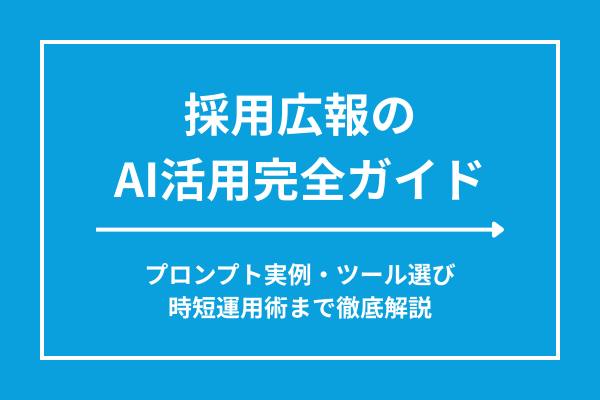採用広報に生成AIを活用できていますか?
2022年に登場した生成AI(Generative AI)は、単なる業務効率化のツールという枠を超えて、企業の競争力を決定づけるインフラになりつつあります。
従来の採用プロセスでは、母集団形成から書類選考、面接、内定出しまでに数ヶ月を要することも珍しくありませんでした。しかし、HR総研の調査が示すように、2025年卒採用においては、大手企業の半数近くが2月までに内定出しを開始するなど、スケジュールの早期化が顕著になってことがわかっています。
この加速する採用活動に対応するためには、人間の処理能力だけに頼る従来型の手法では限界があり、AIによるプロセスの自動化・高速化が不可避となっています。
もはや、AI活用は「先進的な技術」ではなく、「全ての社会人が身につけるべき必須条件」なのです。
この記事では、採用広報の担当者が現場ですぐにAIを活用するための、実践的なノウハウを網羅しました。
読み終える頃には、採用広報に生成AIを活用できるようになるはずです。まずは、なぜ今これほどまでにAI活用が必要とされているのか、その理由から解説します。
- そのまま使える「実務直結プロンプト」
- 競合がまだ十分に対策していない「AI検索(LLMO)対策」
- 運用を継続するための「現実的な体制づくり」
なぜ今、採用広報に生成AIが必須なのか?
「AIを使えば楽ができるから」——もしそう考えているなら、認識を少し改める必要があります。
もちろん、業務効率化は大きなメリットです。しかし、採用広報においてAIが不可欠な理由は、人手不足の解消だけではありません。「情報の届け方」と「情報の受け取られ方」の質が、大きく変化しているからです。

「企業視点」から「候補者視点」への転換をAIが加速させる
採用広報で陥りやすい失敗、それは「企業が言いたいことだけを伝えてしまう」ことです。
「アットホームな職場です」「成長できる環境です」といった聞こえの良い言葉は、企業側の主観に過ぎません。一方で、候補者が本当に知りたいのは「人間関係のトラブルはないか?」「残業の実態はどうなのか?」という、現実的な懸念への回答です。
人間が記事を書くと、どうしても無意識に「良いこと」を書こうとする傾向があります。しかし、AIは違います。
口コミサイトのデータや市場のトレンドをAIに読み込ませることで、以下のような客観的な分析が可能になります。
- 「御社のターゲット層は、『成長』よりも『心理的安全性』を求めている傾向があります」
- 「このアピール内容では、競合他社A社との差別化ができていません」
つまり、AIを活用する目的は、手抜きをすることではなく、候補者のニーズ(本音)への理解を深めることにあります。
自分たちの思い込みを捨て、候補者が本当に求めている情報を提供する。この「視点の転換」を強制的に行ってくれることこそが、AI導入の大きな価値なのです。
検索の未来が変わる!SEOとLLMO(AI検索)の違い
もう一つ、見逃せない変化があります。それは、求職者の「検索行動」の変化です。
長年、採用広報のデジタル戦略といえば、Google検索における上位表示を狙う「SEO(検索エンジン最適化 - Search Engine Optimization)」が主戦場でした。
「エンジニア 採用 東京」「働きやすい会社 ランキング」といったキーワードで検索結果の1ページ目に表示されることが、母集団形成の勝敗を分けていました。
しかし、2024年から2025年にかけて、この前提は崩れ去ろうとしています。
ChatGPT Search、Perplexity、GoogleのSGE(Search Generative Experience)といった「AI検索エンジン」の台頭によって、ユーザーの情報探索行動は「検索してリンクをクリックし、自分で情報を探す」スタイルから、「AIに質問し、要約された回答を得る」スタイルへと変質しています。

マイナビの調査で就職活動中の学生の生成AI利用について聞いたところ2024年卒と2025年卒で大きな変化が見られた。
利用経験ありの学生は2024年卒から2025年卒にかけて23.7pt増え、利用経験なしの学生は23.6pt減ったため、利用経験の有無については1年間で逆転した結果となった。この結果から生成AIの利用が大学生へも広がっている様子がうかがえる。
この新たな環境下における最適化戦略は、「LLMO(大規模言語モデル最適化 - Large Language Model Optimization)」と呼ばれ、多くの企業に注目されています。
「キーワードの含有率」や「被リンク数」といった従来のSEOテクニックは、AI検索には通用しません。AIに「信頼できる情報源」として認識されるためには、以下の要素が不可欠です。
1. 一次情報と権威性の担保
AIは、政府統計、学術論文、業界団体のデータなど、権威性の高い情報源を好む傾向があります。
採用広報の例としては、「働きやすい職場です」と主張したい場合は、「厚生労働省のくるみん認定取得」「平均残業時間の推移データ」といった、働きやすさを裏付ける客観的なデータを明記するとAIに引用されやすい情報になります。
2. 構造化データとFAQの実装
AIが情報を正しく理解し、学習するためには、HTML上のマークアップが重要です。
特に「よくある質問(FAQ)」をSchema.orgのFAQPage構造化データを用いて実装することで、AIは質問と回答のペアを正確に認識できるようになります。
SGEの回答生成において、引用されるコンテンツの多くは、質問に対する「直接的な回答」が簡潔に記述されている箇所から抽出される傾向があります。
FAQ形式(質問+回答)の構造化データは、この「直接的な回答」をAIに明示する役割を果たすため、引用の可能性を高めると考えられています。
採用サイトにおいては、「給与体系」「リモートワーク規定」「選考フロー」といった定型的な情報をFAQ形式で整理し、構造化データとして埋め込むことが、LLMO対策の第一歩となります。
3. ネガティブ情報の戦略的開示と整合性
エン・ジャパンの調査によると、求職者の約70%が企業のネガティブ情報を閲覧していることがわかっています。
例えば、公式情報で「残業なし」と謳っていても、OpenWorkやキャリコネなどの口コミサイトに「月40時間のサービス残業が常態化」という書き込みが多数あれば、PerplexityのようなAI検索エンジンは「公式には残業なしとされているが、口コミでは実態が異なるとの声がある」という回答を生成する可能性があります。
つまり、自社の採用サイトを運営する際には、課題や困難な側面も含めて正直に開示し、口コミ情報との整合性を保つことが、結果としてAIからの信頼獲得につながります。

【そのまま使える】採用広報業務を効率化するAI活用ステップ
AIツールを導入したものの、「当たり障りのない文章しか出てこない」「他社の求人票と区別がつかない」という悩みを抱える採用担当者は多いです。
これは、AIの能力不足ではなく、入力する「プロンプト(指示命令文)」の精度に起因する場合が大半です。本章では、採用業務に特化したプロンプトの実例と改善テクニックを解説します。
1. プロンプトの基本構造:まずはプロンプトの作り方の基本を理解する
効果的なプロンプトを作成するためには、AIに対して「誰になりきって」「どのような文脈で」「どのような制約条件の下で」といった、どのように出力すべきかを明確に指示することで、回答の品質を高めることが可能です。

基本フォーマット例
Role(役割)
あなたはIT業界に特化した、キャリア10年のベテラン採用広報担当者です。 ターゲット心理を深く理解し、心を動かす文章作成に長けています。
Context(背景)
当社は創業5年のSaaSスタートアップです。現在、エンジニア組織の拡大に伴い、テックリード候補を募集しています。 技術的な挑戦環境はあるものの、給与面ではメガベンチャーに劣る部分があり、「やりがい」と「裁量権」を訴求したいと考えています。
Target Persona(ターゲット)
- 30代前半、現職では開発リーダー
- 大企業での意思決定の遅さにフラストレーションを感じている
- 技術選定から携わりたいという意欲が強い
Task(タスク)
上記のターゲットに向けたスカウトメールの文面を作成してください。
Constraints(制約条件)
- 件名は30文字以内、開封率を高める工夫をする
- 本文は400文字程度
- 「成長」「挑戦」といった抽象的な言葉は避け、具体的なエピソードを盛り込む(エピソードは後述の[参照情報]を使用)
- 丁寧すぎず、かつ失礼にならない「プロフェッショナルな親近感」のあるトーン
2. 企画・ペルソナ設計:「関心を引く切り口」をデータから抽出
採用広報の記事を書く際、「20代後半の若手向け」といった曖昧なターゲット設定で書き始めていませんか? これでは誰の関心も引けません。
AIを使えば、既存社員の属性や、口コミサイトにある競合の評判から、候補者の「本音やニーズ」を明確にできます。人間が頭で考える「想像上のターゲット」ではなく、データに基づいた「リアルな悩み」を抽出しましょう。
以下のプロンプトを使用すると、候補者が読みたくなる記事の切り口が見つかります。
あなたは優秀な採用コンサルタント兼編集者です。
以下の情報を元に、ターゲット候補者が「この会社なら自分の悩みが解決できるかも」と感じる記事の企画案を5つ提案してください。
* ターゲット属性:30代前半、SaaS企業のフィールドセールス経験者
* ターゲットの現状:数字を追うだけの毎日に疲弊しており、もっと顧客の本質的な課題解決に関わりたいと考えている(と仮定)
* 自社の魅力:売って終わりではなく、カスタマーサクセスまで一気通貫で関われる体制がある
1. 記事タイトル案(30文字以内・クリックしたくなるもの)
2. 記事の狙い(ターゲットのどの感情に訴求するか)
3. 構成の骨子(箇条書き3点)
3. 記事執筆:社員インタビューの自動化フロー(録音〜要約)
ひとり人事にとって大きな負担は、「インタビュー音源の文字起こしと編集」ではないでしょうか。1時間のインタビューを記事にするには、通常4〜5時間かかります。
しかし、AIを活用した以下のフローなら、作業時間を約1/3(1.5時間程度)まで短縮可能です。(弊社実績)
録音・文字起こし
「CLOVA Note」や「Zoomの文字起こし機能」でテキスト化
構成作成
ChatGPT等のLLMにテキストを読ませ、構成案を作成させる
本文執筆
構成に基づき、AIに執筆させる
ここで注意すべきは、「そのまま出力すると、機械的で単調な文章になる」という点です。
これを防ぐため、執筆指示のプロンプトには必ず「トーン」の指定を入れてください。
このように「口癖を反映して」「熱意のあるトーンで」と指示するだけで、AI特有の不自然さが消え、親しみやすい記事に仕上がります。
4. 効果測定:高価なツールは不要!見るべき3つのKPI
記事を公開した後、「何人に見られたか(PV数)」だけで満足していませんか?
採用広報の目的は、多くの人に読まれることではなく、「自社にマッチする人材からの応募」につなげることです。
高額な分析ツール(TaleBIなど)が推奨されることもありますが、初期段階では不要です。

|
指標(KPI) |
見るべき理由 |
目安・対策 |
|
1. 平均エンゲージメント時間 |
「中身が読まれているか」を判断するため。PVが多くても、ここが10秒以下なら読まれていません。 |
1分以上を目指す。短い場合は、導入文で読者の課題に触れられていない可能性があります。 |
|
2. 読了率(スクロール率) |
記事の最後まで到達した人の割合。 |
GA4のイベント設定で計測。50%以下なら、途中で離脱されています。見出しや画像の配置を見直しましょう。 |
|
3. 応募ページへの遷移率 |
記事を読んで行動変容が起きたかどうかの最重要指標。 |
記事末尾のリンク(CTA)がクリックされた割合。1〜3%あれば合格点です。 |
これら3つの数字を定点観測することで、「どの記事が採用に貢献しているか」が明確になります。高機能なツールを導入するよりも、この基本指標を改善し続ける方が、確実に成果につながります。
採用担当者におすすめのAIツール
世の中には無数のAIツールが溢れていて、どのツールを導入すべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、AIツールを「汎用LLM」「採用業務特化AI」「画像・動画生成AI」の3つのカテゴリーに分けて、それぞれ導入するべきか解説します。
1. 汎用LLM(ChatGPT, Claude, Gemini)
最も汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れるのが、GoogleのGemini、OpenAIのChatGPT、AnthropicのClaudeなどの基盤モデルです。
これらは、記事作成、ブレインストーミング、要約、翻訳チェックなど、あらゆるテキスト業務に対応可能です。
「ChatGPTとGeminiってどっちがいいの?」という質問をよくいただきますが、基本的にどちらでもOKです。既に会社で利用されているLLMがあれば、そちらを利用するようにしましょう。
※生成AIを利用するときは、会社や上司に利用可否を確認するほうが安全です。
- 採用ブログの構成案作成
- 採用ブログの執筆
- 採用戦略の壁打ち
- キャッチコピーのアイデア出し(「100案出して」といった発散思考)
- 市場調査・競合分析 など

弊社ミズサキでは、Geminiをメインに使用しています。汎用LLMは、インフラといって良いほど利用頻度が高いAIです。
まだ生成AIを業務に取り入れていない方は、どれか1つは使えるようにしておきましょう。
今使っているAIがない場合は「ChatGPT」、会社でGoogleWorkspaceを導入している場合は「Gemini」を使うのが無難です。
2. 採用業務特化型AIツール
採用フローに特化してファインチューニングされたツールや、求人媒体が提供するAI機能である。マイナビとElyzaが開発した求人原稿作成AIなどがこれに該当します。これらは、各媒体のレギュレーションやNGワードを学習済みであるため、修正の手間が少なく、即座に実務に投入できる利点があります。
- 求人票(JD)の自動生成
- スカウトメールの自動送信・効果測定
- エントリーシートの自動スクリーニング

採用業務に特化したAIは、余裕があれば導入を検討しましょう。
3. 画像・動画生成AI(Midjourney, Runway, Sora)
Z世代向けのSNS発信では、ビジュアルコンテンツの重要性が増します。
デザイナーのリソースが不足している場合、画像生成AIを用いて採用ピッチ資料の挿絵や、SNS投稿用のアイキャッチ画像を作成することで、クリエイティブの質を保ちながら制作量を増やすことができます。
- 記事のサムネイル作成
- 採用スライドの背景画像作成
- Instagram投稿用のイメージ画像生成
- ショート動画の台本・コンテ作成

ひとり人事の限界…AI活用における「注意点」と対策
ここまで、AIを使って効率的に記事を作るための具体的な手順をお伝えしてきました。「これなら自分でもできそうだ」と思われたかもしれません。
しかし、ツールやプロンプトを知っていることと、それを「実務で使いこなし、成果を出し続けること」は違います。多くの企業がAI導入後に直面する「課題」について、事前に知っておいてください。
「AIっぽさ」が採用ブランドに影響するリスク
懸念点の一つは、AIに一任した記事から感じる「人間味のなさ」です。
最近、求職者のリテラシーは高まっています。「環境が整っています」「非常にやりがいがあります」といった、AI特有の無難な文章は、「AIで書いたのではないか」「本音が隠されているのではないか」と推測される可能性があります。
結果として、「形式的な会社」という印象を与え、採用ブランディングにおいてマイナスになりかねません。
これを防ぐためには、AIが出力した文章に対し、人間による適切な編集(リライト)が不可欠です。
| チェック項目 | 内容 |
| 事実確認・ファクトチェック | 生成された実績数値や制度内容は正確か? (ハルシネーションの防止) |
| 差別化・独自性 | 他社でも言える一般的な表現になっていないか? |
| 倫理チェック | 特定の属性に対するバイアスや、不適切な表現が含まれていないか? |
AIは平均的な文章を作るのは得意ですが、読み手の心に深く響く「共感」を作るのは苦手です。

継続の壁:ツールを入れても「運用する時間」がない
もう一つの課題は、「物理的な時間不足」の問題です。
よくあるのが、次のようなケースです。
- 「ChatGPTの有料版を契約したが、日々の面接対応に追われ、ほとんど利用していない」
- 「高機能な採用マーケティングツールを導入したが、設定が複雑すぎて放置されている」
これは、担当者の怠慢ではありません。単純に、AIを使っても「誰かが操作する必要がある」事実は変わらないからです。
プロンプトを考え、出力された内容をチェックし、CMS(入稿画面)に貼り付け、画像を定し、SNSで拡散する……。AIによって「書く時間」が削減されても、これら周辺業務の手間は残ります。
本来、あなたのコア業務は「目の前の候補者と向き合い、コミュニケーションをとること」です。

初期費用0円・リスクなしで始める「第3の選択肢」
「AIの必要性は理解した。だが、自分でやる時間はないし、質の低い記事を出して会社の評判を落とすのも避けたい」
ここまで読まれて、そう感じていませんか?
多くの担当者が、「自力で対応して疲弊するか」、それとも「高額な費用を払って制作会社に依頼するか」の2択で悩んでいます。
しかし、今の時代だからこそ選べる「第3の選択肢」があります。それは、高額なツール導入でも、従来型の高コストな外注でもない、「AI×プロ編集者による成果報酬型支援」という新しい選択肢です。
「AIの効率」と「プロの編集力」を組み合わせるとは?
私たちミズサキが提供する「リクルーティングPR-X」は、これまでの採用広報サービスとは異なる仕組みです。
その特徴は、「AIをあなたが使いこなす」のではなく、「AIを使いこなすプロに、成果物だけを依頼する」という点にあります。
通常の制作会社に記事作成を依頼すると、1本あたり5万円〜10万円のコストがかかります。これは、ヒアリング、構成作成、執筆、校正のすべてを人間が手作業で行っているためです。
一方、私たちは制作プロセスの約80%をAIで効率化しています。
膨大なインタビューデータの整理や構成案の作成といった「下準備」はAIに任せ、最後の「感情の反映」や「ファクトチェック」という重要パートのみを、熟練のプロ編集者が担当します。
| AIの強み | 人間の強み |
| スピードとデータ処理能力 | 文脈の理解、表現力、リスク管理 |
あなたはAIツールの操作を覚える必要も、プロンプトに悩む必要もありません。完成した高品質な記事を受け取るだけです。

なぜ「全額返金保証」ができるのか?
- 「安価なのは分かったが、品質は大丈夫なのか?」
- 「AIが書いたような、内容の薄い記事が納品されるのではないか?」
そんな不安を解消するために、私たちは「全額返金保証」をお約束しています。
もし、納品された記事の内容にご満足いただけなければ、料金はいただきません。理由はシンプルで、品質に自信があるからです。
採用広報は、結果(応募や認知)が出なければ意味がありません。「納品して終わり」という仕事はしたくないと考えています。この保証は、私たちの「成果へのコミットメント」の表れです。

「月額0円・縛りなし」で必要な時だけ依頼できる柔軟性
多くの採用支援サービスやSaaSは、「半年契約」や「月額固定費」が前提となっています。しかし、採用活動には波があります。「今月は記事を書きたいが、来月は選考で手一杯」という時期もあるでしょう。
だからこそ、私たちは「初期費用0円・月額固定費0円」に設定しました。
- 今月は採用強化月間だから、3本依頼したい
- 来月は採用が落ち着くから、依頼は0本
このように、必要な時に、必要な分だけ利用可能です。
「使っていないのに毎月費用が発生する」といった無駄なコストは一切かかりません。社内稟議を通す必要もない手軽さで、プロの広報チームを「スポット利用」できる感覚でご活用いただけます。
リクルーティングPR-Xが選ばれる5つの理由
「リスクがなく、安くて、品質も良い。そんな話があるのか?」
そう感じられた方もいるかもしれません。
私たちが選ばれるのには明確な理由があります。それは、AIの活用によって「コスト構造」を根本から変えたからです。
他社サービスや自社運用と比較しながら、リクルーティングPR-Xが選ばれる5つの理由を解説します。
|
項目 |
リクルーティングPR-X |
一般的な制作会社 |
AIツール自社運用 |
|
費用感(1本) |
〇 3万円〜 |
5万円〜10万円 |
0円〜(+人件費) |
|
手間(工数) |
〇 一任可能(取材30分のみ) |
一任可能(取材60分〜) |
大(録音・執筆・編集) |
|
記事品質 |
〇 プロ編集(AI×人間) |
プロ品質(人間100%) |
不安定(AI依存) |
|
初期費用 |
〇 0円 |
10万円〜30万円 |
ツールによる |
|
契約期間 |
〇 縛りなし(単発OK) |
6ヶ月〜1年契約 |
月額サブスク |

1. 圧倒的な低価格(月3万円〜)
「法人クオリティの記事は高い」という常識を変えました。AIが下書きを行うことで人件費を削減し、フリーランスのライターに直接依頼するのと同等、あるいはそれ以下の価格を実現しています。浮いた予算を広告費や採用媒体費に回せるため、採用全体の費用対効果が向上します。
2. オンライン取材費込み(一任可能)
「書く時間がない」だけでなく、「インタビューの準備をする時間がない」という声にも応えます。質問項目の設計から当日のインタビュー進行(オンライン30分〜60分)まで、すべて私たちが代行します。あなたは「Zoomに入室して話すだけ」。あとは待っていれば記事が完成します。
3. 採用へのコミット(戦略視点)
私たちは単なる「ライター」ではありません。記事を作る前に、「どんな人材が欲しいのか」「競合に勝つための強みは何か」をヒアリングします。ただ整った文章を書くのではなく、ターゲットの応募意欲を高めることに特化した構成をご提案します。
4. 初期費用・固定費ゼロ
「とりあえず1本試したい」という時に、高額な初期費用や契約期間の縛りは大きなハードルです。私たちは初期費用0円、月額固定費も0円。予算決裁が不要なレベルの手軽さなので、現場の判断ですぐにスタートできます。
5. 全額返金保証
これが最大の特徴です。納品物に納得いただけなければ、理由を問わず全額返金いたします。「社内の合意が得られなかった」「イメージと違った」——どんな理由でも構いません。採用広報のアウトソーシングで発生するリスクを最大限排除します。
採用広報のAI活用に関するよくある質問(FAQ)
最後に、AI活用や外部委託を検討する際、よくある疑問にお答えします。
Q. AIが書いた記事はGoogle検索(SEO)でペナルティを受けませんか?
A. AI製だからといって、一律でペナルティを受けることはありません。
Googleは「制作方法」ではなく「コンテンツの質」を評価基準にしています。ただし、AI特有の「中身が薄い文章」や「事実誤認(ハルシネーション)」が含まれていると、低品質なコンテンツとして順位が下がるリスクがあります。
だからこそ、最終工程で専門知識を持つ人間が加筆・監修(ファクトチェック)を行うプロセスが必要不可欠なのです。
Q. 社員インタビューの音声をAIに入力してもセキュリティは大丈夫ですか?
A. 無料版のAIツールには注意が必要です。
例えば、ChatGPTの無料版などは、入力されたデータがAIの学習(トレーニング)に使用される可能性があります。社外秘の情報や個人情報が含まれるインタビューデータを扱う際は、必ず「学習データに使わない設定(オプトアウト)」を行うか、セキュリティ対策が万全な法人向け有料プランを使用してください。もちろん、当社のサービスでは適切なセキュリティ環境下でデータを扱っています。
Q. 著作権の問題はどうなりますか?
A.「既存記事との類似性」に配慮する必要があります。
生成AIが作成した文章が、Web上の既存記事と酷似している場合、意図せず著作権侵害になってしまうリスクはゼロではありません。
私たちは、専用のコピペチェックツール(類似度判定)ですべての成果物を検査しています。また、独自のインタビュー体験談(一次情報)を必ず盛り込むことで、他サイトとは重複しない「オリジナルの記事」へと仕上げています。
まとめ:賢くAIとプロを使い分け、採用広報を「成果」に変えよう
ここまで、採用広報におけるAI活用の可能性から、現場での課題、そして新しい解決策までを一通り解説してきました。
疑問や不安は、かなり解消されたのではないでしょうか。
これからの時代、採用広報において「AIを使わない」という選択肢は現実的ではありません。しかし、それは「すべてを自分一人で、AIを使って内製しなければならない」という意味ではありません。
経営者や人事担当者であるあなたの最も重要な仕事は、プロンプトを考えることでも、誤字脱字をチェックすることでもありません。
目の前の候補者と向き合い、自社の魅力を伝え、「あなたと一緒に働きたい」と思ってもらうこと。これこそが、AIには代替できない、あなただけのコア業務です。
「良い人が来ない」と悩むだけの日々は、もう終わりにしましょう。
Web上に蓄積された良質な記事は、あなたが寝ている間も、面接をしている間も、未来の仲間を集め続ける「継続的な成果」になります。
私たちは、その環境づくりをリスクゼロでお手伝いします。まずは1本、お試し感覚で記事を作ってみませんか?
あなたの会社の隠れた魅力を、私たちと一緒に世の中へ発信しましょう。

生成AIの登場と性能向上によって、これまでに提供できなかった、超低価格の採用広報・採用ブランディングサービスを提供可能になりました。
- オンライン取材込みで1記事3万円!
- 納品後、満足できなければ全額返金!
- 最低契約期間なし!いつでも解約OK
まずは1記事からお試しください。満足できなければ全額返金いたします。