企業の採用活動において、「面接」は応募者の本質を見極めるための最も重要なプロセスです。
しかし、多くの面接官が「応募者の本音(本当の姿)をどう引き出すか」という共通の悩みを抱えています。
昨今、応募者側もAIを駆使した模擬問答や、企業側の質問傾向の分析など、万全の態勢で面接に臨んでいます。
「暗記してきた完璧なトーク」で好印象を与えようとする応募者も少なくありません。
では、どうすればその準備された「意識的な言葉」の裏にある、その人固有の「無意識の言葉」=「本音」に触れることができるのでしょうか。
この記事では、”言葉”のプロである株式会社往来庵代表の菊地さんが、採用担当者が使える「言葉の深読み術」を、具体的なポイントに絞って分かりやすく解説します。
|

|
【執筆者:株式会社往来庵 菊地さんのご紹介】
菊地克仁 KIKUCHI KATSUHITO
株式会社往来庵 代表取締役、潜在能力開発コンサルタント。
東京都杉並区出身。大学卒業後、 飛島建設で一級建築士として活躍。
その後、三菱信託銀行(当時)で様々な不動産事業に従事。
さらに銀行主導により設立から参画した資産運用会社で、ビル経営代行業(PM業務)に従事しながら、実践心理学を学ぶ。 2013年、定年退職を機に株式会社往来庵を設立。
3,000人以上の個人特性の分析実績あり。
筆跡心理分析トレーナー、NLP(神経言語プログラミング)マスタープラクティショナー、LAB プロファイル(影響言語)トレーナー、キャリアコンサルタントの資格取得。
筆跡心理分析専門家として「ホンマでっかTV2時間スペシャル版」に出演実績あり。
他にFM放送、出版等多数。
<ご紹介>
・往来庵よろず相談所
・メールマガジンのご登録
・LINEでご相談
|
今回は、我々が無意識に使っている”言葉”に着目します。
言葉は意識されて使われることもありますが、多くは無意識に使われています。
「意識される言葉」が理論的な話の展開や起承転結といった「構築されたもの」であるのに対し、「無意識の言葉」は、その人の思考のクセや価値観が不意に表出するものです。
例えば、「でも」「一応」「逆に」といった接続詞や、「〇〇すべき」「〇〇ねばならない」といった断定的な表現。
これらは、本人が意識している以上に、その人の「物事の捉え方(前提)」や「行動を制限する思い込み(ビリーフ)」を雄弁に物語っています。
前回の記事では、個人の特性を筆跡から分析することを試みました。
今回の記事では、実践心理学の視点(影響言語など)も交えながら、面接時に使える、応募者の「言葉」からその人の深い意識や思考特性を読み解く具体的なスキルをご紹介します。
このスキルは、面接だけでなく、日常のコミュニケーションで相手の本音を探る際にも、非常に有効に活用できるものです。
【実践テクニック】応募者の思考特性を暴く「魔法の質問」
面接の場は、応募者の「本音」を引き出す駆け引きの場でもあります。
準備された答えを崩し、その人本来の姿を見るための具体的な質問例を見ていきましょう。
.png?width=600&height=400&name=%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%A6%3F%20(2).png)
①「どうして?」という質問が明かす「思考の型」
応募者が、
「御社に採用していただければ、〇〇のような仕事をしてみたいと思います!」
と意欲的に語ったとします。
これに対して、面接官のあなたは、ただ「素晴らしいですね」と返すだけではもったいない。
ここで、こう尋ねてみてください。
「あなたは『どうして』、〇〇のような仕事がしてみたいと思ったのですか?」
この「どうして?」という日本語は、実は「Why(なぜ=理由)」と「How(どのようにして=経緯)」の両方の意味を含んでいます。
応募者は、瞬間的にどちらかの意味でこの質問を解釈し、答えようとします。
その答え方によって、その人の思考の「型」が見えてくるのです。
答えは、大きく以下の二つに分かれます。
a.「理由」や「価値基準」で答えるケース
「非常に興味があったからです」
「自分の好きな分野の仕事だからです」
「刺激的で面白そうだと思ったからです」
このように、その行動を選択する「理由」や「目的」を答える人。
彼らは、”未来志向・目的志向型(オプション型)”の傾向があります。
- 特徴:常に「可能性」や「選択肢」を探すことでモチベーションが上がります。
新しいやり方やチャレンジに価値を感じ、既存の手順やルールに縛られるよりも、裁量権を持って動くことを好みます。
- 強み:企画力、発想力、フットワークの軽さ。
新規事業開発や営業、マーケティングなど、変化への対応や新しい価値創出が求められる場で力を発揮する可能性があります。
- 弱み:確立された手順に従うことや、地道なルーティンワークは苦手な場合があります。
- 解説:このタイプは「何のためにやるのか」という目的が明確であれば、高いパフォーマンスを発揮します。
逆に、目的が曖昧なまま「とにかくこれをやれ」と指示されると、途端にモチベーションが低下する傾向にあります。
b.「経緯」や「プロセス」で答えるケース
「もともと親が同じような仕事をしていたので…」
「先輩から強く勧められたからです」
「学生時代のアルバイトで似た仕事を手伝い、自分に向いていると感じたので…」
このように、そこに至った「ストーリー」や「経緯(いきさつ)」を説明する人。
彼らは、”過去準拠・手順志向型(プロセス型)”の傾向があります。
- 特徴:「物事には正しいやり方がある」と信じ、確立された手順に従って物事を完遂させることを得意とします。
「過去の成功事例」や「正しい手順」を探すことでモチベーションが上がります。
- 強み:実行力、正確性、継続力。品質管理、経理、総務、または高度な専門技術職など、確立されたプロセスを正確に運用・改善していく場で力を発揮する可能性があります。
- 弱み:前例のないことや、ルールが未整備の状況下では、パフォーマンスが低下する場合があります。
- 解説:このタイプは「どうやってやるのか」という手順が明確であれば、安心して業務に邁進できます。
彼らにとって、過去の実績やデータは行動の羅針盤であり、それを無視して進むことに強いストレスを感じます。
思考パターンごとの質問例
これらは、どちらが優れているという話ではありません。
重要なのは、「自社が今、どの部署で、どちらの特性を持つ人材を求めているか」を面接官が理解していることです。
例えば、「ゼロから新規事業を立ち上げるチーム」に採用するなら、a.のオプション型が適している可能性が高いでしょう。 逆に、「既存システムの運用保守を完璧に行うチーム」であれば、b.のプロセス型が不可欠かもしれません。
この特性が分かったら、次の質問でさらに深掘りします。
ここで、相手の「型」に合わせた質問をぶつけるのがミソです。
<ケースa「理由・目的志向型」だった相手への質問例>
「私は、仕事を通して色々なチャレンジをしてきて、前例がないと聞くと俄然やる気が出た半面、数々の失敗も重ねてきたんだよね。
キミも今までに新しいことにチャレンジして、成功も失敗もしてきたと思う。
その成功事例と失敗事例を、それぞれ3分くらいで一つずつ教えてもらえるかな? 失敗の質は問わないよ。」
<ケースb「経緯・手順志向型」だった相手への質問例>
「私は仕事を通して常に正しい方法、間違いのないやり方を見つけてきたつもりなんだ。
そういうモノは必ずあると思っているしね。
ただ、振り返ると『正しい』と思ってやったのに失敗したり、実が他にもっと優れた方法があった、なんて経験もした。
そんな経験、あなたもしたことない?
その成功事例と失敗事例を、それぞれ3分くらいで一つずつ教えてもらえるかな? 失敗の質は問わないよ。」
ポイントは、相手の思考の型(aまたはb)に面接官自身が寄り添う(合わせる)形で自己開示し、その上で「3分」という制約をつけて具体例を求めることです。
これにより、思考や判断のスピード、機転、そして「暗記していないエピソード」を引き出すことができます。
そして、この次に聞くべき最も重要な質問がこれです。
「今話してくれた『失敗』は、その後のあなたにとって、どんな意味があったと思いますか?」
この質問で、その人の「レジリエンス(回復力・困難を乗り越える力)」と「学習能力」が明確になります。
「その失敗から〇〇を学び、次に活かしました」という姿勢(=内的統制型:原因は自分にあると捉え、改善できる)なのか、 「あの時は運が悪かった」「上司の指示が曖昧だった」と環境のせいにする(=外的統制型:原因は外にあると捉える)のか。
あるいは、「ダメだったマイナスの記憶」としてのみ捉えているのか。
この「失敗の捉え方」という基本姿勢は、入社後の成長角度に直結します。
かつて松下幸之助氏が「キミは自分の人生、運がいいと思うかね?」と聞き、「そうは思いません」と答えた人を採用しなかったという逸話があります。
これも結局は、「物事をどう捉えるか」という思考のクセ(前提)=「運も実力のうち」と考え、良い出来事を自分の力として引き寄せるマインドセットを持っているか、を見ていたのではないでしょうか。
「貢献したい」の裏にある「自己認識」を探る

次は、応募者が、「私は御社の〇〇の分野で貢献したいと思います!」と力強く宣言した場面です。
その意欲は素晴らしいですが、その「根拠」と「自己認識のズレ」を探る必要があります。
面接官:
「なるほど、嬉しいですね。では、私が今あなたに以下の3つの質問をしたら、どう感じますか?『はい、いいえ』で答えてください」
① あなたは、それが「可能だ」と思いますか?
② あなたには、その「能力」があると思いますか?
③ あなたは、それに「ふさわしい人物」だと思いますか?
この質問は、応募者の「自己認識」を揺さぶります。
この3つは、似ているようで全く異なる次元の自信を問うています。
- ① 可能 (Can):「そのタスクは達成可能か?」という、タスク自体への見立てや楽観性を見ています。
ここで躊躇する人は、その「貢献」の難易度を非常に高く見積もっているか、悲観的な傾向があるかもしれません。
- ② 能力 (Have):「自分は達成に必要なスキルを持っているか?」という、客観的な自己評価です。
最もロジカルな問いです。
- ③ ふさわしい (Be):「自分はその役割を担う存在として相応しいか?」という、自己肯定感やアイデンティティの問題です。
能力(②)は「ある」と思っていても、「自分なんかが…」とここで躊躇する人は、いわゆるインポスター症候群の傾向があるかもしれません。
もし、応募者がどれかの質問で「ん~…」と躊躇したり、すぐに「はい」と言えなかった場合、そこがチャンスです。
面接官:
「例えば、2番目の『能力』で少し躊躇したみたいだけど、どういった能力を今後磨いていけば、この質問に自信をもって『はい』って答えられると思う?」
この質問は、応募者が「自覚している弱点(ボトルネック)」を瞬時に見抜き、それに対する課題解決意欲まで確認できる、非常に有効な一手です。
「はい、〇〇というスキルがまだ不足していると自覚しています。そのために現在〇〇という勉強をしています」
といった具体的な答えが返ってくれば、自己認識能力と向上心の両方が確認できます。
ちなみに、3つの質問に間髪入れず「ハイ」「ハイ」「ハイ」と答えた相手は、以下の3つのケースが考えられます。
① 本当にそれを現実化するエネルギーを持つ大物
② ハッタリに慣れた底の浅い自信過剰な人物
③ この質問を知っている(対策済みの)人物
②の「自信過剰な人物」を見抜くには、深堀るとよいでしょう。
「素晴らしい。ではその『能力がある』と即答された根拠について、具体的なエピソードを交えて教えてください」
ここで言葉に詰まるか、中身のない一般論を語るようであれば、その自信は「ハリボテ」である可能性が高いと判断できます。
大前提としての「企業側の責任」
ここまで、応募者の本音を引き出す「技術」についてお話してきました。
しかし、いくら高度なテクニックを駆使しても、面接官(企業側)に「あるもの」が欠けていては、採用は「当たりハズレ」のギャンブルになってしまいます。
それは、「自社にとって『いい人材』とは、一体どういう人なのか?」という明確な定義です。
この定義が曖昧だと、何が起こるか。
面接官は「自分と似たタイプ」や「なんとなく感じがいい人」といった個人の主観で合否を判断してしまいます。
その結果、「営業部は体育会系ばかり」「開発部は物静かな人ばかり」といったように、組織の同質性が高まり、多様性(ダイバーシティ)が失われていきます。
また、「イエスマン」が欲しいのか、「意見を言う人材」が欲しいのかが曖昧なまま採用すると、入社後に「積極性が足りない」「生意気だ」といったミスマッチが必ず発生します。
中小企業の場合、「贅沢は言えない。来てくれるだけで大歓迎!」という現実もあるかもしれませんが、それでも最低限の基準設定は不可欠です。
そのための最も簡単な方法の一つは、社内で「評価の高い人材(ハイパフォーマー)」の思考や行動傾向を分析・言語化しておくことです。
例えば、 「当社のエース営業Aさんは、思考の型が『a. 理由・目的志向型』だ」「経理のBさんは、1-1)の『b. 経緯・手順志向型』で、ミスを発見する力が突出している」 「失敗の質問に対し、ハイパフォーマーは全員が『外的要因』ではなく『内的要因』を語った」 といった具合です。
この分析は、似たような「優秀な人材」を採用する際の強力な「基準(ペルソナ)」となります。
そして逆説的ですが、この「基準」があるからこそ、「今いる優秀層とは『違う』タイプの人材」(例えば、既存社員がb型ばかりなら、あえてa型を採用する)を意図的に見つける際にも活用できるのです。
自社の将来を見据え、「今、本当に必要な人財は誰か」を定義すること。
これこそが採用活動の第一歩であり、経営者や人事の最も重要な責任です。
採用人物像の作成については、下の記事で詳しく解説していますので是非ご確認ください。
本当に価値ある人財を見抜く「方程式」
私たちは、学生時代のテストや偏差値のように、人を点数化して評価することに慣れています。
しかし、社会人として本当に大切なものは、点数化できない部分にあることを知っています。
それは「人間性」であり、「人望」であり、その人の「ものの考え方」です。
「あの人のために成し遂げるんだ!」「あの人に恥はかかせられない!」という気持ちが原点にあるメンバーに恵まれたリーダーは、幸せ者です。
京セラ創業者の稲盛和夫氏は、人を見抜く方程式として、有名な「能力×熱意×考え方」を提唱されました。
- 能力(0~100点):地頭、スキル、専門知識など
- 熱意(0~100点):やる気、情熱、意欲
- 考え方(-100~+100点):その人の哲学、価値観、倫理観
重要なのは、これらが「足し算」ではなく「かけ算」であることです。
そして、唯一マイナスが存在するのが「考え方」です。
どんなに能力が高く(100点)、熱意にあふれていても(100点)、もし「考え方」が利己的であったり、間違った方向(例えば-50点)を向いていれば、その結果は「-500,000点」となり、組織にとって巨大なマイナスを生み出してしまいます。
能力と熱意が高いほど、その害は甚大になるのです。
具体例を挙げましょう。
Aさん:
能力90点(優秀なエンジニア)
熱意90点(残業も厭わない)
しかし、考え方が「-30点」(自分のスキルを誇示したい、他者を見下す、情報を抱え込む)
結果:90 × 90 × (-30) = -243,000点
この人がいることで、チームの士気は下がり、若手は育たず、組織全体としては大きなマイナスです。
Bさん:
能力50点(平凡なスキル)
熱意60点(真面目)
そして、考え方が「+80点」(誠実、謙虚、チームに貢献したい、常に学ぼうとする)
結果:50 × 60 × 80 = +240,000点
Bさんの「能力」はAさんに劣るかもしれません。
しかし、そのポジティブな「考え方」が周囲に好影響を与え、チーム全体の生産性を上げ、本人も成長していくため、組織にとってはAさんより遥かに価値ある「人財」となります。
面接官にとっての永遠のテーマは、この数値化できない「考え方」をどう見抜くか、に尽きます。
その「考え方」を炙り出す、究極の質問
この「考え方(-100~+100点)」を見極めるために、先ほど触れた「失敗の捉え方」の質問も有効ですが、最後に、ある企業の最終面接であった「究極の質問」をご紹介します。
面接官は、その会社の経営者でした。
「明らかに法に触れるとわかっていることを、もし上位者(上司や私)から頼まれたら、キミはやる覚悟があるか?」
これは、応募者の「倫理観」と「根源的な考え方」を試す、強烈なストレステストです。
この時、迷わず「はい、やります!」と答えた被面接者は、採用されませんでした。
非採用の理由は、「愛社精神や仕事への姿勢、基本的な考え方がズレている」というものでした。
「会社や上司の命令なら何でもやります!」という姿勢は、一昔前なら「忠誠心」と評価されたかもしれません。
しかし、今は違います。
経営者の視点に立てば、「上司の命令だから」と法を犯す人間は、「顧客や社会」に対しても同じことをし、いずれ会社に計り知れない損害をもたらすリスクがある、と判断できます。
これこそ、稲盛氏の言う「考え方」がマイナスである典型例です。
では、どう答えればよかったのでしょうか。
模範解答はありませんが、その人の「考え方」がプラスであるならば、例えばこういった趣旨の答えになるはずです。
「お受けできません。 なぜなら、それが法に触れることであれば、実行した結果、お客様や社会からの信頼を失い、最終的に会社の存続を危うくするからです。
私は、会社(あるいは社長)をお守りするためにも、その命令には従えません。
もし、その命令の背景に『〇〇を達成したい』という真の目的があるのであれば、法に触れない別の方法を全力で考え、ご提案します」
これは、単なる「イエス・ノー」ではなく、「なぜノーなのか」という理由(=考え方)と、「代替案の提示(=熱意・能力)」が示されています。
面接官は、「ノー」と言える勇気(倫理観)と、その上で組織に貢献しようとする姿勢(プラスの考え方)を見たいのです。
まとめ
採用面接とは、応募者の「本音」と、企業側が定める「基準」をマッチングさせる場です。
本記事でご紹介した「言葉の前提」を捉える技術を使い、応募者の「思考特性」や「自己認識」という本音を引き出す。
同時に、企業側は「求める人材像」という基準を明確にし、 そして何より、数値化できないが最も重要な「考え方」や「倫理観」を見極める。
これらの「技術」と、企業としての「哲学(軸)」を両立させることこそが、採用の精度を格段に上げ、会社の未来を創る「人財」に出会うための王道であると考えています。







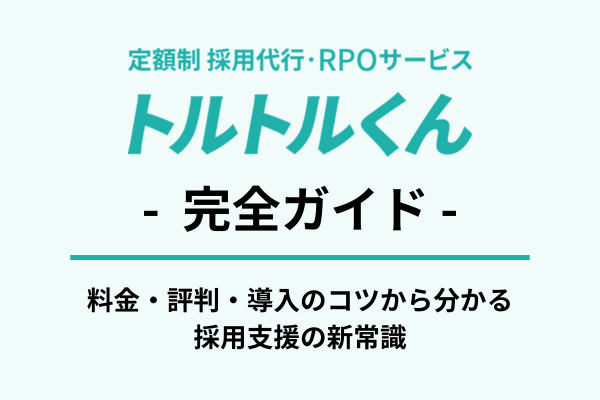

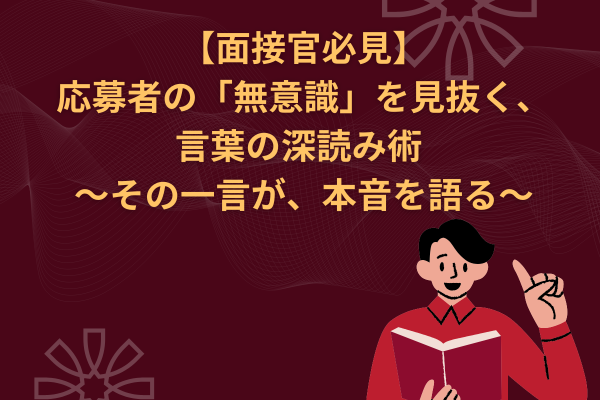

.png?width=600&height=400&name=%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%A6%3F%20(2).png)

