スタートアップやベンチャー・中小企業にとって、採用広報に投資できる予算が限られている時に使えるのが『note』です。
noteとは、文章・画像・音声・動画など様々なコンテンツを手軽に発信できるメディアプラットフォームで、個人・ビジネス問わず幅広く活用されています。
近年、多くの企業が採用オウンドメディアの運用に力を入れる中で、採用広報の有効な手段としてnoteが注目されています。
しかし、採用広報をこれから始める広報担当者・採用担当者にとっては、
- 「noteで本当に採用広報の効果があるのか?」
- 「大手企業がやっているように、オリジナルの採用サイトを制作したほうが良いのではないか?」
といった、懸念があると思います。
この記事では、noteを採用広報に活用すべき理由から、失敗しないための始め方、そして成功している他社事例から学ぶコンテンツの「型」まで、あなたの疑問を解消します。
なぜ今「note」が採用広報に選ばれるのか?
採用広報のツール・プラットフォームについて情報収集すると、ほぼ必ず選択肢として挙げられているのがnoteです。
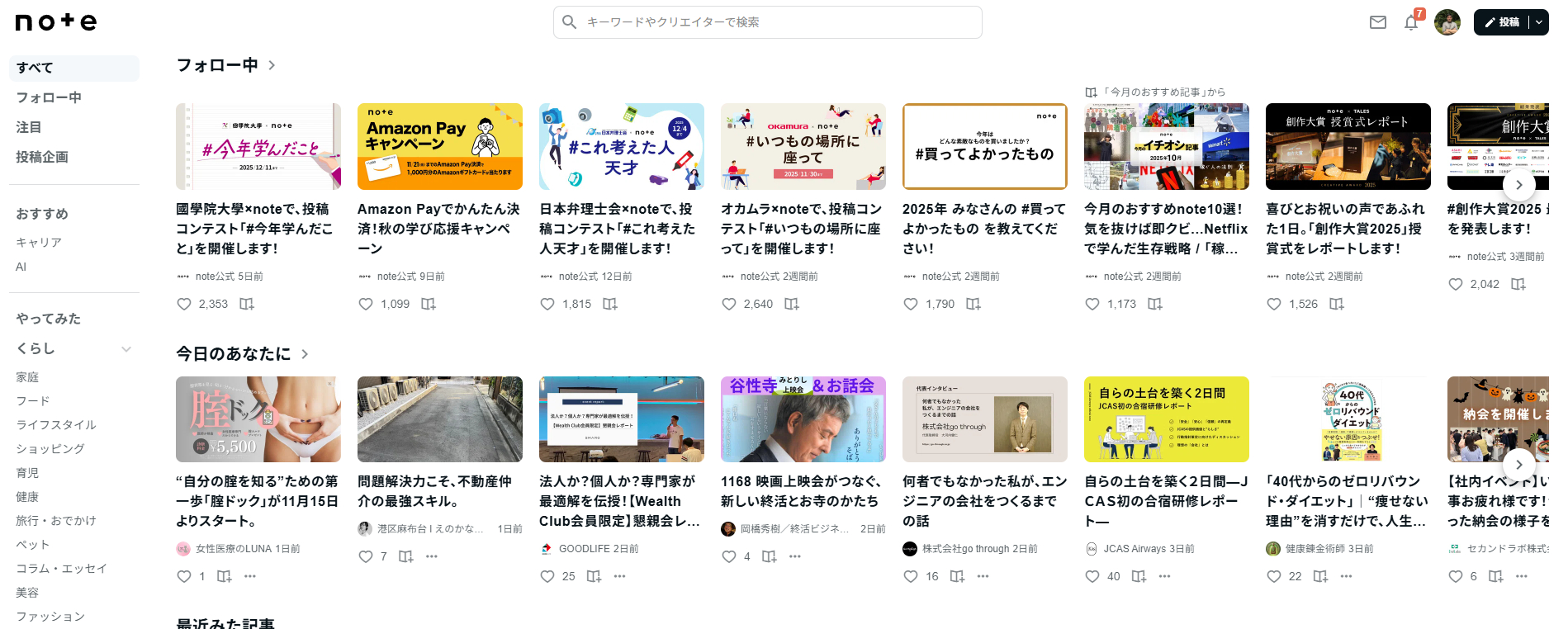
note pro公式アカウントの記事で、採用広報が上手い企業の成功事例やお手本が紹介されており、「SmartHR」・「クックパッド」といった有名企業から、知名度はそこまで高くないベンチャー企業まで、様々な企業が採用広報にnoteを利用していることが伺えます。
なぜ、noteが採用広報に選ばれるのでしょうか?
そもそも採用広報とは?その目的とブランディングの重要性
まず「採用広報」の目的を再確認しましょう。採用広報とは、単に求人情報を出すことではありません。
自社のビジョン、文化、働く人々、制度といった情報を社外に広く発信し、「この会社で働きたい」というファンを増やすための採用ブランディング活動です。

その採用広報によって、候補者へのブランディングを行うのですが、その目的は企業によって異なります。
例えば、以下のような選考プロセスに対する効果改善を目的とする企業が多いです。
- 入社後のミスマッチによる早期離職を防ぐこと
- 応募率の向上
- 選考辞退の減少
|
ミスマッチによる
『やっぱり退職』のリスク
株式会社マイナビが実施した中途採用状況調査によれば、「選考時に離職リスクの高さを懸念しつつ採用したが、やはり離職となってしまったケース」を経験した企業は39.6%に達します 。
その離職の最大の理由は「仕事内容のミスマッチ」(24.5%)であり、次いで「社風や文化とのミスマッチ」「上司との相性」が続きます。
|
給与や待遇といった「条件」だけでなく、企業の「リアルな姿」や「価値観」を事前に深く理解してもらうことで、自社に本当にマッチする人材と出会う確率を高め、これらの課題を解決に導きます。
事実、株式会社ディスコが実施した学生調査では、就職先企業を選ぶ際に「最も重視する点」を尋ねたところ、最多の回答を得たのは「職場の雰囲気が良い」(12.4%)でした。
noteが採用広報に選ばれている「4つの理由」
では、なぜその手段としてnoteが選ばれているのでしょうか。
主な理由は4つあります。
理由1:企業の「リアルな文化」や「価値観」をストーリーで伝えやすい
noteはブログ型のプラットフォームであり、文章だけでなく画像、動画、音声など幅広い形式のコンテンツを自由に発信できます。
社員インタビュー、プロジェクトの裏側、創業者の想いなど、数字やデータでは伝わらない企業の「体温」や「カルチャー」を、熱量を持った記事として届けられます。この"生の情報"こそ、候補者が入社前に最も知りたいことです。
理由2:SNSのような「拡散力」と「ファン化」の仕組みがある
noteには「スキ(いいね)」や「フォロー」機能があり、プラットフォーム内で記事が拡散されやすい構造になっています。
これにより、自社のファン(フォロワー)を増やし、継続的に関係性を築くことができます。
理由3:SEO(検索エンジン最適化)に対応している
noteというプラットフォーム自体がSEOに対応しており、Googleなどの検索結果に表示されやすい特性があります。
これにより、「今すぐ転職したい」という顕在層だけでなく、あなたの会社をまだ知らない「潜在的な候補者」に対しても、記事を通じて自社を"見つけてもらう"ことが可能になります。
理由4:導入ハードルが低く、誰でもすぐに始められる
専門的なWebサイト制作の知識は不要です。
noteは直感的な操作で記事を作成でき、無料プランでも採用広報に十分な機能を備えています。
【徹底比較】自社サイト vs Wantedly vs note (他のツールとの違い)
採用広報の手段は他にもあります。
例えば、「Wantedly」や「自社採用サイト」を使っている企業が多いです。
noteは「カルチャー発信」と「ブランディング」を行うツールとして優れていますが、他のツールにもそれぞれ特徴があります。ここでは、それぞれの特徴を比較し、どのような企業フェーズや目的に適しているかを整理していきます。
比較一覧表
|
比較項目
|
自社採用サイト
|
Wantedly
|
note
|
|
主な目的
|
ブランディング、情報集約、採用活動全般
|
採用活動(特に準顕在層)、採用広報
|
情報発信、採用広報、ブランディング
|
|
主な機能
|
自由 (記事投稿, 応募フォーム, etc.)
|
募集要項掲載, 記事投稿, スカウト, 応募管理
|
記事投稿, マガジン, SNS連携
|
|
費用
|
高 (構築・運用コスト)
|
中〜高 (有料プランが基本)
|
低 (無料〜、有料プランあり)
|
|
導入スピード
|
遅い (企画・設計・構築が必要)
|
早い (アカウント開設後すぐ)
|
最も早い (アカウント開設後すぐ)
|
|
カスタマイズ性
|
高 (デザイン・機能を自由に設計)
|
中 (フォーマットの範囲内)
|
低 (基本的なレイアウトのみ)
|
|
ターゲット層
|
顕在層〜潜在層 (SEO・導線次第)
|
準顕在層〜潜在層 (SNS的側面)
|
潜在層 (コンテンツ次第)
|
|
採用機能
|
自社で構築・連携が必要
|
充実 (スカウト, 応募管理)
|
限定的 (応募は外部連携推奨)
|
1. noteの特徴
| 手軽さとスピード感 |
アカウント作成後すぐに記事を公開でき、導入までのスピードが最も早いです。 |
| 費用 |
無料で始められるため、コストを最小限に抑えたい場合に最適です。 |
| 情報発信の場 |
企業のカルチャー、社員インタビュー、価値観などをストーリーとして発信することに長けています。 |
おすすめしたい企業:
- 採用広報に初めて取り組む企業。
- スタートアップやベンチャーなど、リソースやコストを最小限に抑えたい企業。
- まずはスピーディーに情報発信を始めたい企業。
2. Wantedlyの特徴
| 採用プラットフォーム |
募集要項の掲載だけでなく、採用広報記事の投稿、ダイレクトスカウト、応募管理まで、採用活動を一貫して行える機能が揃っています。 |
| 準顕在層へのアプローチ |
SNSのように気軽に企業と求職者が繋れる設計で、転職を積極的に考えていない「準顕在層」へのアプローチに強みがあります。 |
おすすめしたい企業:
- 一定の採用コストを投資し、求職者へのアプローチ手段を増やしたい企業。
- 転職準顕在層や潜在層にターゲットを広げたい企業。
- 採用広報と採用活動をシームレスに連携させたい企業。
3. 自社採用サイトの特徴
| 最高のカスタマイズ性 |
デザイン、機能、コンテンツ構成など、すべてを自社の思う通りに構築できます。 |
| ブランディングの拠点 |
企業の採用に関するあらゆる情報を集約し、ブランドイメージを最も強く訴求できる場所です。 |
おすすめしたい企業:
- 自社または外注でサイト構築・運用を行うリソース(予算・人材)を有する大企業・中堅企業。
- 採用ブランディングを中長期的な経営戦略として重視する企業。
どのツールを選ぶべきか?
どのツールを選択するかは、企業のフェーズ、目的、そして投入できるリソースによって異なります。
| 今の状況 |
最適なツール |
| まずは、早く、低コストで採用広報を始めたい |
note が最適です。
すぐに情報発信を開始し、企業のカルチャーを伝える場として活用できます
|
| 採用広報と並行し、準顕在層にも積極的にアプローチしたい |
Wantedly が適しています。
スカウト機能を活用しつつ、採用広報コンテンツで候補者の意欲を高めることができます。
|
| 採用ブランディングを確立し、中長期的な資産として採用のハブを構築したい |
自社採用サイトが最終的なゴールとなります。
十分なリソースを確保し、戦略的に構築・運用する必要があります。
|
【導入前に必読】note採用広報のメリットとデメリット
noteを活用することで、多くの企業が採用広報で目指す「理想」を、低コストかつスピーディーに実現できます。
しかし、noteというプラットフォーム特有の「使いにくさ」や「失敗パターン」も存在するので、導入前にメリットとデメリットを把握しておきましょう。
メリット:noteだからこそ実現できること
メリット1:無料で採用広報の「基盤」が手に入る
これが最大のメリットです。無料プランでも記事投稿、マガジン機能、SNS連携など、採用広報に必要な基本機能が揃っています。
通常、オウンドメディア(自社採用サイト)を立ち上げるにはサーバー代、ドメイン代、構築費用(数十万〜数百万円)が必要ですが、noteならそれらが一切不要です。
メリット2:Web制作やサイト運営の知識がなくても使いやすい
noteはエディタ(編集画面)が非常にシンプルで、Web制作の専門知識がなくても直感的に記事を作成できます。
メディア運用のしやすさは、採用広報を継続できるかに直結するので、note以外のプラットフォームやツールを使用することになっても、操作性や見やすさは重視したいポイントになります。
メリット3:noteプラットフォーム内での「認知拡大」が期待できる
noteには「スキ」や「フォロー」、ハッシュタグ機能があり、SNSのようにプラットフォーム内で記事が拡散されやすい仕組みがあります。
自社サイトを立ち上げた場合、最初は誰も訪問してくれませんが、noteならプラットフォームの集客力を活かし、自社をまだ知らない潜在層に記事が届く可能性があります。
メリット4:ドメインパワーが強く「SEO(検索流入)」に有利
ロから自社サイトを構築した場合、Googleなどの検索エンジンに評価されるまでには時間がかかります。
しかし、note(note.com)というドメイン自体が既に検索エンジンから高い評価を受けているため、そこで書いた記事が比較的早く検索結果の上位に表示されやすいというメリットがあります。
【要注意】note特有のデメリットと具体的な対策
一方で、note特有の「使いにくさ」や「リスク」も存在します。これらは事前に知っておけば対策可能です。
デメリット1:デザインの画一性で、他社との差別化が難しい
noteは良くも悪くもデザインフォーマットが統一されています。無料プランでは特に、他社と似たような見た目になりがちで、「自社らしさ」をデザインで表現しにくい側面があります。
対策 →「コンテンツの質」と「プロフィールの工夫」で勝負する
- デザインで差別化できない分、記事の「内容」や「切り口」で独自性を追求します。
- ヘッダー画像やプロフィール紹介文を徹底的に作り込み、一目で「何の会社か」が伝わるように工夫します。
- 本格的なブランディングが必要な場合は「note pro」(独自ドメインやロゴ設定が可能)を検討するか、自社サイトの"入り口"としてnoteを活用します。
デメリット2:直接的な応募機能が弱く、候補者の管理ができない
noteはあくまで「メディアプラットフォーム」です。Wantedlyのような応募フォームや候補者管理(CRM)機能は搭載されていません。
対策 →「導線設計」を徹底する
- 記事を読んで興味を持った候補者が迷わないよう、記事の末尾に「採用サイトはこちら」「募集職種一覧(求人ページへのリンク)」といった明確な導線(CTA)を設置します。
- 応募管理は、別途用意した応募フォーム(Googleフォームや採用管理ツール)で行いましょう。
デメリット3:無料プランでは詳細な分析が難しい
「どの記事が採用に繋がったか」を分析することは重要です。しかし、無料プランで分かるのは「PV数」や「スキ数」など簡易的なデータのみです。
対策 →「分析の目的」に応じてプランを検討する
- フェーズ1(まずは開始): 無料プランで「PV数」「スキ数」をKPIとし、どんな記事が読まれるかのノウハウを蓄積します。
- フェーズ2(本格運用): 「読了率(最後まで読まれたか)」「流入経路」など、より詳細な分析でコンテンツを改善したいフェーズになったら「note pro」への移行を検討します。
デメリット4:プラットフォームの仕様変更リスク
これはnoteに限りませんが、他社のサービスを利用する以上、将来的な規約変更、デザイン変更、サービス終了(可能性は低いですが)といったリスクに左右されます。
対策 →「資産」として記事をバックアップする
- 公開した記事(テキストデータ)は、自社の資産として必ず手元にバックアップ(Wordやテキストファイルで保存)しておきましょう。
- noteを「唯一のメディア」とせず、あくまで「情報発信チャネルの一つ」と位置づけ、リスクを分散させることも重要です。
【5分で診断】あなたの会社に最適なプランは?(無料 vs note pro)
noteには無料プランと、法人向けの「note pro」があります。自社に最適なプランを診断しましょう。
無料プランとnote pro(法人向け)の機能・料金比較表
|
機能
|
無料プラン
|
note pro
|
|
月額費用
|
0円
|
88,000円(税込)〜
|
|
記事投稿
|
無制限
|
無制限
|
|
独自ドメイン
|
✕ (note.com/...)
|
〇 (自社ドメイン)
|
|
ロゴ表示
|
✕ (noteロゴ)
|
〇 (自社ロゴ)
|
|
ヘッダーカスタマイズ
|
✕
|
〇
|
|
詳細な分析機能
|
△ (簡易的)
|
〇 (読了率, 流入経路など)
|
|
予約投稿
|
✕
|
〇
|
|
サポート
|
✕ (セルフ)
|
〇 (専任担当)
|
※料金や機能は2025年11月時点のものです。最新の情報はnote公式サイトにてご確認ください。
企業フェーズ別「おすすめプラン診断」
まずは「無料プラン」で始めるべき企業
| 特徴 |
スタートアップや中小企業、専任の広報・採用担当がいない、まずは試験的に採用広報を導入したい。 |
| 理由 |
無料プランでもnoteの基本機能(記事投稿・拡散)はすべて使えます。まずは無料で始めて「継続できるか」「どんな記事が読まれるか」のノウハウを蓄積するのが最優先です。 |
最初から「note pro」を選ぶべき企業
| 特徴 |
社員100名以上のメガベンチャー・中堅企業、本気で採用ブランディングに取り組みたい、専任担当者がおり分析(効果測定)を重視したい。 |
| 理由 |
「note pro」の真価は分析機能と独自ドメインです。「どの記事が」「誰に」「どう読まれているか」を詳細に分析し、戦略的にコンテンツを改善できます。また、独自ドメインで運用することで、noteを「自社のオウンドメディア」として本格的に見せることができ、候補者への信頼感醸成にも繋がります。 |
失敗しない!note採用広報の始め方「5つのステップ」
思いつきで始めてしまうと、前述の「更新が止まる」という失敗に陥ります。以下の5ステップで、戦略的にnote運用をスタートしましょう。
STEP1:目的(KGI)とターゲット(ペルソナ)を決める
| 目的(KGI) |
まず「何のためにやるのか」を明確にします。
▼例
・エンジニア採用の応募率を20%向上
・選考辞退率を10%改善
・入社半年後の定着率を90%にする
|
| ターゲット(ペルソナ) |
次に「誰に読んでもらいたいのか」を具体的に設定します。
・悪い例:「20代の若手」
・良い例:「SIerで3年勤務。技術力は高いが、もっと裁量権のある環境で働きたいと考えている28歳エンジニア。趣味は...」
|
STEP2:自社の「魅力・強み」を整理する
ターゲット(ペルソナ)が決まったら、その人に響く自社の「魅力」は何かを整理します。
STEP3:具体的なKPI(目標数値)を設計する
STEP1で決めたKGI(目的)を達成するために、計測可能な「中間目標(KPI)」を設定します。
STEP4:運用体制と更新ルールを決める
「誰が」「いつ」「何を」やるのかを決めます。
▼体制の例
| プロジェクトリーダー |
全体の進捗管理、KPI測定 |
| 編集長 |
企画、ネタ出し、記事の校閲 |
| 社内ライター |
社員インタビュー、記事執筆 |
▼ルールの例
| 企画会議の定期実施 |
毎週月曜10:00〜10:15 |
| 記事の公開ペース |
毎週水曜日の12:00(ランチタイム狙い) |
| 記事の長さ |
2000〜3000文字目安 |
STEP5:記事を書き、発信する
準備が整ったら、いよいよ記事を書き始めます。
【お手本事例に学ぶ】明日から書ける!note採用広報コンテンツの型
「何を書けばいいか分からない」という悩みは、多くの担当者が直面します。
その有効な解決策の一つが、ベンチマークとする企業(自社と似た業界、規模、または採用したいターゲット層が共通する企業)のnoteや採用サイトをあらかじめ決めておくことです。
彼らが「何を」「どのように」発信しているかを分析し、参考にして記事を作っていくのは、非常に実践的な手法です。
ここでは、採用広報で定番となっているコンテンツの型と、参考にすべき記事をご紹介します。
(型1)社員インタビュー :働く人の「リアル」を伝える
候補者が最も知りたいのは「どんな人が働いているか」です。
前職や出身大学などを公開することで、同じ属性を持つ候補者に興味を持ってもらうきっかけにもなります。
お手本事例1:株式会社グッドライフ
「不動産業界未経験者」という明確なターゲットに対し、不安を安心に変え、挑戦意欲を掻き立てる、非常に完成度の高い記事です。
この記事は、「不動産業界は厳しそう」「未経験でも大丈夫だろうか」と不安を抱える候補者にとって、「安心材料」と「挑戦する理由」を提供しています。
なぜ研修担当の大川さんが研修を語るのか、その「理由(=現場経験)」が明確であり、記事全体に圧倒的な説得力と信頼感を与えています。
記事はこちら:【社員インタビュー】一人ひとりの挑戦を支える|不動産の基礎から営業現場のリアルまで学べる研修を提供
お手本事例2:株式会社リブキャリア
「記念すべき公式note初投稿」とのことで、その重責を見事に果たしています。
「企業のコアバリュー」を「個人の物語」に完璧に落とし込んだ、採用広報のお手本のような記事です。
「ファーストキャリアは"スーパーの精肉部門"」。これは読者のスクロールする指を確実に止めます。「なぜそこから人材紹介に?」という強い興味を引き出す、完璧な導入です。
記事はこちら:【社員インタビュー】「人と正しく向き合うこと」を追い求め、辿り着いたリブキャリアという選択肢
(型2)会社紹介・カルチャー :ビジョンや「らしさ」を伝える
「企業理念」や「会社の雰囲気」、大切にしている価値観を伝えます。
企業理念や会社の雰囲気は、候補者が「選考に進むかどうか」、「その会社に入社するかどうか」を決める重要な判断材料です。
代表や事業責任者へのインタビュー形式、ミッション・ビジョン・バリューを紹介する形式など、様々な表現方法があります。
お手本事例3:株式会社カオナビ
カオナビの佐藤CEOによる新ビジョン「タレントインテリジェンス」発表の記事です。
インタビュー形式で、カオナビという企業の「第二創業」を告げる内容になっています。
注目するべきは、ただ「働きやすさ」や「研修の手厚さ」をアピールする記事とは違って、働きやすさをベースにしたうえで大事なのは「働きがい」と断言している点です。
記事はこちら:「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーを変わらず目指す。カオナビの新ビジョン「タレントインテリジェンス」に込めた想い
お手本事例4:株式会社令和トラベル
「カルチャー」という非常に抽象的な概念を、「わくわくランチ」という具体的な施策紹介に落とし込んだ記事です。
「仲が良い」「風通しが良い」といった採用広報で使い古された言葉を一切使わずに、「この会社は、本気でカルチャー醸成に投資している」という会社の姿勢を表現しています。
「出社するきっかけ」という現実的な課題から始まり、それが「学び」や「相互理解」の場へと進化していくプロセスが描かれており、候補者は「自分もこの輪の中に入ったら楽しそうだ」と、入社後のポジティブな日常を具体的にイメージできます。
記事はこちら:小さな”きっかけ”から、カルチャーが育つ🌱令和トラベルの『わくわくランチ』とは?
(型3)社内イベント・オフィスツアー :職場の「雰囲気」を伝える
写真や動画を多用し、視覚的に「働く環境」を伝えます。
オフィスツアーは、ただのオフィス紹介でももちろん問題ないのですが、候補者が入社してから実際に働く環境を前もって見せることで、不安を解消することを心がけましょう。
また社内イベントは、会社の価値観や雰囲気を伝える絶好のチャンスです。採用広報を始める際は、イベントの画像や動画などを撮影しておき、コンテンツ化していくことをおすすめします。
お手本事例5:株式会社ヤプリ
社内ピッチイベント『Yappli Ship』のレポート記事です。
ただのイベント紹介にとどまらず、ヤプリが大切にする「ゼロトゥワン」という価値観が伝わってきます。
「自分のアイデアを形にしたい」「挑戦を応援してくれる環境で働きたい」と考える候補者にとって、非常に魅力的な記事です。
記事はこちら:やってみたい!が会社を動かす日。社内ピッチイベント「Yappli Ship」第2回レポート
お手本事例6:SOMPOシステムズ株式会社
新入社員の方による立川オフィスの紹介記事です。
この記事では、新入社員が入社後いちばん長く過ごす場所(研修室)にフォーカスしています。
一般的なオフィスツアー(執務室や豪華な役員室)を見せられても、新卒候補者は「自分ごと」として捉えられません。
しかし、この記事は「自分たちが新入社員としてこんな場所で過ごしたんですよ」というメッセージを、先輩となる新入社員自らが発信しています。
記事はこちら:新入社員が立川オフィスを紹介!
(型4)人事制度・選考プロセス :入社後の「安心感」を伝える
候補者の「入社したらどうなる?」という具体的な不安を解消します。
また、企業が思っているよりも候補者が注目しているのが、選考プロセスです。
採用広報立ち上げた際は、入社までのプロセスと入社後にどうなるかということがわかる記事を、早いうちに掲載しておきましょう。
お手本事例7: サイボウズ株式会社
「給与評価」の舞台裏の記事です。
「給与」という最もセンシティブな情報を「誠実さ」と「透明性」をもって開示することで、候補者との間に「信頼」を構築する、採用ブランディング記事です。
多くの候補者が「結局、いくらもらえるの?」と疑問に思う中、この数字と時系列グラフを冒頭で提示することで、一気に記事への「本気度」と「信頼度」を高めています。
記事はこちら:最新の平均年収総額・昇給率も公開!「サイボウズの給与評価」の舞台裏
お手本事例8:ARISE analytics
ARISE analyticsの「2027年卒向け選考フロー」の記事です。
選考プロセスの案内と同時に、「データサイエンティスト」という職種名が持つ「理系トップ層でないと無理」「プログラミングができないと門前払い」という心理的障壁を取り払っています。
記事はこちら:【2027年卒向け】 選考フローについて
(型5)入社エントリー :新入社員の「決め手」を伝える
新入社員が「なぜこの会社を選んだか」を自分の言葉で語る、強力なコンテンツです。
noteの「#入社エントリー」というハッシュタグには、多くの企業の新入社員によるリアルな声が集まっています。大手企業からスタートアップへの転職理由、未経験からの挑戦など、候補者の共感を呼ぶ記事が多く見られます。
お手本事例9:株式会社エムニ
大企業から転職した金澤様のインタビュー記事です。
この記事は、「エムニという会社を知ってもらう」のではなく、「大企業にいる同じ境遇の人が感じている悩みを、ウチならこう解決できますよ」と、具体的な解決策を提示しています。
記事はこちら:AI応用の博士号研究者が大企業からスタートアップへ舵を切る理由:社会実装の最前線で「地に足ついたAI」を届けたい
お手本事例10:セカンドラボ株式会社
最後は、セカンドラボの「入社の決め手」を紹介する新卒向けの記事です。
代わり、学生が抱くであろう不安に対し、「この会社は、あなたという"人"に本当に関心がある」というメッセージを、記事の導入から結びまで一貫して伝えることで、圧倒的な「安心感」と「信頼」を構築しています。
記事はこちら:セカンドラボ入社の決め手はなに?先輩たちのリアルな声を紹介します!
note採用広報の効果を最大化する「3つの運用テクニック」
記事を書きっぱなしにせず、より多くの候補者に届けるためのテクニックを紹介します。
テクニック1:既存のSNS(X, Facebook)と連携し、認知を広げる
noteを公開したら、必ず自社の公式SNS(X(旧Twitter)やFacebook)でシェアしましょう。
| X(旧Twitter) |
拡散力が高い。記事の「見どころ」を引用したり、関連する社員にメンションしたりして、拡散を狙います。 |
| Facebook |
実名制で信頼性が高い。特にリファラル採用(社員の紹介)に繋げたい場合、社員に「シェアしてね」と呼びかけるのが有効です。 |
テクニック2:「マガジン」機能を活用し、情報を整理する
記事が溜まってきたら、「マガジン」機能(フォルダ分けのようなもの)を使いましょう。

- 例:「社員インタビュー」「会社カルチャー」「人事制度」
- 情報を整理することで、noteを訪れた候補者が「知りたい情報」にすぐにアクセスできるようになり、オウンドメディアとしての利便性が高まります。
テクニック3:定期的に「効果測定」を行い、コンテンツを改善する
STEP3で設定したKPIを、最低でも月1回は振り返りましょう。
noteで採用広報を立ち上げた当初は、以下の指標をKPIにしましょう。
- PV数:どの記事が読まれているか?
- スキの数:どの記事が心を動かしたか?
- 読了率:どの記事が最後まで読まれたか?※Proプランのみ
読まれている記事の傾向を分析し、「次はこういう切り口で書いてみよう」と改善(PDCA)を回すことが、note運用成功の鍵です。
noteを使った採用広報についてよくある質問(FAQ)
まとめ
note採用広報は、単なる求人情報の掲載ではありません。
それは、「自社のファンを作り、応募の質と量を高め、ミスマッチを減らす」ための、強力なブランディング活動です。
高額な採用サイトや求人媒体への投資が難しいスタートアップや中小企業にとって、noteは「低コスト」で「リアルな魅力」を「ストーリー」として届けられる、最強のツールとなり得ます。
この記事で紹介した「5つのステップ」や「コンテンツ事例」を参考に、まずは「なぜ、採用広報を行うのか?」という目的をチームで話し合うところから始めてみてください。
あなたの会社にしかない「熱」や「想い」をnoteに乗せて発信することが、未来の優秀な仲間と出会うための、一番の近道となるはずです。
弊社、ミズサキが運営する採用広報代行サービス「リクルーティングPR-X」は、採用のプロによる採用広報を、1記事3万円というフリーランス並みの低価格で提供しています。
採用広報の立ち上げから、今のオウンドメディアのテコ入れ、記事制作ペースの加速化など、様々な支援が可能です。
「これからの採用難のために、今から準備しておきたい」とお考えの方は、ぜひミズサキまでご相談ください。







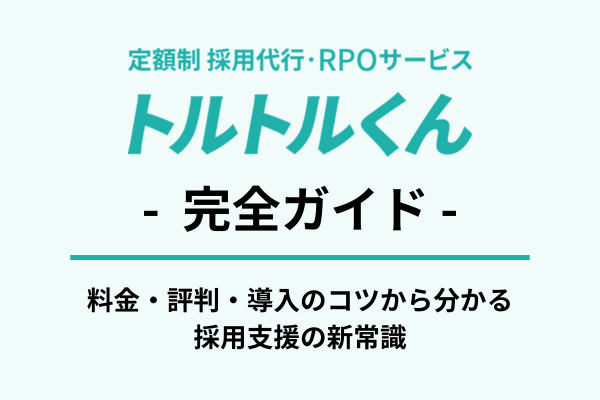

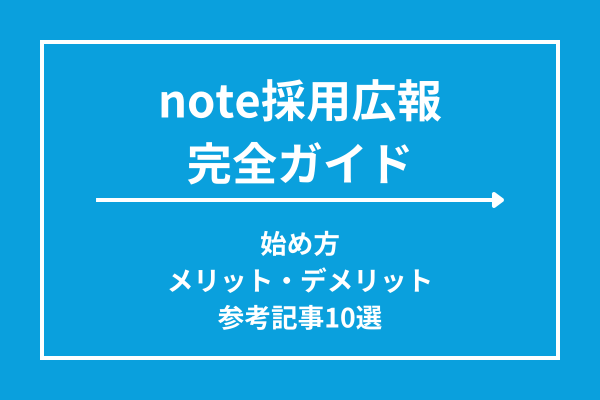

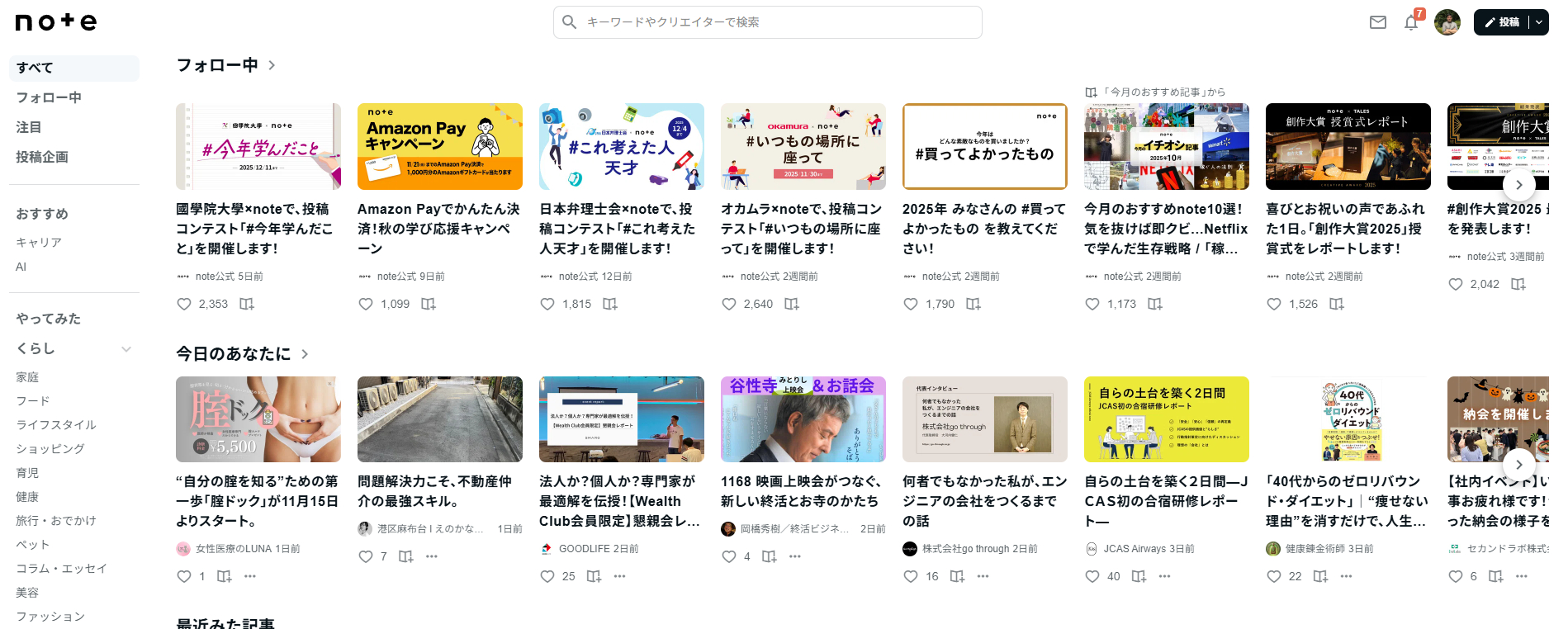



-1.png?width=500&height=500&name=%E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%20(5)-1.png)