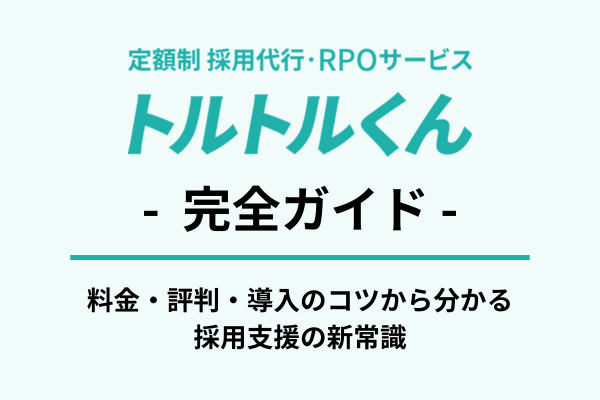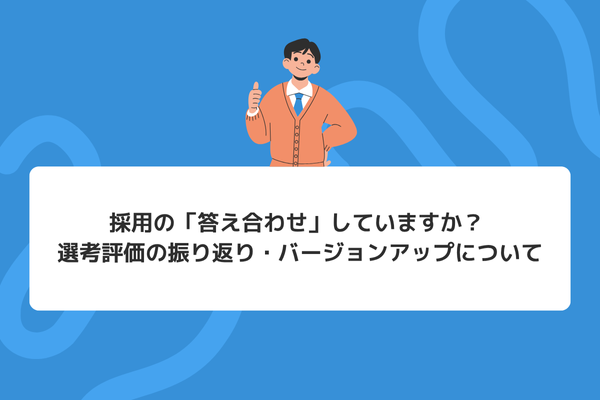「面接官によって評価がバラバラ。『Aさんは良いって言ったけど、Bさんは微妙だ』となり、結局社長の鶴の一声で決めてしまっている…」
「鳴り物入りで採用した期待のエースが、入社3ヶ月で『社風が合わない』と退職。また一からやり直しか…」
「日々の業務に追われ、採用が良い結果だったのか、きちんと振り返る時間がない。気づけば同じような失敗を繰り返している気がする」
「採用は『縁』や『運』だと思っていて、正直、改善のしようがないと感じている」...
もし一つでも心当たりがあれば、この記事は貴社の未来を変えるきっかけになるかもしれません。
採用活動は、内定を出して終わりではありません。
むしろ、そこからが本当のスタートです。
今回の記事では、採用の成否を分ける「選考評価の振り返り」と、それを未来に活かす「バージョンアップ」の方法について、明日から実践できるレベルまで掘り下げて、詳しく解説していきます。
「採って終わり」が招く悲劇。なぜ、採用の振り返りが重要なのか?
「人手不足だから、とにかく採用できればOK」
そう考えてしまう気持ちも分かります。
しかし、その場しのぎの採用は、後々、より大きなコストとなって会社に跳ね返ってきます。
採用の振り返りを怠ることが、いかに危険なことか、まずはご理解ください。
採用活動とは、以下のような一連のサイクルで成り立っています。
|
【採用成功サイクル】
① 採用計画・人物像設定 → ② 募集・母集団形成 → ③ 選考・評価 → ④ 内定・入社 → ⑤ 定着・活躍 → (①へ戻る:ここでの学びが次を良くする)
|
採用活動は「点」ではなく「サイクル」なのです。
多くの企業が①〜④で力尽きてしまい、最も重要な⑤から①へのフィードバック、つまり「振り返り」のプロセスが欠落しています。
このサイクルが途切れると、ミスマッチによる負の連鎖が始まります。
ミスマッチによる母集団形成の不足、選考辞退の増加、早期離職が続くと、採用コスト(求人広告費、紹介手数料、人件費)が無駄になるだけでなく、現場の士気低下、引き継ぎ業務の負担増、さらには「あの会社は人がすぐ辞める」というネガティブな評判に繋がり、次の採用がさらに難しくなるという悪循環に陥るのです。
ノウハウが蓄積されない「場当たり採用」には再現性がありません。
何が成功要因で、何が失敗要因だったのかを分析しないため、採用担当者や面接官のスキルが向上しません。
担当者が変わるたびにゼロからのスタートとなり、会社としての採用力がいつまでも強化されないのです。
さらに、振り返りをせず、場当たり的な採用を続けると、自社が大切にしている価値観や文化に合わない人材が増えていく可能性があります。
これは、組織の一体感を損ない、長期的には企業の競争力低下を招く静かなリスクです。
組織文化の希薄化に繋がってしまうのです。
適切な振り返りは、こうした悲劇を未然に防ぎ、貴社の採用力を着実に高めるための、唯一の「羅針盤」なのです。
【実践編】明日からできる!効果的な振り返りの3ステップ
「振り返りの重要性は分かった。でも、何から始めれば…?」
ご安心ください。取り掛かりに際しては大掛かりな分析ツールや専門知識は必要ありません。
まずは、下で紹介する3つのステップを愚直に実行することから始めてみましょう。
Step1:情報の「見える化」~“なんとなく”を卒業する評価シート~
振り返りの大前提は、客観的に検証できる「記録」を残すことです。
面接官の頭の中にしかない「なんとなく良いと思った」「ビビッときた」という感覚は、後から検証のしようがありません。
そのために不可欠なのが「選考評価シート」です。
ExcelやGoogleスプレッドシートの簡単なもので構いません。
重要なのは、その「中身」です。
ここで評価シートについて、少し紹介します。
詳細については下の記事で解説していますのでそちらも合わせてご確認ください。
それではさっそく、選考評価シートについて見てみましょう。
選考評価シートの全体像
選考評価シートとは、下のものです。
構成要素は下記の通り。
自社に合わせて項目や内容をカスタマイズして使用してください。
|
【選考評価シートの構成要素】
・実施日、担当者名、応募者名
・評価項目(MUST、BETTER、OUT)
・特記事項、評価点、懸念点、選考状況、引継ぎ事項
・応募者からの質問&回答
・応募者へのマスト質問&回答(必ずしておきたい質問をあらかじめ記入することで聞き逃しを防ぎます。)
|
選考評価シートの作り方
選考評価シートはどうやって作れば良いのか?
作成方法は以下の通りです。
1.採用人物像を設定する
この選考評価シート作成に際しては求める人物像をあらかじめ設定し、それを基に項目と質問を用意すると整理しやすいです。
採用人物像を設定するには、下の内容を洗い出すと言葉にしやすいです。
|
【採用人物像設定時に洗い出すこと】
・期待する役割(採用した人材にやってもらう仕事)
・期待する成果(採用した人材に創り出してもらいたい成果)
・成果に対する壁(その成果を出すために困難なことや難しいこと)
・活躍する人のイメージ(成果を出せる人材の特徴とは)
・ターゲット層のイメージ(どこにいて、どんなことを考え、何をしている人か)
|
さらに詳しい求める人物像の作成については下の記事で解説しています。
2.評価項目の設定
求める人物像を明確化したら、それに沿って評価項目を設定します。
評価項目は大きく「MUST」「BETTER」「OUT」の3つに分けられます。
MUST(必須) 項目は企業が求める人物像を具現化する上で非常に重要な要素です。
従来の採用では、「経歴」 や 「スキル」 といった表面的な肩書きに注目しがちでした。
しかし、このような評価基準では、入社後のミスマッチが起こりやすく、期待した活躍に繋がらないケースも少なくありません。
そこで、注目されているのが 「人間力」 という概念です。
スキルや経験は入社後の教育や実践を通して育成できますが、人間力は長年の生活や経験を通して培われたものであり、容易には変えられません。
なぜ「人間力」が重要なのか?
人間力は、「社会を構成し運営するとともに、自立した一人の人間として力強く生きていくための総合的な力」 を意味します。
企業にとって、人間力のある人材は以下のような点で期待できます。
|
「人間力」のある人材は...?
高い成長力: 新しい知識やスキルを積極的に吸収し、自己成長を続けられる。
問題解決能力: 困難な状況にも冷静に対応し、解決策を見出すことができる。
コミュニケーション能力: 周囲と円滑なコミュニケーションを図り、協調性を生み出す。
責任感: 自分の仕事に責任を持ち、最後までやり遂げる。
倫理観: 社会規範や倫理観を遵守し、誠実な行動をとる。
|
では、具体的にどのような要素が人間力を構成するのでしょうか?
以下に、評価項目例を挙げます。
|
「人間力」の構成要素とは...?
一例↓
① 思考力
論理的思考力:物事を論理的に捉え、筋道を立てて考える力
批判的思考力:既存の考え方や情報に疑問を持ち、多角的に検証する力
創造力:新しい発想やアイデアを生み出す力
問題解決能力:課題を分析し、解決策を見出す力
②対人関係力
コミュニケーション能力:相手の話を理解し、自分の考えを的確に伝える力
傾聴力:相手の話に耳を傾け、共感する力
協調性:周囲と協力し、チームワークを重視する力
リーダーシップ:チームをまとめ、目標達成に向けて牽引する力
共感力:相手の気持ちに寄り添い、理解する力
③自己管理力
自律性:指示されなくても、自ら考え行動する力
責任感:自分の仕事に責任を持ち、最後までやり遂げる力
計画性:目標を立て、計画的に行動する力
ストレス耐性:困難な状況にも冷静に対応する力
向上心:常に自己成長を目指し、努力する力
④価値観・倫理観
誠実さ:嘘やごまかしをせず、正直に行動する
倫理観:社会規範や倫理観を遵守する
責任感:自分の行動の結果に責任を持つ
貢献意欲:社会や組織に貢献したいという気持ち
多様性理解:異なる価値観や文化を尊重する
|
採用面接における評価項目は、MUST(必須)要素に加え、BETTER(あれば良いね!)要素を設定することで、より自社にマッチした人材を見つけることができます。
BETTER要素とは、社内で特に活躍している社員が共通して持っている要素や、スキル・経験 のことです。
BETTER要素を設定するメリットは下の通り。
・良い採用の再現性:活躍人材の採用基準を明確化することで、面接官ごとの評価のばらつきを減らし、再現性のある採用が可能になります。
・ミスマッチの軽減:入社後の活躍を予測できるため、採用ミスマッチを軽減することができます。
・採用効率の向上:評価基準が明確になることで、面接時間の短縮や効率的な選考に繋がります。
|
BETTER要素設定のポイント!
活躍している社員の分析:実際に活躍している社員の共通点(スキル、経験、性格特性など)を分析します。
評価項目の具体化:分析結果に基づき、具体的な評価項目を設定します。
面接官との共有:評価項目を面接官間で共有し、認識を統一します。
|
BETTER要素の具体例には、以下のものがあります↓
・特定のスキル:〇〇に関する知識や経験
・経験:〇〇業界での経験、〇〇のプロジェクト経験
・性格特性:積極性、チャレンジ精神、リーダーシップ
・実績:〇〇で〇〇の成果を上げた経験
OUT(採用見送り)要素 を設定することは、自社に合わない応募者を早期に見抜き、採用ミスマッチを防ぐために重要です。
OUT要素とは、「これがあれば、採用を見送る」 という基準のことです。
OUT要素を設けることで、採用コストの削減を図ることができます。
採用活動には、募集広告費、面接官の人件費、採用後の研修費用など、多大なコストがかかります。
ミスマッチを防ぐことで、これらのコストを削減できます。
また、求職者への配慮にもなります。
求職者にとっても、入社後にミスマッチを感じて早期に退職することは、時間と労力の無駄になってしまいますので、未然に防ぐことができます。
さらに、企業成長を阻害する要因をなくすことにも繋がると言えます。
企業理念や社風に合わない人材を採用してしまうと、組織全体の士気や生産性に悪影響を及ぼす可能性がありますので、OUTの要素で判断をすることができれば企業側のマイナスを抑えられます。
OUT要素は以下の方法で設定すると良いでしょう。
|
OUT要素の設定方法は...?
・過去の退職者の分析:早期退職者や、社風に馴染めなかった社員の特徴を分析します。
・行動特性の分析:遅刻癖、責任感の欠如、協調性のなさなど、問題行動を起こしやすい人の特徴を分析します。
・価値観の分析:企業理念やビジョンと相容れない価値観を持つ人の特徴を分析します。
|
OUT要素の具体例には以下のものが挙げられます。
・協調性がない:チームワークを重視する職場で、協調性がない人は、周囲との摩擦を生み、組織全体の士気を低下させる可能性があります。
責任感がない:自分の仕事に責任を持たず、ミスを繰り返す人は、周囲の負担を増やし、業務効率を低下させる可能性があります。
遅刻が多い:遅刻が多い人は、時間に対する意識が低く、周囲に迷惑をかける可能性があります。
嘘をつく:誠実さに欠ける人は、社内外の信頼関係を損なう可能性があります。
この採用人物像、評価を結果に合わせて改善し、面接時の質問修正に活かしていきましょう。
ポイントはコメントの質を高めること。
評価の根拠となるコメント欄こそ、振り返りの質を左右します。
NGなコメント:「コミュニケーション能力が高い」「真面目そう」「やる気を感じた」
→ これでは個人の感想であり、客観的な評価ではありません。
OKなコメント(STARメソッドを意識):
「『前職で売上目標が未達だった際(Situation/Task)、まず顧客データを分析し、失注原因を特定(Action)。
その上で、提案資料の改善と、週1回の営業チームでの対策会議を自ら企画・実行し、3ヶ月後には目標を120%達成した(Result)』という具体的なエピソードから、高い課題解決能力と主体性が確認できた」
→ このように「状況・課題」「行動」「結果」をセットで記録することで、誰が読んでも納得できる評価になります。
Step2:関係者での「すり合わせ」~現場を巻き込んだ本音の会議~
情報が見える化できたら、次に関係者で共有し、議論します。
ここで犯しがちな間違いが、採用担当者と役員だけで完結させてしまうことです。
成功の鍵は、配属予定先の現場責任者や、年の近い若手社員など、多様な立場の人を巻き込むことにあります。
効果的な振り返り会議の進め方
事前準備:評価シートや議論したいポイントを事前に共有し、参加者には目を通しておいてもらう。
ファシリテーション:議論の活性化(参加者全員が積極的に発言しやすい環境を作り、多様な意見を引き出す)、意見の整理(出された意見をまとめ、論点を明確にし、議論を構造化する)、合意形成(議論の結果をまとめ、参加者全員が納得できる結論を導き出す)、問題解決(集団の力を活用して、問題解決を促進する)を意識します。
結果の共有:まずは、採用に至った/至らなかった候補者の評価シートを全員で確認し、事実を共有します。
評価の深掘り:「なぜAさんの評価は、面接官によってSとCで大きく割れたのでしょうか?」「どの発言をどう解釈しましたか?」と、評価が分かれたポイントを深掘りします。ここでは、誰もが安心して発言できる心理的安全性を担保することが重要です。
入社後パフォーマンスとの接続:現場責任者から「最近入社したBさんは、面接では『協調性が高い』という評価でしたが、実際にはチームと少し孤立しがちです。選考時に見抜けなかった点はありますか?」といった、リアルな声を拾い上げます。
改善アクションの決定:「では次回から、協調性を測るために『チームでの失敗経験と、そこから学んだこと』を質問に追加してみましょう」といった、具体的な次のアクションを決め、担当者と期限を明確にします。
この振り返り会議は、犯人探しの場ではありません。
「より良い採用」という共通のゴールに向かって、建設的な意見を交わす文化を育むことが目的です。
Step3:「入社後」との「答え合わせ」~自社の“勝利の方程式”を見つける~
次に行うのが、選考時の評価と入社後のパフォーマンスを比較する「答え合わせ」です。
これを行うことで、貴社独自の「活躍人材の共通点=勝利の方程式」が見えてきます。
「答え合わせ」の方法例を挙げると以下のもの。
・ハイパフォーマー分析
入社後に高い成果を出し、周囲からも評価されている社員の面接評価シートを徹底的に分析します。
「彼/彼女は、面接でどんな経験を語っていたか?」「どの評価項目が特に高かったか?」「面接官はどんなコメントを残していたか?」
→ ここに、貴社で活躍するために本当に必要なスキルやスタンスのヒントが隠されています。
・早期離職者・ローパフォーマー分析
目を背けたくなるかもしれませんが、こちらも同様に重要です。
「なぜミスマッチが起きたのか?」「選考時に見抜くべきだった懸念点(サイン)はなかったか?」「評価シートのどの項目が、実態と乖離していたか?」
→ 失敗から学ぶことで、同じ過ちを防ぐためのチェック機能が生まれます。
この地道な答え合わせこそが、感覚的な採用から脱却し、データに基づいた「科学的な採用」へと進化させるためのエンジンとなるのです。
振り返りから始める!採用選考の「バージョンアップ」術
振り返りで得た「宝の地図」を手に、いよいよ採用の仕組みをバージョンアップしていきましょう。
改善すべきは、主に3つのポイントです。
改善ポイント1:「採用したい人物像」の解像度を上げる
「コミュニケーション能力が高い、意欲的な人」といった曖昧な人物像では、評価にブレが生じます。
振り返りで得た「活躍人材の共通点」を基に、採用ペルソナ(具体的な人物像)の解像度を極限まで高めましょう。
Before:明るく元気で、やる気のある若手営業
After(解像度を上げた人物像):⇩
経験:無形商材の法人営業経験2年以上。新規開拓で、自らリストアップからアポ獲得、クロージングまで一貫して行った経験がある。
行動特性:顧客の潜在ニーズを引き出す「傾聴力」に長けている。失敗を恐れず、まず行動してみてから改善する「トライ&エラー」を厭わない。
価値観:個人の成果だけでなく、チームの目標達成に喜びを感じる。新しい知識やスキルを学ぶことに貪欲である
私たちミズサキ株式会社がご支援する際も、まずはお客様と一緒にこの「人物像の解像度を上げること」に最も時間をかけます。
ここが全ての土台であり、この精度が採用の成否の8割を決めると言っても過言ではありません。
改善ポイント2:「評価基準(評価シート)」を戦略的にアップデートする
明確になった人物像に合わせて、面接評価シートと質問内容をアップデートします。
これは、貴社だけの「採用のものさし」を研ぎ澄ます作業です。
構造化面接の導入:面接官の個人的な興味で質問が脱線するのを防ぎ、全ての候補者に一部分だけ同じ質問をすることで、公平に比較評価できるようにする手法です。「コンピテンシー(行動特性)」を測るための質問をあらかじめ複数用意しておきましょう。
質問の質を高める:
・行動質問(過去を問う)「これまでの仕事で、最も困難だった課題は何ですか?それをどう乗り越えましたか?」
→ 過去の行動から、再現性のある能力を測る。
・状況質問(未来を問う) 「もし、お客様から理不尽なクレームを受けたら、まずどう対応しますか?」
→ 思考プロセスや対応力を測る。
|
【面接時のポイント】
意図や意味が乗っていない質問をただしたり、闇雲に深堀るということはないようにしましょう。
面接では、応募者の語る成果や結果ではなく、”プロセス”を見るようにします。
結果や成果が、自社の環境、サービスでも再現性のあるものかどうかを確認するためです。
応募者のこれまでの経験や仕事には”PDCA”のサイクルがあるので、↓の要素を軸に内容を把握していきます。
Plan:「計画、きっかけ」
Do:「行動」
Check:「振り返り、結果」
Action:「改善、学び」
たとえばCheckの情報が面接時に出てきたら、その結果を出すためにとった行動とそのきっかけ、また結果から得られた学びがどのようなものだったかも確認します。
この深堀りの際に使えるのが、5W1Hを聞くテクニック。
Why:「なぜ、目的」→行動の源泉が分かる。自走型/指示遂行型。
Who:「誰に対して、どんな人と」→自社のお客さん、社員に置き換えると再現性の有無が分かる。
What:「何を」→アイデア、思考のレベルを確かめられる。
When:「いつ、どれくらいの期間で」→推進力、計画性が分かる。
How:「どのように」→実行力、まわりを巻き込む力、調整力が分かる
例えば、「サークルで新歓担当となり、新入生の入部者数を前年比120%にした」というエピソードが出たら、5W1Hで深堀り。
応募者が新歓担当となった背景、どのような方法で成果を出したか、方法を思いついたきっかけ(自分で決めた?先輩から言われたことだった?)を知ることで、人材の特性、傾向の解像度を高められます。
|
アップデートした評価シートと質問集は、採用活動における「共通の土台」のようなものです。
全員がこれに則って選考を進めることで、評価のブレを最小限に抑えられ、改善の方向性を見つけ出しやすくなります。
改善ポイント3:「面接官」の目線を揃え、バイアスを排除する
どんなに素晴らしい評価シートがあっても、使う人(面接官)の目線がバラバラでは意味がありません。
新しい評価基準が完成したら、必ず「面接官トレーニング」を実施し、目線を揃えることが不可欠です。
トレーニングで共有すべきこと
評価基準の読み合わせ: なぜこの項目を評価するのか、背景や意図まで共有する。
評価エラー(無意識の偏見)の共有:
・ハロー効果 1つの良い点(例:高学歴)に引きずられ、他も全て良く見えてしまう。
・類似性バイアス 自分と似たタイプ(例:出身地、趣味が同じ)に親近感を覚え、甘く評価してしまう。
・第一印象効果 最初の数分の印象で、評価全体を決めつけてしまう。
→ こうしたバイアスの存在を「知る」だけで、客観的に評価しようという意識が働きます。
・コンプライアンス研修 本籍地、思想信条、家族構成など、聞いてはいけないNG質問を再確認し、企業のリーガルリスクを防ぎます。
面接官は「候補者を評価する」だけでなく、「会社を代表する広報担当」でもあります。
トレーニングを通じて、面接官全員が会社の顔としての自覚を持つことが、候補者の入社意欲を高めることにも繋がるのです。
まとめ:採用は、育てていくもの。
採用選考は、一度作ったら終わり、という完成形のないプロセスです。
市場は変わり、会社も成長し、求める人物像も変化していきます。
大切なのは、現状に満足せず、「振り返り → 改善」のサイクル(PDCA)を回し続けること。
つまり、採用活動そのものを、会社全体で「育てていく」という意識を持つことです。
感覚や経験則だけに頼るのではなく、事実(データ)に基づいて議論し、改善を重ねる。
採用は、十分に「科学」できる領域なのです。
この記事を読んで、「やることがたくさんある…」と圧倒されてしまったかもしれません。
しかし、どうかご安心ください。全てを一度に完璧にやる必要はありません。
まずは、
「次回の面接から、評価シートに具体的なコメントを一つ多く残してみる」
「次の採用が終わったら、30分だけ現場責任者を交えて話す時間を作る」
「ハイパフォーマーの社員に、面接で何を話したか聞いてみる」
そんな「最初の小さな一歩」からで大丈夫です。
その一歩の積み重ねが、数ヶ月後、一年後の採用結果を劇的に変え、貴社の未来を創る素晴らしい出会いを引き寄せるはずです。
もし、
「自社だけでは何から手をつければいいか分からない」
「客観的な視点で、うちの採用の課題を診断してほしい」
と感じたら、いつでも私たちミズサキ株式会社にご相談ください。
貴社の採用活動が、未来を創る力強いエンジンとなるよう、全力でサポートさせていただきます。