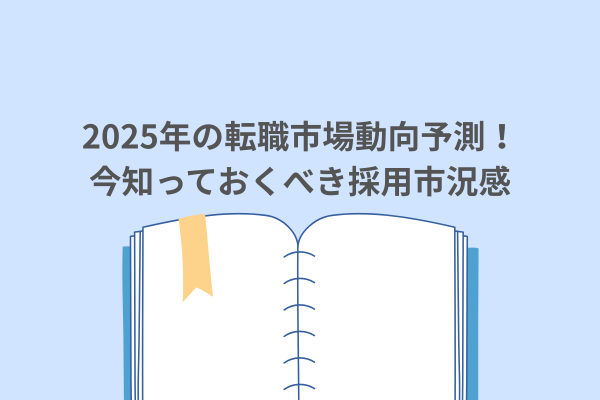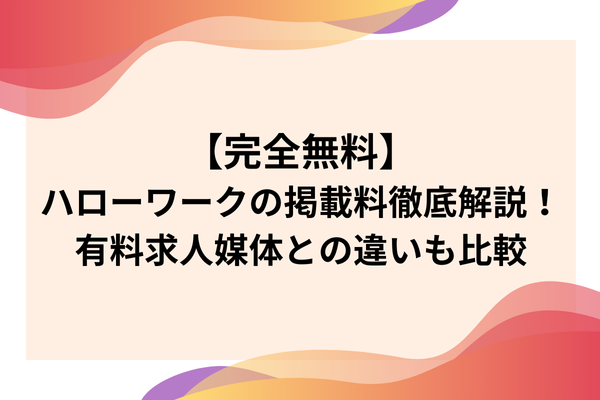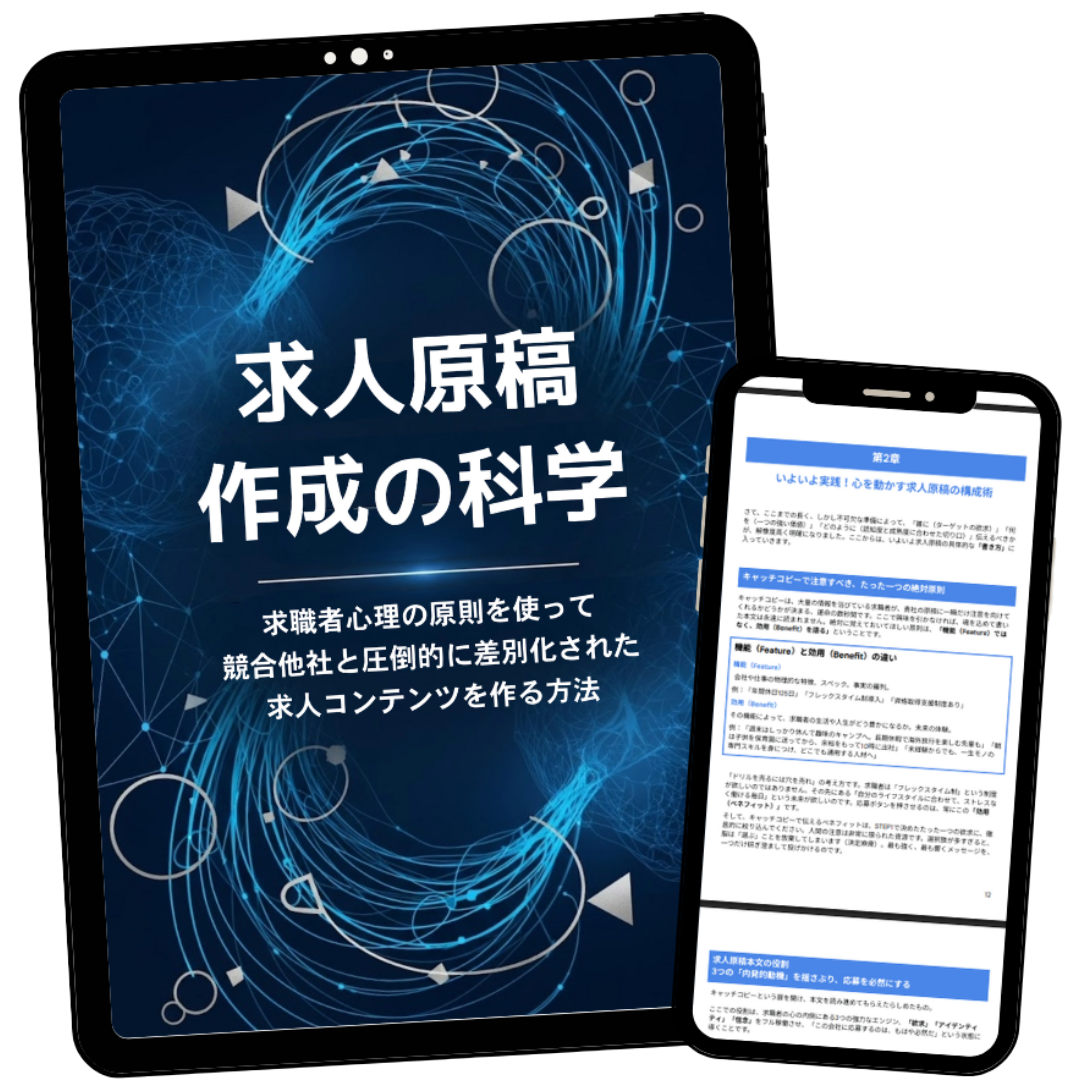「求人広告費がかさんで、経営を圧迫している…」
「コストをかけずに、地域に根差した人材を採用したい」
このような悩みを抱える経営者や採用担当者の方にとって、ハローワークは非常に強力な味方です。
ただ、ハローワークのポテンシャルを最大限に引き出すためには、単に求人を出すだけでは不十分です。
本記事では、「ハローワーク 掲載料」をテーマに、ハロワークの基本から、有料媒体との賢い使い分け、掲載できないケース、そして応募が集まる求人票の作り方まで、採用コストの削減と採用成功を両立させるための実践的ノウハウを解説します。
ハローワークの掲載料は本当に無料?基本情報と利用料金の仕組み
ハローワークの求人掲載料は、結論から言うと完全に無料です。
求人を出す際に初期費用や掲載料、成約時の手数料など一切かかりません。
厚生労働省が運営する公的な職業紹介機関であるため、企業は安心してコストをかけずに求人を掲載できます。
また、掲載後に追加費用が発生することもありません。
この仕組みは、特に中小企業や個人事業主にとって大きなメリットとなっています。
ただし、求人内容や企業の状況によっては掲載できない場合もあるため、注意が必要です。
ハローワークで求人を出す場合の利用料金と費用構造を解説
ハローワークで求人を出す場合、利用料金は一切かかりません。
求人票の作成や掲載、応募者の紹介、面接調整など、すべてのサービスが無料で提供されます。
※応募者の紹介までをハローワークが無料で行い、その後の面接日程の調整は企業と応募者で直接進めるのが一般的です。
また、採用が決まった場合でも手数料や成功報酬は発生しません。
この無料サービスは、厚生労働省が雇用促進を目的として運営しているため実現しています。
一方で、民間の求人媒体では掲載料やオプション費用が発生することが一般的です。
ハローワークの無料掲載は、採用コストを抑えたい企業にとって非常に魅力的な選択肢です。
求人サイト・有料求人媒体との掲載料の違いとは
ハローワークと民間の求人サイトや有料求人媒体では、掲載料やサービス内容に大きな違いがあります。
民間の求人サイトでは、掲載期間やプランによって数万円から数十万円の費用がかかることが一般的です。
また、オプションやスカウト機能などを利用する場合は、さらに追加費用が発生します。
一方、ハローワークはすべてのサービスが無料で利用できるため、コストをかけずに幅広い求職者にアプローチできます。
下記の表で、ハローワークと有料求人媒体の掲載料の違いを比較します。
| 媒体名 |
掲載料 |
特徴 |
| ハローワーク |
無料 |
公的機関
全国の求職者にアプローチ可能 |
| 民間求人サイト |
数万円~数十万円
※無料掲載できる媒体も一部あり |
ターゲット層やオプションが豊富 |
無料掲載の理由と掲載できないケース
ハローワークが無料で求人掲載を提供している理由は、国の雇用対策の一環として、すべての企業に平等な採用機会を与えるためです。
そのため、企業規模や業種を問わず、基本的には誰でも利用できます。
ただし、法令違反や過去にトラブルがあった企業、虚偽の求人情報を掲載したことがある場合などは、掲載を断られるケースもあります。
また、求人内容が公序良俗に反する場合や、雇用保険の適用事業所でない場合も掲載できません。
無料で利用できる反面、一定のルールや審査があることを理解しておきましょう。
- 法令違反歴がある企業は掲載不可
- 虚偽求人や過去のトラブルがある場合は審査で落ちる
- 雇用保険未加入の事業所は掲載できない場合がある
詳細については次の項目で説明します。
ハローワークに求人を出せない会社とは?掲載条件と注意点
ハローワークは原則として多くの企業が利用できますが、すべての会社が求人を掲載できるわけではありません。
掲載には一定の条件があり、これを満たさない場合は求人票の受理を断られることがあります。
特に、法令違反歴や過去のトラブル、雇用保険の未加入などが主な理由です。
また、求人内容が公序良俗に反する場合や、労働条件が著しく不適切な場合も掲載不可となります。
事前に自社の状況や求人内容を確認し、必要な条件を満たしているかチェックすることが重要です。
求人掲載できない主な条件・企業の特徴
ハローワークで求人掲載ができない主な条件や企業の特徴は以下の通りです。
これらに該当する場合、求人票の受理が拒否されることがありますので注意しましょう。
| 求人掲載できない主な条件・企業の特徴 |
| 過去に法令違反(労働基準法、最低賃金法など)があった企業 |
| 虚偽の求人情報を掲載したことがある企業 |
| 雇用保険の適用事業所でない場合 |
| 反社会的勢力と関係がある企業 |
| 求人内容が公序良俗に反する場合 |
必要なもの・雇用保険や助成金の関係
ハローワークで求人を掲載するには、雇用保険の適用事業所であることが基本条件となります。
雇用保険に加入していない場合、求人掲載が認められない場合があります。
また、助成金の申請を考えている場合も、雇用保険の加入が必須となります。
求人掲載時には、事業所番号や法人番号、会社の登記簿謄本などの書類が必要になることもあります。
事前に必要書類を準備し、スムーズに手続きを進めましょう。
- 雇用保険適用事業所番号
- 法人番号や登記簿謄本
- 助成金申請時は追加書類が必要な場合あり
事業所の登録・管轄などの基本的なルール
ハローワークで求人を掲載するには、まず事業所の登録が必要です。
登録は、事業所の所在地を管轄するハローワーク、またはハローワークインターネットサービスで行います。
管轄外のハローワークでは原則として手続きができませんので注意しましょう。
登録後は、求人票の作成や内容の確認、必要書類の提出などの手続きを進めます。
また、複数の事業所がある場合は、それぞれの事業所ごとに登録が必要となる場合があります。
管轄や登録ルールを事前に確認しておくことで、スムーズな求人掲載が可能です。
- 事業所所在地の管轄ハローワーク、またはハローワークインターネットサービスで登録
- 複数事業所は個別登録が必要な場合あり
- 登録後に求人票作成・内容確認を実施
【実践ガイド】ハローワーク求人掲載の流れとステップ
ハローワークで求人を掲載する際の流れは、事業所登録から求人票の作成、必要書類の提出、求人情報の公開まで複数のステップがあります。
初めて利用する場合でも、手順をしっかり押さえておけばスムーズに進めることができます。
また、最近ではインターネットサービス(ハローワークインターネットサービス)を活用することで、窓口に行かずに手続きができるケースも増えています。
ここでは、具体的な流れと各ステップのポイントを解説します。
求人掲載の申し込みと申込書の記入方法
求人掲載の申し込みは、まず事業所の管轄ハローワークで行います。
窓口で求人申込書を受け取り、必要事項を記入します。
申込書には、会社情報、募集職種、仕事内容、雇用条件、給与、勤務時間など詳細な情報を記載する必要があります。
記入内容に不明点がある場合は、窓口担当者が丁寧にサポートしてくれるので安心です。
正確かつ具体的に記入することで、求職者に魅力的な求人情報を提供できます。
- 会社情報や事業内容の記入
- 募集職種・仕事内容・雇用条件の詳細記載
- 窓口担当者によるサポートあり
ハローワークインターネットサービスを利用することで、自宅のパソコンから申し込みをすることも可能です。
ハローワークインターネットサービスについては、下の記事で登録~求人の申し込みまでの詳細を解説しています↓
必要書類・提出物と登録手続きの流れ
求人掲載には、事業所登録に必要な書類や求人票の提出が求められます。
主な必要書類は、事業所の登記簿謄本、雇用保険適用事業所番号、会社案内などです。
これらの書類を揃えたうえで、求人票とともにハローワーク窓口に提出します。
書類に不備がなければ、その場で登録手続きが進みます。
ハローワークインターネットサービスを利用する場合も、初回は書類の郵送や持参が必要な場合があります。
事前に必要書類を確認し、スムーズな手続きを心がけましょう。
- 登記簿謄本や雇用保険番号の準備
- 求人票の作成、提出
- インターネットサービス利用時も初回は書類提出が必要な場合あり
窓口・インターネットサービス(求人情報公開・マイページ活用)
ハローワークの求人掲載は、従来の窓口での手続きに加え、ハローワークインターネットサービスを活用することで、より便利に行えるようになっています。
窓口では担当者が直接サポートしてくれるため、初めての方でも安心して手続きが可能です。
一方、インターネットサービスでは、求人情報の公開や内容の修正、応募者管理などがオンラインで完結します。
マイページを作成すれば、求人票の管理や応募者とのやり取りも効率的に行えます。
状況に応じて窓口とインターネットサービスを使い分けることで、よりスムーズな採用活動が実現できます。
| 窓口 |
担当者によるサポートが受けられる |
| インターネットサービス |
24時間求人情報の管理が可能 |
| マイページ |
求人票の修正や応募者管理が簡単 |
掲載までの時間と応対担当者とのやり取り
ハローワークで求人を掲載する場合、書類提出や内容確認が完了すれば、通常は即日から数日以内に求人情報が公開されます。
窓口での手続きでは、担当者が内容をチェックし、不明点や修正点があればその場でアドバイスを受けられます。
インターネットサービスを利用する場合も、内容確認後に公開となるため、スピーディーな対応が期待できます。
担当者とのやり取りを円滑に進めることで、より早く求人を公開できるだけでなく、内容の充実やトラブル防止にもつながります。
- 即日~数日で求人情報が公開
- 担当者が内容を丁寧にチェック、アドバイス
- スムーズなやり取りでトラブル防止
ハローワーク求人掲載の期間・延長・有効期限について
ハローワークの求人掲載には、一定の掲載期間と有効期限が設けられています。
通常、求人票の有効期間は原則として求人を受理した月の翌々月末までですが、希望すれば延長手続きも可能です。
掲載期間が終了する前に延長申請を行うことで、継続して求人情報を公開できます。
また、掲載内容の修正や更新も随時可能なので、状況に応じて柔軟に対応できます。
有効期限や延長手続きのルールを把握しておくことで、採用活動を計画的に進めることができます。
求人掲載期間の基本と延長手続きの方法
ハローワークの求人掲載期間は、原則として求人を受理した月の翌々月末までです。
掲載期間が終了する前に、延長を希望する場合は、窓口やインターネットサービスから延長申請を行うことができます。
延長手続きは何度でも可能で、採用が決まるまで継続して掲載することもできます。
ただし、掲載内容に変更がある場合は、必ず修正手続きを行いましょう。
延長申請を忘れると自動的に掲載終了となるため、スケジュール管理が重要です。
- 掲載期間は原則として求人を受理した月の翌々月末まで
- 延長申請は窓口、インターネットで可能
- 延長回数に制限はなし
掲載内容の修正・公開延長のコツ
求人掲載中に内容を修正したい場合は、窓口またはインターネットサービスから随時変更が可能です。
仕事内容や給与、勤務条件などに変更が生じた場合は、速やかに修正手続きを行いましょう。
また、応募が少ない場合は、掲載内容を見直して魅力的な表現に変更することも効果的です。
公開延長の際は、定期的に内容を更新することで、求職者の目に留まりやすくなります。
担当者と相談しながら、より良い求人票を作成することが採用成功のポイントです。
- 内容変更は随時可能
- 応募状況に応じて内容を見直す
- 定期的な更新で求職者の注目度アップ
採用活動を成功させる!求人作成・応募・選考までの具体的コツ
ハローワークでの採用活動を成功させるためには、求人票の作成から応募者対応、選考、採用後のフォローまで一貫した工夫が必要です。
無料で掲載できるメリットを最大限に活かし、求職者にとって魅力的な情報を提供することが重要です。
また、応募者とのやり取りや面接の進め方、採用後のフォローアップまで丁寧に対応することで、ミスマッチを防ぎ、定着率の向上にもつながります。
ここでは、各ステップごとの具体的なコツを紹介します。
求人情報の作成ポイント(記載内容・画像・職種・仕事内容)
求人票を作成する際は、求職者が知りたい情報を分かりやすく、具体的に記載することが大切です。
職種や仕事内容、給与、勤務時間、休日、福利厚生などの基本情報はもちろん、職場の雰囲気や求める人物像も明記しましょう。
画像や写真を活用することで、職場のイメージが伝わりやすくなります。
ハローワークインターネットサービスでは、『事業所PR情報』のページで会社のロゴや職場の写真などを登録できます。
これを活用することで、求職者に対して職場のイメージをより具体的に伝えられます。
また、仕事内容はできるだけ具体的に記載し、未経験者歓迎や経験者優遇などの条件も明確にしましょう。
これにより、ミスマッチを防ぎ、応募者の質を高めることができます。
- 仕事内容や職種は具体的に記載
- 給与・勤務条件、福利厚生を明確に
- 職場写真やイメージ画像を活用
- 求める人物像や歓迎条件も記載
さらに詳しく...
ハローワークの求人票については、求職者からの見え方や求人票の文字数の制限など、独特な仕組みやルールがあります。
この特徴を踏まえたうえで、効果的なハローワーク用の求人票を作成することがポイント。
ハローワーク求人票の作成のポイントについては下の記事をご確認ください↓
記事で解説しているように、ハローワーク求人票では、特に重要な6項目を作りこむようにしましょう。
- 項目1:職種名 - 最大28文字のキャッチコピー
- 項目2:仕事内容 - 最初の3行が第一印象を決める
- 項目3:就業時間に関する特記事項 - 求職者の入職後の働き方のイメージをサポートする
- 項目4:休日 - 求職者の働き方や生活スタイルに大きく影響する条件
- 項目5:事業内容と会社の特長 - 求職者が家族や友人にどんな会社かを説明する材料になる
- 項目6:求人に関する特記事項 - 遠慮することなく自由に書く
応募者とのやり取り・面接の流れと注意点
応募者からの問い合わせや応募があった際は、迅速かつ丁寧な対応を心がけましょう。
面接日程の調整や必要書類の案内など、スムーズなやり取りが応募者の印象を左右します。
面接時には、仕事内容や職場環境について詳しく説明し、応募者の希望や不安にも耳を傾けることが大切です。
また、面接結果の連絡はできるだけ早く行い、合否に関わらず丁寧な対応を心掛けましょう。
トラブル防止のため、やり取りの記録を残しておくこともおすすめです。
- 応募者対応は迅速・丁寧に
- 面接日程や必要書類を明確に案内
- 仕事内容や職場環境を詳しく説明
- 面接結果は早めに連絡
ミズサキは応募者との連絡の際に使えるメッセージテンプレートを公開しています。
状況に応じて、是非ご活用ください↓
選考から採用・採用後のフォローアップ
選考では、応募者のスキルや経験だけでなく、職場との相性や意欲も重視しましょう。
採用が決まったら、入社手続きや研修、職場への紹介など、スムーズな受け入れ体制を整えることが重要です。
また、採用後も定期的にフォローアップを行い、困りごとや不安がないか確認することで、早期離職の防止につながります。
ハローワークの担当者とも連携し、必要に応じてサポートを受けることも可能です。
採用活動の一連の流れを丁寧に進めることで、企業と求職者双方にとって満足度の高い採用が実現します。
- スキル・経験・意欲・相性を総合的に判断
- 入社手続きや研修を丁寧に実施
- 採用後も定期的にフォローアップ
- ハローワーク担当者と連携してサポートを活用
ハローワーク掲載のメリット・デメリット徹底解説
ハローワークの求人掲載は無料で利用できる点が最大の魅力ですが、他にも多くのメリットがあります。
一方で、民間の有料求人媒体と比べるとデメリットや向き・不向きも存在します。
ここでは、ハローワーク掲載のメリット・デメリットを徹底的に解説し、どのような企業や求人に向いているのかを明らかにします。
実際の利用者の声や体験談も交えながら、最適な採用手法を選ぶための参考にしてください。
無料掲載ならではのメリット・活用法
ハローワークの最大のメリットは、何といっても求人掲載が完全無料である点です。
採用コストを抑えたい中小企業や個人事業主にとっては、非常に大きな魅力となります。
また、全国のハローワークネットワークを通じて幅広い求職者にアプローチできるため、地元人材の確保にも有効です。
2022年度の実績では、ハローワークは新規求職申込件数約458万人、新規求人数約1052万人、就職件数約126万人と、民間の求人サイトや職業紹介会社よりも多くの求職者が利用をしているサービスです。
サイトへのアクセス数は1日で240万件にも上ります。
さらに、ハローワークの担当者によるサポートや、助成金・雇用保険などの各種制度の案内も受けられます。
無料でありながら、求人票の修正や延長も柔軟に対応できるため、継続的な採用活動にも最適です。
- 掲載料が完全無料
- 全国の求職者にアプローチ可能
- 担当者のサポートや各種制度の案内が受けられる
- 求人票の修正・延長が柔軟
ハローワーク活用のメリットについては下の記事で詳しく解説しています↓
有料求人媒体との比較・向いているケース
ハローワークと有料求人媒体を比較すると、コスト面だけでなく、ターゲット層や掲載方法にも違いがあります。
有料媒体は、専門職や若手人材、即戦力を求める場合に強みがありますが、掲載料が高額になることも。
一方、ハローワークは幅広い年齢層や地元志向の求職者にリーチでき、コストをかけずに採用活動を行いたい企業に向いています。
下記の表で、両者の特徴を比較します。
| 項目 |
ハローワーク |
有料求人媒体 |
| 掲載料 |
無料 |
数万円~数十万円 |
| ターゲット層 |
幅広い年齢層・地元志向 |
専門職・若手・即戦力 |
| サポート |
担当者による無料サポート |
オプションで手厚いサポート |
| 掲載期間 |
原則として求人を受理した月の翌々月末まで(延長可) |
プランによる |
また、ハローワーク以外で、無料で利用できる求人媒体について下の記事で解説しています。
ご興味のある方はぜひ読んでみてください↓
利用者(企業・求職者)のリアルな声・体験談
実際にハローワークを利用した企業や求職者からは、さまざまな声が寄せられています。
企業側からは「無料でここまでサポートしてもらえるとは思わなかった」「地元の人材を採用できた」といった満足の声が多く聞かれます。
一方で「応募者の年齢層が広く、選考に時間がかかった」「専門職の応募が少なかった」といった課題も挙げられています。
求職者からは「地元の求人が多くて探しやすい」「担当者が親身に相談に乗ってくれた」といったポジティブな意見が目立ちます。
利用者のリアルな体験談を参考に、自社の採用活動に活かしましょう。
- 企業:無料でサポートが手厚い
- 企業:地元人材の採用に成功
- 企業:応募者の幅が広く選考に時間がかかる場合も
- 求職者:地元求人が多く探しやすい
- 求職者:担当者が親身に対応
【Q&A】ハローワーク求人掲載のよくある質問とトラブル対応
ハローワークで求人掲載を行う際には、さまざまな疑問やトラブルが発生することがあります。
ここでは、よくある質問とその対応策について解説します。
掲載できない理由が分からない場合や、職種ごとの掲載可否、他の求人媒体との併用方法など、実際の現場でよくある悩みをQ&A形式でまとめました。
トラブル時の相談先や、スムーズな対応のポイントも紹介しますので、困ったときの参考にしてください。
掲載できない理由が分からない時の相談先
求人掲載を申し込んだものの、掲載不可となった場合は、まず管轄のハローワーク窓口に相談しましょう。
担当者が理由を説明し、必要な改善点や追加書類についてアドバイスしてくれます。
また、ハローワークの公式サイトや電話相談窓口も活用できます。
掲載不可の理由が分からない場合は、自己判断せず必ず専門の担当者に確認することが大切です。
- 管轄ハローワーク窓口で相談
- 担当者が理由や改善点を説明
- 公式サイトや電話相談も利用可能
職種ごとの掲載可能性・経験が必要なケース
ハローワークでは、ほとんどの職種で求人掲載が可能ですが、一部の専門職や資格が必要な職種では、追加書類や証明が求められる場合があります。
また、経験者のみを募集する場合は、その旨を求人票に明記する必要があります。
職種ごとの掲載可否や必要条件については、事前にハローワーク担当者に確認しておくと安心です。
- ほとんどの職種で掲載可能
- 専門職、資格職は追加書類が必要な場合あり
- 経験者募集は求人票に明記
求人媒体活用や転職サイトとの併用のポイント
ハローワークと民間の求人媒体や転職サイトを併用することで、より多くの求職者にアプローチできます。
ハローワークは地元志向や幅広い年齢層に強く、有料媒体は専門職や若手層に強みがあります。
併用する際は、求人内容やターゲット層を明確にし、それぞれの媒体の特性を活かした情報発信を心がけましょう。
また、応募者管理や選考フローの整理も重要です。
- ハローワークと有料媒体の併用で幅広い層にアプローチ
- 媒体ごとに求人内容やターゲットを調整
- 応募者管理や選考フローの整理が重要
有料求人媒体については下の記事で詳細を確認できます↓
まとめ:ハローワークを賢く活用し、採用活動を成功に導く
この記事では、ハローワークの求人掲載について、料金体系から掲載方法、成功のコツまでを解説しました。
ハローワークの最大の魅力は、掲載料・紹介料・成功報酬が一切かからない完全無料の採用サービスである点です。
採用コストを大幅に削減できるため、特に中小企業やスタートアップにとって非常に強力な味方となります。
ただし、そのメリットを最大限に活かすには、単に求人を出すだけでは不十分です。
採用成功の鍵は、求職者の心に響く具体的な求人票を作成し、応募者一人ひとりに迅速かつ丁寧な対応を心がけることにあります。
また、法令遵守など掲載には一定の条件があるため、事前にルールを確認することも忘れてはなりません。
有料求人媒体との違いを理解し、自社の採用戦略に合わせてハローワークを有効活用、あるいは併用することで、採用の可能性はさらに広がります。
本記事を参考に、貴社の採用活動を成功へと導いてください!