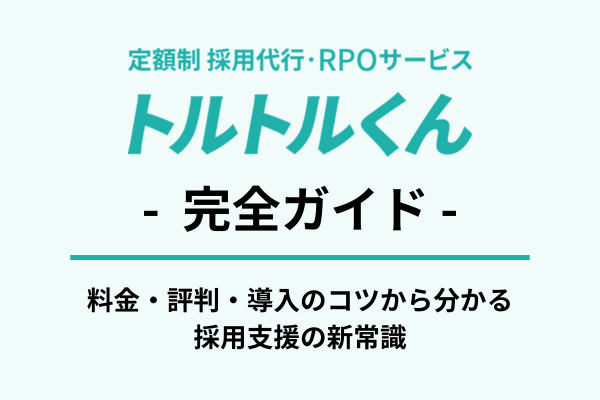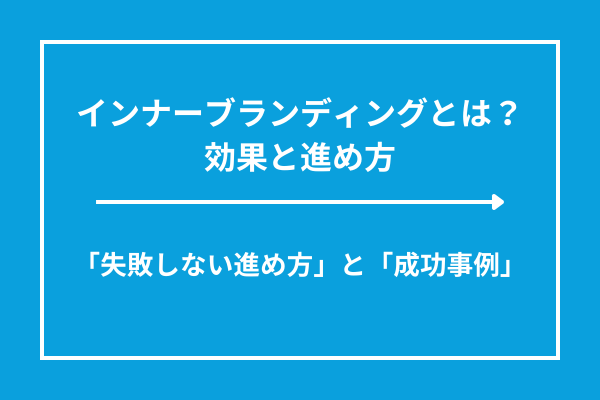組織が急拡大する中で、創業時の熱量を維持するのは容易ではありません。いざ施策を講じようとしても、「現場の社員に『宗教的だ』と反発されたらどうしよう」「効果が見えにくく、施策を継続できるか不安だ」といった悩みがつきまとうものです。
そんな時に知っておきたいのが「インナーブランディング」です。
インナーブランディングは、企業の理念や独自の価値観を社内に浸透させて、社員のエンゲージメントを高めるための一連の活動のことです。
本記事では、インナーブランディングの基礎知識から、他社の具体的な成功事例、そして現場を巻き込むための実践ステップまでを網羅的に解説します。
特に、多くの企業が陥りがちな「現場のしらけ・反発」を回避するための進め方や、プロジェクトを成功に導くための具体的な効果測定指標(KPI)についても詳しく触れています。
ぜひ、これからの組織変革の一手としてお役立てください。
>> インナーブランディングを加速させる採用広報|リクルーティングPR-Xはこちら
インナーブランディングとは?アウターブランディングとの違い
「ブランディング」と聞くと、顧客に向けた広告やPR活動を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、企業が持続的に成長するためには、外側だけでなく「内側」へのブランディングが不可欠です。
インナーブランディングの定義
インナーブランディングとは、企業の理念(ミッション・ビジョン・バリュー)や独自の価値観を社内に浸透させ、従業員一人ひとりに「自分ごと」として共感・体現してもらうための一連の活動を指します。
単に社訓を暗記させたり、唱和させたりすることではありません。
従業員が「自分たちの会社は何を目指しているのか」「自分の仕事は社会にどう貢献しているのか」を深く理解し、日々の業務や判断において、自然と理念に基づいた行動がとれる状態を目指すものです。
これにより、組織全体のベクトルが揃い、従業員エンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)が高まる効果が期待できます。
尚、Gallup社が実施した従業員エンゲージメントの国際比較調査によると、日本の従業員のうち「熱意あふれる(Engaged)」社員の割合はわずか7%と世界的に見ても最低水準です。
このことからも、日本企業のインナーエンゲージメントの必要性はますます高まっていると考えられています。
インナーブランディングとアウターブランディングの関係
インナーブランディングを理解する上で欠かせないのが、「アウターブランディング(エクスターナルブランディング)」との関係性です。
| 項目 |
インナーブランディング |
アウターブランディング |
| 目的 |
組織を作る、人材を定着させる |
売上を作る、認知を広げる |
| 手段 |
社内報、ワークショップ、表彰制度、オフィス環境など |
Webサイト、広告、ロゴ、プレスリリースなど |
| 役割 |
社外への約束を果たすために、社内の意識と行動を整えること |
社外に対して「私たちはこんな価値を提供します」と約束すること |
重要なのは、この2つは企業の成長を支える「車の両輪」のように相互関係にあり、どちらが欠けても企業活動はうまくいかないということです。
もし、インナーブランディング(中身)が伴っていない状態で、アウターブランディング(外見)ばかりを強化したらどうなるでしょうか?
華やかな広告を見て入社した求職者や、期待してサービスを利用した顧客は、「言っていることと、実際の社員の態度が違う」と強烈なギャップを感じるでしょう。これは結果として「誇大広告」となり、企業の信頼を大きく損なうリスクになります。
「外に向けた約束」を守る実力を、「内の結束」で養う。この両輪が噛み合って初めて、真に強いブランドが形成されるのです。
なぜ今、インナーブランディングが必要なのか?4つのメリット
「組織作りは重要だが、売上に直結しないコストではないか?」
そう捉えられることもありますが、現代においてインナーブランディングは、単なる福利厚生や社内広報の枠を超え、企業の存続を左右する経営戦略そのものになっています。
なぜ今、多くの企業がこの取り組みに注力しているのか。組織運営において不可欠な4つのメリットを解説します。

【採用・定着】優秀な人材の確保と離職率の低下
最大のメリットは、深刻化する労働力不足への対抗策となる点です。
終身雇用が崩壊し、転職が当たり前となった現在、給与や待遇といった条件面だけでは人材を引き留めることが難しくなっています。
インナーブランディングによって「この会社は何のために存在し、どこに向かっているのか」というビジョンへの共感が生まれると、従業員の会社に対するエンゲージメント(帰属意識)が高まります。
結果として、「この会社で働くこと自体に意義がある」と感じる層が定着し、離職率の低下(リテンション)に直結します。また、その熱量は採用活動においても求職者に伝播し、ミスマッチのない優秀な人材の確保を容易にします。
事実、Gallup社による調査によると、エンゲージメントスコアが高い上位25%のチームは、下位25%のチームと比較して、以下の通り離職率が劇的に低いことが判明しています。
- 元々離職が多い業界: エンゲージメントが高いチームは、離職率が21%低い。
- 元々定着が良い業界: エンゲージメントが高いチームは、離職率が51%低い。
【生産性】従業員エンゲージメントと生産性の向上
理念が浸透することで、従業員の働き方は「やらされ仕事」から「自分ごとの仕事」へと変化します。
会社の目指すゴールが明確であれば、従業員は上司の細かい指示を待たずとも、「ゴールに近づくためには今何をすべきか」を自律的に判断できるようになります。
現場の意思決定スピードが上がり、部門間の連携もスムーズになるため、組織全体の業務効率と生産性が向上します。
実際に、英国ウォーリック大学が700名以上を対象とした実験では、幸福感が高まった従業員は、そうでないグループと比較して、生産性が約12%向上することが実証されています。
さらに、Gallup社のデータでは、エンゲージメントの高いチームは低いチームと比較して、生産性が14~18%向上、収益性が23%向上するとわかっています。
【顧客体験】サービス品質の均質化・向上(CX)
インナーブランディングは、顧客満足度(CS)や顧客体験(CX)の向上にも寄与します。
マニュアルで行動を縛るのには限界がありますが、判断軸となる「価値観(バリュー)」が共有されていれば、想定外の事態においても、現場の従業員が企業ブランドにふさわしい振る舞いを選択できるようになるからです。
事実、顧客ロイヤルティの指標であるNPS(ネット・プロモーター・スコア)の開発元であるBain & Companyの調査によると、従業員エンゲージメントと顧客NPSの間に強い相関関係があるとされています。また、Gallupデータでは、エンゲージメントの高いチームは、顧客ロイヤルティ/エンゲージメントスコアが10%高いという結果が出ています。
【ブランド】対外的なブランド力の底上げ
SNS時代において、従業員一人ひとりは企業の「メディア(広告塔)」そのものです。
どんなに素晴らしいTVCMを流しても、SNS上で従業員が会社の悪口を言っていたり、接客態度が悪かったりすれば、企業ブランドは一瞬で毀損します。
逆に、従業員が自社を誇りに思い、ポジティブな発信や行動を行えば、それは広告費をかけずとも最強のプロモーションとなります。「中の人」の熱量が、外のブランド力を底上げするのです。
Gallupの調査によれば、エンゲージメントの高い組織では、安全事故(労働災害)や商品ロス・盗難などのリスクが大幅に低減されるというデータが出ています。
【重要】インナーブランディングが失敗する「3つの壁」とその対策
インナーブランディングには多くのメリットがある一方で、「途中でお蔵入りになった」「現場がしらけてしまった」という失敗事例も少なくありません。
担当者が最も恐れる「現場の反発」や「形骸化」といったリスクを回避するために、事前に知っておくべき3つの失敗パターンと、その対策をお伝えします。
失敗1:トップダウンによる「価値観の押し付け」
最も多い失敗が、一部のメンバーだけで作った綺麗な言葉(理念)を、一方的に現場へ通達してしまうケースです。
現場からすれば、「忙しいのにお題目を増やされた」「上層部の自己満足だ」と受け取られ、かえって心が離れてしまいます。
対策:現場を巻き込む「ボトムアップ」のアプローチ
理念の策定や浸透施策を検討する段階から、現場のキーマンを巻き込みましょう。
特に「トップダウンの失敗」を防ぐ鍵は、ミドルマネジメント(中間管理職)にあります。事実、Gallupの調査によれば、チームのエンゲージメントの変動要因の70%は「マネージャー・上司の質」だけで説明できるとされています。つまり、どれほど素晴らしい理念を掲げても、現場の課長や部長がそれを理解し、部下に翻訳して伝えなければ、チームに理念を浸透させることは非常に難しいということです。
ワークショップなどで「自分たちの強みは何か」「どうありたいか」を従業員自身に語ってもらい、その言葉を吸い上げて理念に反映させるプロセスが重要です。「自分たちで作った言葉」であれば、納得感と当事者意識が格段に高まります。
失敗2:施策のやりっぱなし(イベントの形骸化)
キックオフイベントやクレドカードの配布を行って満足し、その後何もしないパターンです。
一時的に盛り上がっても、日常業務に戻れば意識は薄れます。「あのアツいイベントは何だったのか」と、冷めた空気が流れる原因になります。
対策:日常業務への「仕組み化」
一過性のイベント(点)ではなく、継続的な仕組み(線)で設計します。
- 毎朝の朝礼で理念に関するエピソードを共有する
- 人事評価制度に「バリューの体現度」を組み込む
- 称賛ツール(サンクスカード等)で日常的にフィードバックし合う
このように、意識せざるを得ない環境を日常の中に組み込むことが定着への近道です。
失敗3:効果が見えにくく予算が続かない
インナーブランディングは、人の意識を変える活動であるため、即効性は期待できません。
投資対効果(ROI)が曖昧なままだと、成果を証明できずに施策の継続が困難になることがあります。
対策:定量的なKPIを事前に定義しておく
スタートする前に、何を成功指標とするか(KPI)を明確にしておきましょう。
売上などの財務指標だけでなく、以下のような指標を定点観測することをおすすめします。
| 指標 |
内容 |
| eNPS(従業員推奨度) |
親しい友人に自社への入社を勧めたいか |
| 離職率・定着率 |
特に若手やハイパフォーマーの推移 |
| 採用コスト・リファラル採用数 |
社員紹介による採用が増えているか |
| 社内報の閲覧率・イベント参加率 |
関心の度合い |
これらの数字を用いて「組織の状態」を可視化することで、プロジェクトの健全な運営と改善が可能になります。
インナーブランディングの正しい進め方 5ステップ
失敗の多くは、準備不足のままいきなり「社内イベント」や「ポスター掲示」などの手段(How)に飛びつくことで起こります。

Step1. 現状分析(サーベイ・ヒアリング)
まずは組織の現状分析から始めます。「なぜ理念が浸透していないのか?」という原因は企業によって異なります。
これらを特定するために、全社員向けのアンケート(サーベイ)や、キーマンへのヒアリングを実施し、現状と理想のギャップ(課題)を明確にします。
Step2. 理念・MVVの策定・再定義
現状分析で見えた課題に基づき、浸透させるべき「芯」となる言葉を整えます。
もし既存の理念が形骸化していたり、今の事業フェーズに合わなくなっていたりする場合は、このタイミングでミッション・ビジョン・バリュー(MVV)やパーパスの再定義を行います。
重要なのは、単に綺麗なスローガンを作ることではありません。「なぜその言葉なのか」「その言葉にはどんな歴史や想いが込められているのか」というストーリー(物語)まで言語化することです。
Step3. 戦略・コンセプト設計
「誰に(ターゲット)」「何を(メッセージ)」「どのように(手段)」伝えるかの全体戦略を描きます。
| コンセプトの指針 |
内容 |
| 誰に |
全社員一斉か、まずは管理職から固めるか。 |
| 何を |
新しいバリューの「認知」を広げるのか、具体的な「行動変容」を促すのか。 |
| どのように |
職場環境の改善・企業理念の情報発信など、どのような手段を取るか。 |
この段階で、前述した「KPI(効果測定指標)」も設定しておきます。
Step4. 具体的な浸透施策の実行
戦略に基づき、具体的な施策を実行します。
大きく分けて「知る(認知)」「理解する(対話)」「行動する(体現)」の3段階があり、フェーズに合わせて社内報、ワークショップ、表彰制度などのツールを組み合わせて展開します。
Step5. 効果測定とフィードバック
施策実施後は、Step1で行ったサーベイを再度実施し、スコアの変化を確認します。
「認知度は上がったが、行動には結びついていない」などの結果が出れば、次はワークショップを強化するなど、PDCAサイクルを回して改善を続けます。
インナーブランディングの具体的な施策・手法と企業事例
ここでは、Step4で実施する具体的な施策について、有名企業の成功事例や、中堅企業でも取り入れやすい手法を交えて解説します。
施策は大きく「情報発信」「対話・体験」「環境・制度」の3つに分類できます。
【情報発信】社内報・動画・ブランドブック

理念やビジョンを「言葉」や「ビジュアル」で正しく伝え、認知を広げるための施策です。
ザ・リッツ・カールトン:「クレドカード」による企業理念の浸透
ザ・リッツ・カールトンは、全従業員が携帯する「クレドカード」と、「ラインナップ」という毎日の朝礼によって、企業理念を浸透させています。
- クレドカードとは:「ゴールドスタンダード」と呼ばれる企業理念体系を、クレドカードとして全従業員が携帯。
- ラインナップとは: 世界中の拠点で毎日、全従業員がシフトに入る前に集まり、クレドやサービスのバリューについてディスカッションを実施。
また、クレドに基づいた判断であれば、上司の許可なく1日2,000ドルまでの決裁権が現場スタッフに与えられている(通説)ことは有名です。これは「理念を信じて任せる」という究極のインナーブランディングであると言えます。
株式会社マクロミル:社内報「ミルコミ」・Web社内報「NOW」による心理的安全性の向上
株式会社マクロミルが実施したのは、成功談だけでなく、先輩社員の「失敗談(修羅場)」を赤裸々に公開した社内報「ミルコミ」「NOW」です。これらの社内報は、経団連推薦社内報審査や「社内報アワード」でグランプリやゴールド賞を受賞するなど、外部からも高い評価を受けています。
「失敗しても大丈夫」「先輩も同じ苦労をしてきた」というメッセージは、組織の「心理的安全性」を高める効果があります。Googleの「プロジェクト・アリストテレス」でも言及されたように、心理的安全性はチームの生産性を高める最重要因子であると言われており、この社内報企画はインナーブランディングとして組織に大きな影響を与えたと考えられます。
【対話・体験】社内イベント・ワークショップ

一方的な発信だけでなく、従業員自身が考え、体感する場を作ることで「自分ごと化」を促します。
ぺんてる株式会社:全社員参加型ワークショップ「RAKUGAKI WEEK」によるビジョンの実体験
文房具メーカーのぺんてる株式会社では、「表現するよろこびを育む」というビジョンの共有のため、自社製品のペンなどを使って工場の壁や巨大な布に自由に落書きを行う、という世界中の従業員3,000人以上が参加するワークショップ「PENTEL RAKUGAKI WEEK」を開催しています。
普段は製造や事務に従事し、エンドユーザーの「描く喜び」を直接感じにくい社員が、自らユーザー体験をすることで、自社製品とビジョンの価値を身体的に理解できたと言います。
味の素株式会社:表彰制度「ASVアワード」による企業理念の具体化
味の素は、事業を通じて社会価値と経済価値を共創するという独自の取り組みを「ASV(Ajinomoto Group Shared Value)」と称して、経営の基本方針としています。このASVを社員に理解してもらい、行動を変えるための施策として、温室効果ガス削減と収益化を両立させたプロジェクトなど、ASVを体現した取り組みを表彰する「ASVアワード」が開催されています。
表彰を全社に共有することで、ASVという「抽象的な概念」を「具体的な社員の行動」として可視化することに成功しました。
【環境・制度】オフィス環境・評価制度

物理的な環境や人事制度を変えることで、理念に基づいた行動を「習慣化」させます。
株式会社オリエンタルランド:「マジカルディズニーキャスト」活動による相互称賛文化の醸成
東京ディズニーリゾートには、キャスト同士が仲間の素晴らしい行い対して、専用カードにメッセージを書いて手渡す活動をしています。特に高く評価されたキャストは「マジカルディズニーキャスト」として選出され、マジカルディズニーキャストピンが授与される制度です。
カードを手渡されたキャストが名誉を得られると同時に、良い行動に対して即レスで称賛されるため、行動変容が効率的に行われるのが特徴です。
株式会社ユーザベース:「7つのルール」とオフィス環境の整合性
株式会社ユーザベースの7つのルールとは、自由主義で行こう」「異能は才能」など、同社の価値観を明文化した行動指針のことです。
この行動指針と働く環境(オフィス、制度、ツール)の間に矛盾がないことが、強力なカルチャーを生み出しています。
例えば、「オープンコミュニケーション」を掲げる同社では、オフィスに仕切りを設けない、Slackでの会話をオープンにするなど、物理的・デジタルな環境がルールと整合しています。
インナーブランディングは「最強の採用広報」になる
ここまでインナーブランディングの重要性と進め方を解説してきましたが、この活動は単に「社内を良くして終わり」ではありません。実は、インナーブランディングの成功こそが、最も強力な「採用広報」の武器になるのです。
なぜ、組織の内側を磨くことが、外からの応募者獲得につながるのか。そのメカニズムと、成果を最大化するポイントを解説します。
社内の熱量は、そのまま「採用コンテンツ」になる
求職者が企業選びで最も知りたいのは、綺麗なキャッチコピーや条件だけでなく、「実際にどんな人たちが、どんな想いで働いているのか」というリアルな姿です。
インナーブランディングによって社内の熱量が高まると、そこには自然と良質な「コンテンツ」が生まれます。
- 社員の表情: ワークショップで真剣に議論する姿や、アワードで涙を流して喜ぶ姿。
- 社員の言葉: インタビューで語られる、理念に基づいた熱いエピソード。
- 社内の雰囲気: オフィスで活発にコミュニケーションが交わされる風景。
これらは、作られた広告では決して出せない「本物の魅力」として、求職者の心を強く動かします。
「入社後のギャップ」をなくし、定着率を高める
採用広報において最も避けるべきは、「入社後のミスマッチ」です。
「入ってみたら、イメージと全然違った」という理由での早期離職は、企業にとっても本人にとっても不幸な結果しか生みません。
インナーブランディングが進んでいる企業は、「自分たちが大切にしている価値観(バリュー)」が明確です。そのため、採用広報においても「うちはこういう価値観を大切にする会社です(逆に、こういう価値観は合いません)」と、ありのままの社風を自信を持って発信できます。
結果として、そのカルチャーに共感する人材だけが集まるようになり、入社後の定着率と活躍の確度が飛躍的に高まります。
良いインナーブランディング施策は、プロの手で「外」へ発信しよう
しかし、ここで一つ問題があります。いくら社内で素晴らしい取り組みや感動的なエピソードが生まれていても、それが社外に伝わらなければ、採用にはつながらないということです。
「社内報で良い記事が書けた」「アワードですごいスピーチがあった」。
こうした社内の資産は、社内だけで留めておくのは非常にもったいないことです。
- 社内報のインタビュー記事を、採用オウンドメディア向けにリライトして公開する。
- 社内イベントの様子を動画にまとめ、採用サイトやSNSで発信する。
- 独自の制度やカルチャーを、プレスリリースとして配信する。
このように、社内の空気を第三者(プロ)の視点で言語化し、魅力的なコンテンツとして外へ発信していくことで、インナーブランディングの投資対効果は何倍にも膨れ上がります。
弊社ミズサキは、低リスクで採用ブランディング・採用広報を始められるサービス「リクルーティングPR-X」を提供しています。インナーブランディングとアウターブランディングの相乗効果を活かし、自社のポテンシャルを最大限発揮したいと思っている広報担当の方は、まずはお気軽にご相談ください。
>> リクルーティングPR-Xのサービス詳細・お問い合わせはこちら
インナーブランディングに関するよくある質問(FAQ)
最後に、インナーブランディングに取り組む際によくある疑問について回答します。
まとめ:組織の内側を固め、採用に強い企業へ
インナーブランディングは、単なるイメージアップや自己満足の施策ではなく、社員のエンゲージメント向上による生産性や収益率を向上させ、そして採用活動に大きくプラスの影響を及ぼすものです。一朝一夕で成し遂げられるものではありませんが、個人の価値観が多様化し、変化の激しい現代において、企業が持続的に成長し続けるためには避けて通れない取り組みです。
まずは、自社の現状分析(サーベイ)から始めてみてください。そして、現場の社員を巻き込みながら、少しずつ「自社らしい価値観」を育てていきましょう。
「社内の理念浸透を進めつつ、その魅力を採用に活かしたいなら」
社内で生まれた熱量やユニークな取り組みを、ただの「内輪ネタ」で終わらせないでください。採用広報代行サービス「リクルーティングPR-X」では、貴社の隠れた魅力を発掘し、その取り組みを求職者の心に響くコンテンツへと変換して発信します。
インナーブランディングの成果を採用力に変えたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
>> 採用広報代行サービス「リクルーティングPR-X」の詳細を見る