「ブログやSNSの更新は頑張ってくれているけど、結局それで何人採用できたの? コスパ悪くない?」
採用広報に力を入れ始めた矢先、上司や経営層からこのような厳しい指摘を受け、答えに詰まってしまった経験はありませんか?
「認知獲得が大事だ」となんとなく説明しても、数字にシビアな経営陣には響きません。採用広報は成果が出るまでに時間がかかる施策だからこそ、活動の価値を証明する「ロジック」と「指標」が不可欠です。
この記事では、採用広報における「KPIの正解リスト」と、最終目標(採用人数)から逆算して必要な活動量を割り出す「具体的な計算ロジック」を解説します。
この記事を読み終える頃には、上司を納得させる「根拠ある数値目標」が完成し、自信を持って採用広報を推進できるようになるはずです。
なぜ「採用広報」にKPIが必要なのか?感覚論からの脱却
採用広報の現場では、つい「記事を〇本公開する」「SNSを毎日投稿する」といった「行動量(Do)」を目的にしてしまいがちです。しかし、それだけでは経営層に対して「活動の価値」を証明することはできません。
なぜなら、会社が求めているのは「記事を書くこと」ではなく、「採用課題を解決すること」だからです。
ここで重要になるのが、感覚論ではなく客観的な数値で成果を示すためのKPI(重要業績評価指標)の設定です。
KGIとKPIの違いとは?目標達成の構造を理解する
KPIを設定する前に、必ず対になるKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)との関係性を整理しておく必要があります。この2つは、以下のようなピラミッド構造になっています。

| 項目 |
KGI(重要目標達成指標) |
KPI(重要業績評価指標) |
| 定義 |
最終ゴール
組織として最終的に達成すべき数値目標
|
中間ゴール
KGI達成のためにクリアすべき
通過点の数値目標
|
| 採用広報での例 |
年間採用人数 10名
採用コスト 20%削減
|
採用サイトからの応募数 月間20件
オウンドメディアのPV数 月間1万PV
|
つまり、「KPI(中間ゴール)を一つひとつ達成していけば、論理的にKGI(最終ゴール)が達成される」という設計図を作ることが、KPI設定の本質です。
「とりあえずPVを追う」のではなく、「採用人数(KGI)を達成するために、これだけのPV(KPI)が必要だから追う」という逆算のロジックがあるかどうかが、上司を説得できるかの分かれ道となります。
KPIを設定する3つのメリット(説明責任・改善・モチベーション)
採用広報において適切なKPIを設定することは、単なる進捗管理だけでなく、組織として統一の指標を持ち、統一感のある動きをすることができます。具体的なメリットは以下の3つです。
社内(上司)への説明責任を果たせる(予算確保)
「頑張っています」という主観的な報告ではなく、「目標の応募数に対して進捗率90%です」と数値で語ることで、活動の成果が可視化されます。これにより、次年度の予算確保や、他部署への協力要請(インタビュー依頼など)がスムーズになります。
ボトルネックを特定し、改善できる(PDCA)
数値目標があると、「PVは足りているのに、応募につながっていない(=記事の内容や導線に問題がある)」といった具体的な課題(ボトルネック)が見えてきます。効果の薄い施策を停止し、効果のある施策にリソースを集中させる判断が可能になります。
チームのモチベーション維持
採用という最終成果が出るまでには時間がかかります。KPIという「小さなゴール」を設定することで、日々の活動での達成感を味わえるようになり、チームのモチベーション維持につながります。
【保存版】フェーズ別・採用広報KPI指標一覧リスト
KPIの重要性を理解したところで、次は「具体的にどの数字を見ればいいのか」という疑問にお答えします。
採用広報のKPI設定で最も重要なのは、「求職者の行動フェーズに合わせて指標を使い分ける」ことです。
まだ会社のことを知らない人にいきなり「応募」を求めても無理がありますし、逆に応募直前の人に「認知」の指標を当てはめても意味がありません。
ここでは、求職者の心理変容を4つのフェーズに分け、それぞれの段階で追うべき「KPIの正解リスト」を網羅的に紹介します。
1. 認知フェーズ(知ってもらう)の指標
まずは「自社の存在を知ってもらう」段階です。どんなに素晴らしい会社でも、知られていなければ選択肢に入りません。
ここでは「接触量の最大化」を測る指標を設定します。
Webサイトの場合(オウンドメディア・採用サイト)
| 指標 |
内容 |
| PV数(ページビュー) |
記事やページが閲覧された延べ回数。 |
| UU数(ユニークユーザー) |
サイトを訪問した「人数」。
同じ人が何度も見ても1人とカウントされるため、
純粋なリーチ数を測るのに適しています。 |
| セッション数 |
訪問の回数。 |
SNSの場合(X, Instagram, Facebook等)
| 指標 |
内容 |
| インプレッション数(表示回数) |
投稿がタイムラインに表示された回数。 |
| リーチ数 |
投稿を見たユニークユーザー数。 |
| フォロワー数 |
継続的に情報を届けられるファンの数。 |
2. 興味・関心フェーズ(自分事化する)の指標
認知された後、「この会社、面白そうだな」「自分に合うかもしれない」と興味を持ってもらう段階です。
ここでは、単に「見た」だけでなく、「どれくらい深く情報を摂取したか」を測る質的な指標が重要になります。
Webサイトの場合
| 指標 |
内容 |
| 平均滞在時間 |
ユーザーが記事を読んでいる時間。
短すぎる場合は「タイトル詐欺」や「内容が薄い」と
判断されている可能性があります。 |
読了率(スクロール率)
|
記事の最後まで到達した割合。 |
ページ回遊率
|
1回の訪問で何ページ見たか。
「社員インタビュー」から「会社概要」へ
遷移しているかなどを確認します。 |
SNSの場合
| 指標 |
内容 |
| エンゲージメント率 |
「いいね」「コメント」「シェア」「保存」などのリアクションの割合。 |
| 保存数 |
特にInstagramなどで重要。
「後で見返したい」=「高い関心」を示すため、
採用につながりやすい指標です。 |
| 動画再生数・視聴完了率 |
動画コンテンツの場合、最後まで見られているかが重要です。 |
3. 応募・行動フェーズ(動いてもらう)の指標
興味を持ったユーザーが、実際に求人への応募や説明会への参加といった「アクション」を起こす段階です。
広報活動が具体的な成果に結びついているかを測る、非常に重要なフェーズです。
| 指標 |
内容 |
| 遷移率(CTR) |
記事やSNS投稿内の「求人ページへのリンク」がクリックされた割合。 |
| エントリーフォーム到達率 |
求人ページを見た人のうち、応募フォームまで進んだ割合。 |
| 応募数(エントリー数) |
実際にフォーム送信が完了した数。 |
| CPA(Cost Per Acquisition:応募単価) |
応募1件を獲得するためにかかった費用(広告費など)。 |
4. 選考・定着フェーズ(質を測る)の指標
ここが多くの企業で見落とされがちなポイントです。単に応募数が増えても、すぐに辞退されたり、ミスマッチで早期離職されたりしては意味がありません。「広報が伝えた内容と、入社後の現実にギャップがないか(採用の質)」を測ります。
| 指標 |
内容 |
| 選考通過率 |
書類選考や面接を通過した割合。
低い場合は、ターゲットではない層からの応募ばかり集めている
(広報のメッセージがズレている)可能性があります。 |
| 内定承諾率 |
内定を出した人のうち、入社を決めた割合。
ここが高い場合、広報コンテンツによって
志望度が十分に高められていたと言えます。 |
| 選考辞退率 |
選考途中で離脱された割合。 |
| 早期離職率(定着率) |
入社後3ヶ月〜1年以内の離職率。
ミスマッチ防止の観点で、長期的に追うべき指標です。
|
KGIから逆算する「KPI計算シミュレーション」の方法
「KPIの指標はわかったけれど、具体的に目標数値をいくつに設定すればいいの?」ここが、多くの担当者が最も頭を悩ませるポイントです。
ここからは、「KPIの逆算シミュレーション」を行います。
「なんとなく月間1万PVを目指す」のではなく、「採用人数(KGI)を達成するためには、論理的に計算すると月間1万PVが必須である」と言えるようになるための計算ロジックです。
Step1. KGI(採用目標人数)とフェーズを整理する
まずはゴールとなるKGI(最終的な採用目標人数)を確認します。
例えば、「半年後までに中途エンジニアを1名採用する」というKGIを設定したとしましょう。
次に、その採用に至るまでの標準的なフロー(フェーズ)を書き出します。
Step2. 「歩留まり率」を設定する(業界平均と自社実績)
次に、各フェーズの間をどれくらいの確率で通過できるかという「歩留まり率(通過率)」を設定します。
自社に過去の採用データがある場合は、その実績値を使用するのが最も正確です。もし実績データがない、またはこれから採用広報を本格化する場合は、一般的な業界平均や肌感値を仮置きして計算します。
ここでは、一般的な中途採用における歩留まり率の例(仮定)を使用します。
中途採用の一般的な歩留まり率
| 項目 |
歩留まり率(通過率) |
実績データ |
| 内定承諾率(内定→入社) |
50% |
内定を出した2人に1人が入社 |
| 面接通過率(面接→内定) |
20% |
最終面接まで進んだ5人に1人に内定 |
| 書類選考通過率(応募→面接) |
20% |
応募者の5人に1人が書類通過 |
| 応募率/CVR(閲覧→応募) |
1.0% |
採用広報記事を読んだ100人に1人が応募 |
歩留まり率の設定イメージ
%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86.png?width=900&height=500&name=%E6%AD%A9%E7%95%99%E3%81%BE%E3%82%8A%E7%8E%87(%E9%80%9A%E9%81%8E%E7%8E%87)%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86.png)
Step3. 採用目標を達成するために必要なPV・応募数は?
それでは、実際に計算してみましょう。
例として、目標を「5名の採用(入社)」とします。
1. 内定は何人に出すべきか?
| 目標 |
5名入社 |
| 内定承諾率 |
50% |
| 【KPI】内定出し数 |
5名 ÷ 0.5 = 10名 |
2. 面接は何人実施すべきか?
| 目標 |
10名に内定 |
面接通過率(全体)
|
20% |
| 【KPI】面接実施人数 |
10名 ÷ 0.2 = 50名 |
3. 応募(エントリー)は何件必要か?
| 目標 |
10名と面接 |
| 書類選考通過率 |
20% |
| 【KPI】必要応募数 |
50名 ÷ 0.2 = 250名 |
4. 記事のPV数は何件必要か?
| 目標 |
250件の応募 |
応募率(CVR)
|
1.0% |
| 【KPI】必要PV数 |
250件 ÷ 0.01 = 25,000 PV |
いかがでしょうか。
このように逆算することで、「エンジニアを5名採用するためには、採用広報で月間25,000PVを獲得し、250件の応募を集める必要がある」というロジックが完成します。
もし上司に「25,000PVも必要なのか?」「コストがかかりすぎる」と言われた場合も、このロジックがあれば冷静に説得できます。
このように、「どの係数を改善すればKGIを達成できるか」という建設的な議論が可能になるのです。これこそが、KPIを設定する最大の価値です。
【重要】広報担当が「採用決定数」をKPIにしてはいけない理由
前章のシミュレーションで、KGI(採用決定数)からKPIを逆算する方法を解説しました。しかし、ここで一つ、あなた自身の身を守るために非常に重要な注意点があります。
それは、「採用広報担当個人のKPIとして『採用決定数』そのものを設定してはいけない」ということです。
「えっ? 採用が目的なのに?」と思われるかもしれません。しかし、ここを混同すると、あなたの努力ではコントロールできない要因で評価を下げられ、モチベーションを失う原因になります。
「広報の責任」と「人事の責任」の境界線(分界点)
採用活動は、大きく「集める(母集団形成)」と「育てる(意欲向上・ミスマッチ防止)」、そして「見極める・口説く(選考)」の3つのプロセスに分かれます。
あなたの認識の通り、採用広報の役割は、単に「応募者を集めること」だけに留まりません。
応募前の段階から広報コンテンツを通じて企業理解を深めさせることで、候補者の選考に進む決意を固めさせたり、選考中・内定後の辞退を回避する重要な役割を担っています。
もし、あなたが素晴らしい候補者を100人集め、十分な動機付けも行ったとしましょう。しかし、面接官の態度が悪かったり、提示された給与条件が市場相場より低かったりして、結果的に誰も入社しなかったとしたらどうでしょうか? これで「採用人数ゼロだから、広報の成果もゼロ」と評価されるのは不公平です。
広報の努力だけでコントロールできない「最終的な採用決定」をKPIにすべきではありません。
そのため、採用広報担当としてのKPIは、広報が直接影響を与えられる範囲、すなわち「選考のテーブルに乗せるまで」と「選考・内定段階での歩留まりに貢献すること」に設定することをおすすめします。
ここまでをあなたの責任範囲とし、「私はこれだけ質の高い母集団を、これだけの数、選考へ送り、さらに選考体験の土台を築きました」と言える状態を作ることが、採用広報を正しく評価するためのポイントです。
「数」より「質」を証明するKPI(意欲向上・ミスマッチ防止)
上司からよくある指摘として、「応募数は増えたけど、質の悪い応募ばかりじゃないか?」というものがあります。
この「質」の懸念に対して、広報担当はどう反論すべきでしょうか。
ここで追うべきなのが、広報が貢献した「ミスマッチ防止」と「選考意欲の向上」に関するKPIです。
単に応募数を追うのではなく、「広報コンテンツに触れた人」と「触れていない人」で、その後の歩留まり率に差があるかを確認してみてください。
|
選考通過率の比較
(ミスマッチ防止)
|
「社員インタビューを読んだ応募者は、読んでいない応募者よりも、一次面接通過率が20%高い」 |
内定承諾率の比較
(辞退回避・意欲向上) |
「オウンドメディア経由の応募者は、会社への理解度が深く、内定承諾率が他チャネルより高い」 |
もしこのようなデータが出せれば、あなたの広報活動は「ただ数を集めた」だけでなく、「自社のカルチャーに合う質の高い人材をスクリーニングし、選考への意欲を高めて集めた」という証明になります。
KPIを絵に描いた餅にしないためのPDCA運用
苦労して計算式を組み立て、KPIを設定しても、それが「設定しただけ」で終わってしまっては意味がありません。
採用広報の状況は日々変化します。目標(KGI)に到達するためには、定期的に現在地を確認し、軌道修正を行うPDCAサイクルが不可欠です。
ここでは、形骸化させず、実効性のある運用を行うためのルーチンを紹介します。
週次・月次でチェックすべき項目と改善アクション
KPI管理は「見る頻度」によって役割が異なります。
全てを毎日見る必要はありません。チェック項目を決めて、週次・月次で数値を確認するようにしましょう。
【週次】健康診断(異常がないかチェック)
- 見るべき指標: PV数、SNSインプレッション数、応募数(速報値)
- アクション:
-
- 「今週はSNSの伸びが悪いな、投稿時間が悪かったか?」
- 「急に応募が増えた。どの記事がバズった?」
- 大きな異常値がないかを確認し、短期的な投稿スケジュールの微調整を行います。
【月次】精密検査(戦略の見直し)
- 見るべき指標: 各フェーズの歩留まり率(CVR、通過率)、CPA(応募単価)、KGIに対する進捗率
- アクション:
-
- 「PVは目標通りだが、応募率(CVR)が先月より落ちている。記事下の導線バナーを変更しよう」
- 「応募数は足りているが、書類通過率が悪い。ターゲット設定を見直して、より専門的な記事を増やそう」
- ボトルネックを特定し、翌月のコンテンツ企画や予算配分を変更します。
KPI未達時に見直すべきポイント(ボトルネックの発見)
KPIが未達だった場合、焦ってやみくもに行動量を増やすのは逆効果です。
前述の「計算シミュレーション」で整理したフェーズのどこが詰まっているか(ボトルネック)を特定し、そこだけを改善します。
「認知(PV)」が足りない場合
- 原因:コンテンツの露出不足。
- 対策:SNSでの拡散回数を増やす、社員にシェアを依頼する、Web広告を検討する。
「応募(CV)」が足りない場合
- 原因:記事は読まれているが、魅力が伝わっていない。または応募ボタンが見つけにくい。
- 対策:記事の末尾に魅力的なオファー(CTA)を置く、社員のリアルな声を増やして共感を高める、エントリーフォームの項目を減らす。
「採用(KGI)」が足りない場合(歩留まり悪化)
- 原因:ミスマッチな人材からの応募が多い。
- 対策:キラキラした情報だけでなく、仕事の厳しさやリアルな情報を発信し(RJP)、カルチャーに合う人だけをスクリーニングする内容にシフトする。
正確なKPI測定と改善には「リソース」と「専門性」が不可欠
ここまで、KPIを設定から運用方法までを解説してきました。
最後に一つだけ、現場の担当者が直面する「現実的な壁」についてお話しさせてください。
採用広報を一人で回す限界(兼任担当者の苦悩)
あなたは今、採用広報以外にも、面接調整、スカウトメールの送信、エージェント対応、もしかすると労務管理まで、多くの業務を兼任していませんか?
正直に申し上げます。「高品質な記事を執筆し、SNSを毎日更新し、さらに今回解説したような複雑なKPI分析を行って、毎月改善レポートを作る」……これを一人で完璧にこなすのは、物理的に限界があります。
多くの担当者が、KPIを設定したものの、日々の業務に忙殺されて数値入力がおろそかになり、結局「今月もなんとなく記事を書いただけ」という状態に戻ってしまうのです。
戦略設計から数値分析まで任せられる「リクルーティングPR-X」
「ロジックは理解したが、それを実行し続けるリソースがない」
「上司へのレポート作成だけで日が暮れてしまう」
もしそう感じているのであれば、戦略と運用のプロに頼るのも一つの経営判断です。
弊社が提供する「リクルーティングPR-X」は、今回解説したようなKPI設定を含めた戦略設計から丸ごと支援します。
しかも、初めての方でもリスクなく導入いただける「5つの特徴」があります。
|
特徴
|
解説 |
|
1記事3万円の低価格
|
業界最安級の価格設定です。 |
|
初期費用・固定費ゼロ
|
制作記事・動画に対応する従量課金制です。 |
| KPI設定・戦略設計付き |
KGIから逆算した設計図もセットでご提供します。 |
| 全額返金保証 |
納品後、内容にご満足いただけなかった場合は
制作費用を全額を返金いたします。 |
| 最低契約期間なし(縛りなし) |
「まずは1ヶ月だけ」といったスモールスタートが可能。
いつでも解約OKです。 |
あなたが社内で説明責任を果たすための「根拠あるデータ」と「成果」は私たちが用意します。あなたは、本来注力すべき「候補者とのコミュニケーション」や「面接」に集中してください。
まずは無料相談で、貴社の現在のKGIを教えていただけませんか?
目標達成に必要なKPIシミュレーションを、私たちが一緒に作成します。
>>「リクルーティングPR-X」のサービス詳細・無料相談はこちら
採用広報KPIに関するよくある質問(FAQ)
最後に、採用広報のKPIについてよく寄せられる質問に回答します。
まとめ:適切なKPI設定で、採用広報の「価値」を証明しよう
本記事では、採用広報におけるKPI設定の重要性と、具体的な計算ロジックについて解説しました。
採用広報は、正しく行えば企業の採用力を底上げする資産になります。
感覚論ではなく「数字」という共通言語を使って、活動の価値を正しく証明し、採用成功というゴールを目指しましょう。
もし、KPIの設計や運用で迷うことがあれば、いつでも「リクルーティングPR-X」にご相談ください。あなたの活動を、全力でサポートいたします。







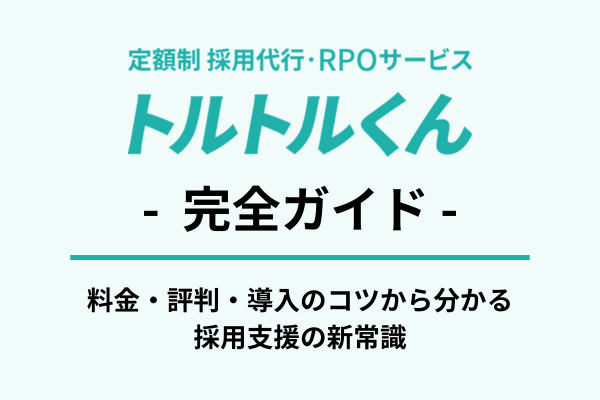

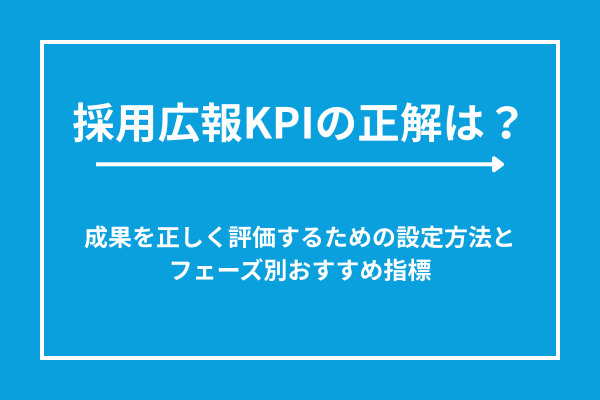



%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86.png?width=900&height=500&name=%E6%AD%A9%E7%95%99%E3%81%BE%E3%82%8A%E7%8E%87(%E9%80%9A%E9%81%8E%E7%8E%87)%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86.png)
