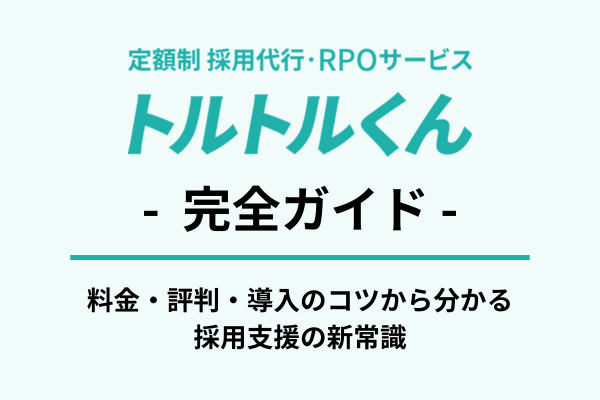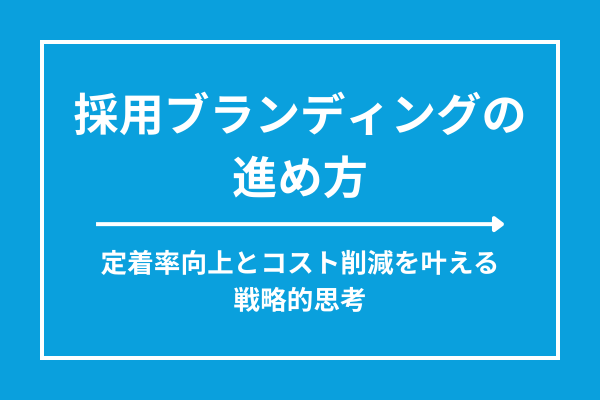「求人媒体に広告を出しても、以前のように応募が集まらない」
「せっかく採用した若手が、『思っていたのと違う』と早期離職してしまう」
「経営層から『当社のブランド力を強化して優秀な人材を採れ』と言われたが、何から手をつければいいか分からない」
採用市場が売り手市場へと変化する中、このような悩みを抱える採用担当者様は少なくありません。
特に実務と戦略の両方を考えなければいけない担当者様にとって、経営層からの抽象的な指示と、現場の実情との板挟みになることは大きなストレスではないでしょうか。
「採用ブランディング」は、単に綺麗な採用サイトを作ることではありません。
それは、自社の「らしさ」を定義することで応募数増加や内定辞退の防止といった採用成果を最大化し、さらには現場社員を巻き込みながら組織そのものを強くしていくプロジェクトです。
本記事では、「採用広報」との明確な違いから、具体的な実践方法まで徹底的に解説します。
採用ブランディングとは?「採用広報」との決定的な違い
「採用ブランディングに取り組もう」と考えたとき、最初につまずきがちなのが「採用広報」や「採用マーケティング」との混同です。
経営層に予算や計画を承認してもらうためにも、まずはこの言葉の定義を明確にし、「なぜ今ブランディングが必要なのか」を整理しましょう。
採用ブランディングの定義:「選ばれる」必然を作る戦略
採用ブランディングとは、一言で言えば「自社独自の価値(らしさ)を設計し、ターゲットから選ばれる必然性を作ること」です。
よくある誤解として、「採用広報=採用ブランディング」と捉えてしまうケースがありますが、両者の役割は異なります。
| 採用ブランディング(戦略・中身) |
採用広報(戦術・拡散) |
| 「自社はどのような価値を提供する会社か」というコンセプトや魅力そのものを設計すること。 |
設計された魅力を、SNSや求人媒体を通じてターゲットに広く知らせる活動のこと。 |
どれほど素晴らしい広告・広報で認知を集めても、肝心の企業(ブランド)のコンセプトがターゲットに合っていなかったり、実態と乖離があったりすれば、入社・採用には至りません。あるいは、入社しても「思っていたのと違う」とすぐに辞めてしまうでしょう。
【図解】採用ブランディング・採用広報・採用マーケティングの違い
上司や経営層に説明する際は、以下の違いを整理して伝えるとスムーズです。
|
項目
|
採用ブランディング
|
採用マーケティング
|
採用広報
|
|
役割
|
「価値」の設計
|
「市場」の攻略
|
「情報」の伝達
|
|
目的
|
ファン化・共感の獲得
(好きになってもらう)
|
応募数の最大化・効率化
(集める・口説く)
|
認知拡大・露出増加
(知ってもらう)
|
|
主な活動
|
採用コンセプト策定
求める人物像(ペルソナ)設定
自社の魅力(EVP)の言語化
|
市場/競合分析
ターゲット選定
プロセス改善(歩留まり改善)
|
SNS運用
ブログ/記事発信
メディア掲載
|
|
対象
|
候補者の「感情・価値観」
|
候補者の「行動」
|
候補者の「目」
|
この表からも分かるように、採用ブランディングはすべての活動の上位概念に位置します。ここがブレていると、採用マーケティングも採用広報も一貫性を失い、効果が半減してしまいます。

なぜ今、採用ブランディングが不可欠なのか?(3つの背景)
なぜ今、多くの企業がコストをかけてまで採用ブランディングに注力しているのでしょうか。その背景には、採用市場を取り巻く3つの大きな変化があります。
1. 労働人口減少による「選ばれる難易度」の上昇
少子高齢化により、労働市場は完全に「売り手市場」です。企業が求職者を選ぶのではなく、「企業が求職者から選ばれる」時代になりました。
事実、リクルートワークス研究所の調査によると、全国の民間企業の求人総数は約76.5万人であるのに対し、民間企業への就職を希望する学生数は約46.1万人にとどまっています。これは、単純計算で約30.4万人分の求人が充足されず、企業間の人材獲得競争は極めて激しい状況にあることを示唆しています。
給与や条件だけでなく、「この会社で働く意味」というブランド価値がなければ、優秀な人材の選択肢に入ることすら難しくなっています。
2. SNS普及による「透明性」の要求
かつては、企業側が発信する情報(求人広告など)が全てでした。
しかし現在は、SNSや口コミサイトで、社員のリアルな声や退職者の本音が簡単に可視化されます。実態とかけ離れた「良いことだけを言う」発信はすぐに嘘だと見抜かれます。
Thinkings株式会社の調査を見ると、採用活動におけるSNSや口コミサイトの影響力の大きさがわかります。
だからこそ、ありのままの魅力を正しく伝えるブランディングが必要です。
3. Z世代の価値観変化(意味・共感重視)
これからの採用ターゲットとなるZ世代や若手層は、物質的な報酬以上に「共感」や「貢献実感」を重視する傾向にあります。「何をするか(業務内容)」以上に「誰と、どんな想いでやるか(企業文化)」が、入社の決め手となります。
事実、株式会社学情の調査によれば、「パーパス(存在意義)」を制定している企業に「好感が持てる」と回答した学生は約7割、企業のパーパスを知ることで「志望度が上がる」と回答した学生も6割を超えています。
採用担当者と経営層が知るべき導入メリット
「採用ブランディングが重要なのは分かったが、手間と時間をかけてまでやる価値はあるのか?」
経営層や現場の責任者からこのような質問を投げかけられることもあるでしょう。採用ブランディングは広告のように即効性がある施策ではないため、導入には社内の納得感が必要です。
ここで提示すべきは、単なる「イメージアップ」という曖昧な効果ではなく、「採用コストの削減」や「組織力の強化」といった、経営インパクトのある具体的なメリットです。
【採用効率】ミスマッチ低減によるコスト削減と歩留まり改善
採用ブランディングを実施する最大の目的は、母集団の「数」ではなく「質」を劇的に向上させる点にあります。
従来の採用手法では、「とにかく応募数を集める」ことに注力しがちでした。しかし、その結果として、「面接してみたら自社のカルチャーと合わなかった」「内定を出しても競合他社に逃げられた」といった無駄な工数が発生していなかったでしょうか。
採用ブランディングによって、「自社はこういう会社だ」というメッセージが明確になると、以下の好循環が生まれます。
1. スクリーニング効果
採用における最大の失敗は、採用できなかったことではなく、「ミスマッチによる早期離職」です。エン・ジャパンの調査と関連する試算データによると、入社から半年以内に早期離職が発生した場合の企業損失額は、1名あたり約640万円に達すると試算されています。
採用ブランディングによって、自社のカルチャーや厳しさも含めたリアルな情報を発信し、ミスマッチを未然に防ぐことができれば、この損失を直接的に回避できます。
また、自社の価値観に合わない層が応募を控えるようになり、書類選考や一次面接の通過率が向上します。無駄な面接時間が削減され、本当に会うべき候補者にリソースを集中できます。
2. 内定承諾率(歩留まり)の向上
応募時点ですでに企業理念やビジョンに共感しているため、他社と条件面で比較されたとしても、選ばれる確率が高まります。
リクルートマネジメントソリューションズの調査によれば、入社意欲の向上には、企業との接点における「対話」や「納得感」が重要であるとされています。給与など条件面での差別化が難しい中小企業であっても、ブランディングを通じて「自社のビジョン」や「働く意義」への深い共感を得られれば、他社と比較された際に「感情的な結びつき」が決定打となり、内定承諾率を高めることができます。
同様にキャリタスリサーチの調査でも、エントリーや選考の段階では「採用コンセプト」や「企業理念」への理解が学生の行動を後押ししていることが示されています。
3. 採用コストの最適化
採用ブランディングにより「指名検索(会社名での検索)」や「オーガニック応募(広告を経由しない直接応募)」が増加すれば、高額な紹介手数料(年収の30〜35%)がかかる人材紹介エージェントへの依存度を下げることができます。
また、企業の価値観に共感した候補者が集まることで、母集団の「質」が向上し、書類選考や一次面接の通過率が上がり、最終的な入社に至るまでの歩留まりの改善にも期待できます。
無駄な面接工数が削減されることも、間接的なコスト削減効果として無視できません。
【組織強化】既存社員のエンゲージメント向上(インナーブランディング)
これは採用担当者様にとって、「隠れたメリット」です。
採用活動を人事部門だけで完結させず、現場社員を巻き込んでブランディングを行うことで、インナーブランディング(社内への浸透)効果が期待できます。
例えば、若手社員にインタビュー記事への協力を依頼したり、リクルーターとして学生と対話してもらうプロセスを想像してみてください。彼らは、自社の魅力や仕事のやりがいを改めて言語化することになります。
- 「自分たちの会社には、こんな良いところがあったんだ」
- 「学生に夢を語った手前、自分ももっと頑張らなくては」
このように、採用活動を通じて既存社員が自社を見つめ直すことで、エンゲージメント(愛社精神や貢献意欲)が高まります。
さらに、現場社員が採用に関与することで、「人事が勝手に連れてきた新人」ではなく、「自分たちが選んで招き入れた仲間」という当事者意識が芽生えます。これにより、入社後の育成やフォローに対する現場の協力が得やすくなり、結果として新人の定着率向上にもつながるのです。
失敗しない採用ブランディングの進め方【5ステップ】
「採用ブランディング」と聞くと、どうしても「おしゃれな採用サイトを作ること」や「かっこいいコンセプトムービーを作ること」から始めてしまいがちです。しかし、戦略のないクリエイティブは、コストと自己満足で終わってしまいます。
成功への最短ルートは、マーケティングの定石通りに、「分析」から「検証」までの手順を飛ばさずに踏むことです。ここでは、明日から着手できる具体的な5つのステップを解説します。
STEP1:現状分析(3C分析による強みの棚卸し)
最初に行うべきは、自社の立ち位置を客観的に把握することです。ここではマーケティングのフレームワーク「3C分析」が役立ちます。
採用ブランディングに使える『3C分析』
Company
(自社) |
既存社員が感じている魅力や不満は何か。
(自社の理念、事業の強み、社風、制度 など)
「嘘偽りのない実態」を洗い出します。
|
Competitor
(競合) |
採用競合となる企業はどこか。
彼らはどんなメッセージを打ち出し、どんな条件を提示しているか。
他社と比較した際の自社の勝ち筋(差別化ポイント)を探ります。
|
Customer
(候補者) |
ターゲットとなる求職者は何を求めているか。
(給与か、働きやすさか、成長環境か)
市場全体のトレンドはどうなっているか。
|
ポイントは、人事担当者の思い込みだけでなく、現場社員へのアンケートや、エージェントからの客観的な意見を取り入れることです。

STEP2:ペルソナ設計(ターゲットの解像度を高める)
「20代の若手営業職」といった属性だけのターゲット設定では不十分です。
採用ブランディングでは、たった一人の架空の人物像「ペルソナ」を描くことで、メッセージの解像度を高めます。
| 項目 |
例
|
| 基本属性 |
年齢、居住地、現在の職種、年収
|
| 価値観・性格 |
安定志向か挑戦志向か、論理的か感情的か
|
| 現状の悩み |
現職で何に不満を感じているか(例:トップダウンで意見が通らない)
|
| 転職で叶えたいこと |
自分のアイデアを形にしたい、チームで達成感を味わいたい
|
実際に社内で活躍しているエース社員や、最近入社した若手社員をモデルにすると、リアリティのあるペルソナが設定しやすくなります。現場マネージャーにも協力してもらい、具体的な人物像を定義しましょう。
STEP3:採用コンセプトとEVP(従業員価値提案)の策定
分析とペルソナ設定ができたら、自社が提供できる価値を言語化します。
これをEVP(Employee Value Proposition:従業員価値提案)と呼びます。
「なぜ、他社ではなく自社で働くのか?」
この問いに対する明確な答えが、採用コンセプトになります。キャッチーなコピーを作る前に、まずは「誰に(Who)、何を(What)約束する会社なのか」というコアメッセージを固めましょう。
例えば、「安定性」を求めるペルソナに対して「挑戦」ばかりを訴求しても響きません。ペルソナの心に刺さり、かつ競合が真似できない自社独自の価値を言葉にします。
STEP4:情報発信チャネルの選定とクリエイティブ制作
コンセプトが決まったら、それを伝えるための手段(チャネル)を選びます。
代表的なチャネルと特徴をまとめました。
| 代表的なチャネル |
特徴 |
| 採用サイト |
情報の受け皿となる基地。網羅的な情報を掲載。 |
| SNS(X, Instagram等) |
認知拡大や、日常の雰囲気を伝えるのに最適。 |
| 動画メディア |
社員の雰囲気やオフィスの様子を直感的に伝える。 |
| 採用ピッチ資料 |
具体的な事業内容や制度を深く理解してもらう。 |
重要なのは、ペルソナが普段どこで情報を得ているかに合わせることです。そして、どのチャネルでもSTEP3で決めた「コンセプト」からブレない一貫したメッセージを発信し続けることが、ブランド形成の鍵となります。
STEP5:効果検証とPDCA(KPIの設定方法)
採用ブランディングは「やりっぱなし」で終わらせてはいけません。しかし、「採用ブランディングは効果が出るまで時間がかかる」と言われる通り、すぐに結果が見えにくいのも事実です。
そこで、経営層への報告やプロジェクトの進行管理においては、KPI(重要業績評価指標)を「短期的指標」と「長期的指標」に分けて設定することをおすすめします。
短期的KPI(活動量・反響)
- 採用サイトのPV数、滞在時間
- SNSのフォロワー増減、エンゲージメント率(いいね、シェア)
- 説明会への参加率、アンケートでの好意的な回答率
長期的KPI(成果・質):
- 応募数、有効応募率(ターゲット層からの応募割合)
- 内定承諾率、辞退率の低下
- 入社後の定着率、早期離職率の低下
まずは短期的な数値で進捗を可視化しつつ、最終的には長期的な「定着」や「質」の向上を目指すというロードマップを引くことで、社内の理解を得ながら継続的な改善(PDCA)が可能になります。
Z世代・若手に響くブランディングの鉄則
これからの採用活動の主役となるZ世代や若手層は、生まれた時からインターネットがあり、膨大な情報の中から「嘘」を見抜くことに長けています。彼らに選ばれるためには、昭和・平成的な「企業=偉い」「良いことだけを見せる」というスタンスを捨て、現代に即したブランディング戦略へアップデートする必要があります。
「給与や福利厚生をアピールしているのに、若手の反応が鈍い」
「内定を出しても、承諾までの間に連絡が途絶えてしまう」
もしこのような現象が起きているなら、それは貴社のメッセージが「今の若者の価値観」とズレている可能性があります。
ここでは、多くの企業が見落としがちな、2つの鉄則をご紹介します。
「綺麗な嘘」は見抜かれる!リアルと透明性の重要性
かつての採用活動では、企業の「良い側面」だけを切り取って見せることが正解とされていました。しかし、Z世代にとってそれは「隠蔽」や「不誠実」と受け取られかねません。
彼らは企業が発信する公式情報だけでなく、口コミサイトやSNSを駆使して、裏側の情報を徹底的にリサーチします。ポジティブな情報しかない企業よりも、「大変なこと」や「課題」も含めてオープンに語る企業の方を「信頼できる(トラスト)」と判断する傾向があります。
透明性の高い情報発信は、入社後の「リアリティショック」を防ぎ、早期離職を抑制する効果もあります。弱みも含めてさらけ出す勇気こそが、最強のブランディングになります。
社員を「主役」にする現場巻き込み型の発信
人事担当者が作った洗練されたキャッチコピーよりも、現場で働く社員の「等身大の言葉」の方が、何倍も熱量が伝わります。
「採用は人事の仕事」と切り離すのではなく、現場社員を巻き込み、彼らを主役にしたコンテンツを発信しましょう。
| コンテンツ例 |
内容 |
社員インタビュー記事
|
成功談だけでなく、苦労や失敗をどう乗り越えたかを語ってもらう。 |
| 現場社員によるSNS発信 |
日常のオフィス風景やランチの様子など、「空気感」を伝える。 |
| リクルーター面談 |
成功談だけでなく、苦労や失敗をどう乗り越えたかを語ってもらう。 |
これにより、求職者は「自分がこの会社で働いたらどうなるか」を追体験できるようになります。また、前述した通り、社員自身が自社の魅力を発信することで、社員自身のエンゲージメントが高まるという副次効果も期待できます。
採用ブランディングの成功事例
ここでは採用ブランディングの成功事例をご紹介します。企業規模に関わらず成果が出ていることがわかります。
事例1:三和建設株式会社(建設業)

※三和建設株式会社(大阪府/従業員数:約200名)
取り組み
- 採用コンセプト「つくるひとをつくる」: 建設会社でありながら、建物の実績よりも「社員の成長」にフォーカス。「入社すれば成長できる環境がある」ことをブランディングの核に据えた。
- 選考プロセスの差別化: 「プレゼン選考」や、学生と社員が本音で語り合う場を設けるなど、能力よりも価値観のマッチングを重視した選考設計。
- 「ひとづくり寮」の建設: 社員寮を単なる住処ではなく「人間形成の場」として設計し、メディアにも露出させた。
採用ブランディングの成果
- エントリー数の増加: 建設業界の不人気イメージを覆し、数百名単位の学生エントリーを獲得。
- 採用ミスマッチの解消: 「成長したい」という意欲の高い学生が集まるようになり、入社後の定着率が向上。
出展元:「一人の採用に138時間を費やす」三和建設株式会社が導入した「理念共感型」の人財採用戦略とは?(施工の神様)
事例2:株式会社サン技研(機械設計)

※株式会社サン技研(石川県/従業員数:約10名)
取り組み
- 採用サイトのフルリニューアル: これまで「何をしている会社か分かりにくかった」サイトを一新。
- 「未経験でも技術者になれる」ストーリー設計: 具体的な教育体制や、未経験からプロになった先輩社員のインタビューを掲載し、応募のハードル(不安)を取り除いた。
- ハローワーク求人票との連動: 求人票からWebサイトへ誘導する動線を徹底した。
採用ブランディングの成果
- 短期間での採用成功: リニューアル公開後、わずか3週間で応募が発生。
- 採用効率の向上: 結果として、公開直後の期間で7名の応募を獲得し、その中から5名を採用(うちCAD経験者も含む)するという、小規模組織としては異例の成果を上げた。
出展元:採用支援での実績まとめ(株式会社Spring&Co.)
事例3:くら寿司株式会社(飲食・サービス)

※くら寿司(大阪府/従業員数:約2800名)
取り組み
- 採用コンセプトの刷新: 「ただの飲食業」ではなく「食の革命を起こすグローバル企業」としての側面を強調。
- 幹部候補生(通称:グローバル新卒)の採用枠新設: TOEIC800点以上、年収1000万円提示など、従来の飲食業界の常識を覆す条件を提示し、ビジネス感度の高い学生にターゲットを絞った広報を展開。
採用ブランディングの成果
- エントリー層の激変: これまで接点を持てなかった早慶上智などの上位校学生からのエントリーが急増。
- エントリー数増加: 新しい採用ブランディング導入後、エントリー数が前年比で大幅増(年度により150%〜200%増と報道)を記録。
参考:くら寿司が「年収1000万円」で新卒募集するワケ(東洋経済オンライン)
採用ブランディングを成功させるための「外部パートナー」の選び方
ここまで成功事例を見てきましたが、「これを今のリソースだけで自社でやるのは正直厳しい」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
特に他の業務と兼任している採用担当者様にとって、すべての工程を内製化することは、むしろ失敗のリスクを高めることにもなりかねません。
内製化の限界と、プロに頼るべき「客観的視点」
「コストをかけたくないから」と、すべてを自分たちだけで完結させようとすると、以下の「あるある失敗パターン」に陥りがちです。
| 「灯台下暗し」の罠 |
リソース不足による自然消滅 |
| 自社のことは自分たちが一番よく知っているつもりでも、実は「当たり前すぎて強みに気づけない」ことが多々あります。「アットホームな職場」といった、手垢のついた抽象的な言葉に逃げてしまい、他社との差別化が図れなくなります。 |
「毎週ブログを更新する」と決めても、採用繁忙期に入ると更新が止まり、放置されたSNSやブログが逆に「活気のない会社」というネガティブな印象を与えてしまいます。 |
このような事態を防ぐために、プロ(外部パートナー)の力を借りることも検討しましょう。
「戦略」や「最終決定」は社内で握りつつ、「客観的な分析」や「継続的なアウトプット(制作)」は外部に頼るという役割分担こそが、プロジェクトを完遂させる秘訣です。
社内のしがらみがない第三者の視点だからこそ、現場社員から本音を引き出せたり、経営層に対して忖度のない提案ができたりするメリットもあります。一人で抱え込まず、プロを「壁打ち相手」として使う視点を持ちましょう。
採用広報代行「リクルーティングPR-X」が選ばれる理由
もし、貴社が「何から手をつけていいかわからない」「現場の負担を増やさずに発信を続けたい」とお考えなら、採用ブランディング・採用広報代行サービス「リクルーティングPR-X」の活用をご検討ください。
採用ブランディングの核となる「3C分析」や「コンセプト設計」のフェーズから伴走し、貴社だけの勝ち筋を一緒に見つけ出します。
更に、初めての方でもリスクなく導入いただける「5つの特徴」があります。
|
特徴
|
解説 |
|
1記事3万円の低価格
|
業界最安級の価格設定です。 |
|
初期費用・固定費ゼロ
|
制作記事・動画に対応する従量課金制です。 |
| KPI設定・戦略設計付き |
KGIから逆算した設計図もセットでご提供します。 |
| 全額返金保証 |
納品後、内容にご満足いただけなかった場合は
制作費用を全額を返金いたします。 |
| 最低契約期間なし(縛りなし) |
「まずは1ヶ月だけ」といったスモールスタートが可能。
いつでも解約OKです。 |
「まずは自社の現状を整理したい」というだけでも構いません。まずは無料相談で、貴社の採用課題をお聞かせください。
>>リクルーティングPR-Xのサービス詳細・お問い合わせはこちら
採用ブランディングに関するよくある質問(FAQ)
最後に、採用ブランディングに取り組む際によく寄せられる質問と、その回答をまとめました。社内稟議やプロジェクト進行の参考にしてください。
まとめ:採用ブランディングで「選ばれる企業」へ
採用ブランディングは、一朝一夕で完成する魔法の杖ではありません。しかし、労働人口が減少し続ける日本において、企業の未来を作るために「必要な投資」であることは間違いありません。
「自社の魅力は何だろう?」「どんな仲間と働きたいのだろう?」
この問いに向き合い、現場社員と共に作ったブランドは、求職者の心に届き、貴社を「選ばれる企業」へと変えてくれるはずです。
まずは、現状の整理から始めてみませんか? 私たちが全力でサポートいたします。
>>リクルーティングPR-Xのサービスページはこちら
>>ご相談のお問い合わせはこちら